| ◇おしゃべり◇ |
| BBS |


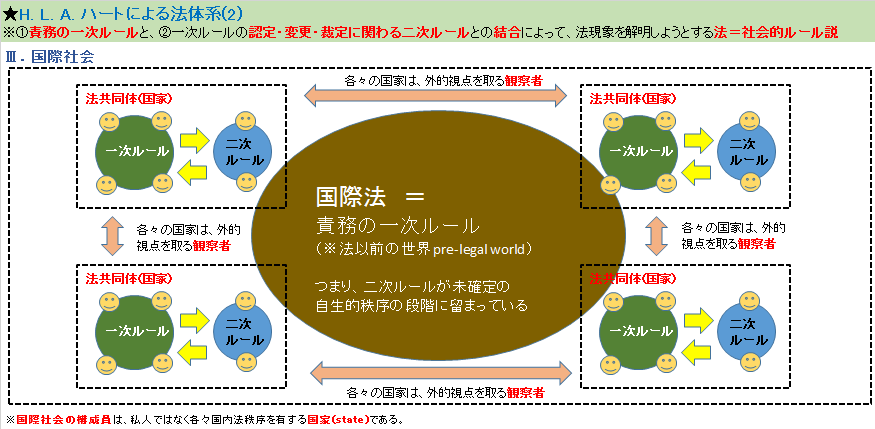
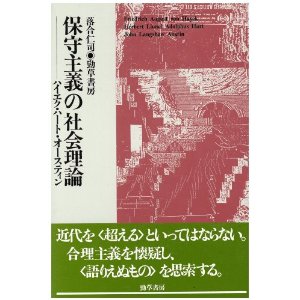 |
『保守主義の社会理論―ハイエク・ハート・オースティン 』(落合 仁司:著) |
| ①F.A.ハイエクの自生的秩序論、②H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)、③J.L.オースティンの言語行為論という20世紀哲学の諸潮流の内的関連性を、④ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論と絡めながら解説し、社会哲学の観点から「20世紀以降の保守主義の社会哲学」を論じた名著。 書中に多々登場する哲学・思想用語を一つ一つ辞書等でチェックしていく根気さえあれば、論旨明快で読みやすいはず。 |
| + | ... |
本書は、現代における保守主義についての、社会哲学的な論述である。
従って、現代の保守主義を対象とした、政治学を始めとする社会科学的な分析とは、差し当たり、関係ない。 本書は、現代の保守主義を、経済哲学や法哲学さらには言語哲学を含む、社会哲学の地平において解釈する試みなのである。 しかし、20世紀末の現代において、何故に、保守主義を、しかも、社会科学ならぬ社会哲学の地平において、取り上げねばならぬのか。 今世紀末は、人間の《或るもの》からの離脱不能性と、人間による《或るもの》の操作不能性とを、倦むことなく語り続けて来た保守の精神からは、恐らく最も遠い処に漂い着いた時代である。 すなわち、今世紀末は、人間の《総てのもの》からの個体的な解放と、人間による《総てのもの》の合理的な制御とを、飽くことなく欲し続けて来た啓蒙の精神が、人類の最も誇るべき価値であるかの如き高みに昇り詰めた時代なのである。 そのような啓蒙主義への、最大の敵対者であった筈の保守主義を、今、何故に、しかも、社会哲学などという非科学的な地平において、取り上げねばならぬのか。 言い換えれば、あたかも啓蒙の進歩主義によって完全に領導されているかに見える、近代社会の唯中にあって、伝統の持続とその解釈などという営為が、果たして、いかなる意味を持ち、また、いかにして可能であるのか。 保守主義の社会哲学、すなわち、伝統の持続とその解釈という営為を引き受けるに当たって、これらの問いを避けて通る訳にはいかない。 しかし、これらの問いに答えることは、外ならぬ本論の課題である。 |
| + | ... |
◆1.世紀末の《近代》我々の時代は、機械と快楽の時代に見える。 産業技術と消費大衆の支配の時代である。 なるほど、この二世紀の間に、産業技術は、蒸気機関と鉄道輸送から電気機器と自動車交通へ、さらには情報処理機器とデータ通信へと大きく移行し、消費大衆は、ブルジョワジーとプロレタリアートから豊かな中間大衆へ、さらには新しい快楽的個人へと激しく変遷してきている。 しかし、技術的な合理主義と大衆的な個人主義の一貫した進展という意味において、この二世紀は、むしろ連続した平面の上にある。 すなわち、我々の時代は、フランス革命と、産業革命さらにはそれに引き続く民主革命とによって解き放たれた、合理主義と個体主義、あるいは産業主義と民主主義という、加速度運動の相の下に捉えられるのである。 言い換えれば、我々の時代は、19世紀と20世紀の200年間を通じて、あらゆる世界を席巻してきた、産業化と民主化という激浪の波頭に位置しているのである。 ここでは、この産業主義と民主主義の二世紀を、《近代》と呼ぶことにしたい。 従って、我々の時代は、20世紀末の《近代》と言うことになる。 この産業主義と民主主義、あるいは合理主義と個体主義の《近代》を称揚する思想は枚挙に暇がない。 近代自然法論や社会契約論、さらには啓蒙思想は言うに及ばず、19世紀以降に限っても、功利主義やマルクス主義、さらにはそれに引き続く、実証主義的な社会科学(たとえば分析法学、新古典派及びケインズ派経済学、機能主義社会学など)やマルクス主義的な社会科学、といった社会思想が、産業化(合理化)と民主化(固体化)の双方あるいはいずれか一方を、積極的に推進すべく、その言論を展開している。 産業主義(合理主義)あるいは民主主義(個体主義)を称揚する、これらの社会思想こそ、このニ世紀を通じて、進歩主義と呼び習わされて来た思想に外ならない。 《近代》の進歩主義は、功利主義とマルクス主義とに端を発する、《近代》社会科学によって担われて来たと言っても、決して言い過ぎではないのである。 《近代》の進歩主義は、言うまでもなく、極めて多様な傾向を孕んでいる。 そこには、自由主義的な傾向も存在すれば、社会主義的な傾向も存在する。 しかし、いずれの傾向も、その力点の置き方に多少の違いはあるとしても、合理主義と個体主義を信奉することにおいて、いささかも選ぶ処はない。 《近代》進歩主義は、人間とその社会を、理性によって目的合理的に制御し得るし、また、そうすべきである、と考える合理主義と、人間とその社会を、個体的な欲求充足に還元し得るし、また、そうすべきである、と考える個体主義とを、その共通の前提としているのである。 進歩主義は、このニ世紀に亘って、社会の合理的な管理と人間の個体的な解放という二つのスローガンを、倦むこと無く主張し続けてきた。 このニ世紀に亘って進行した、産業化あるいは管理化と、民主化あるいは大衆化という二重革命は、このような進歩主義を、その思想的な前提とし、また帰結ともしているのである。 しかし、このような産業化と民主化の進行、あるいは進歩主義の哲学に対する懐疑もまた跡を絶たない。 合理主義と個体主義の哲学に対する懐疑は、《近代》思想史のいわば裏面を形成している。 たとえば、20世紀を代表する、ウィトゲンシュタインや日常言語学派、あるいは現象学や解釈学、さらには構造主義やポスト構造主義の哲学は、多かれ少なかれ、合理主義と個体主義に対する懐疑を、その発条(バネ)として展開されている。 しかし、合理主義と個体主義に対する懐疑の歴史において、決して逸することの許されないのは、フランス革命の産み落とした合理主義と個体主義の狂気に対して、敢然と立ち向かったバーク以来の保守主義の伝統である。 保守主義は、産業化と民主化の進行とともに、怒涛の如く進撃してきた進歩主義の哲学に抗して、200年このかた、《近代》への懐疑の哲学を守り続けてきた。 合理主義と個体主義に対する懐疑の伝統は、取りも直さず、《近代》保守主義の伝統に外ならないのである。 この意味において、ウィトゲンシュタインや日常言語学派の哲学といった20世紀思想もまた、《近代》保守主義の伝統の現代的な表現である、と言って言えなくもない。 本書もまた、このような《近代》保守主義の伝統に棹さして、20世紀末における、その今日的な表現を模索する試みに外ならないのである。 《近代》の保守主義は、人間とその社会を、理性によって意識的に制御する可能性を疑う。 人間の行為は、合理的には言及し得ない偏見や暗黙知を前提として始めて可能になるのであって、意識的には制御し尽くせないからである。 また、保守主義は、人間とその社会を、個体の意図に還元する可能性を疑う。 人間の行為は、個体には帰属し得ない権威やルールに依存して始めて可能になるのであって、その意図に還元し尽くせないからである。 このように合理主義と個体主義を懐疑する立脚点こそ、伝統あるいは慣習と呼ばれるものに外ならない。 すなわち、伝統あるいは慣習とは、行為の持続的な遂行の結果として生成される秩序であるにも拘わらず、行為の意識的な対象としては制御不能であり(偏見あるいは暗黙知)、かつ、行為の主観的な意図には還元不能である(権威あるいはルール)何ものかである。 言い換えれば、伝統あるいは慣習とは、人間の行為によって生成される秩序であって、自らの存在を理由付けるいかなる根拠も持ち得ない(偏見あるいは暗黙知)にも拘わらず、自らは行為の当否を判定する根拠となり得る(権威あるいはルール)というものなのである。 保守主義は、このような伝統あるいは慣習こそが、人間とその社会の存在を辛くも可能にするのである、と主張する。 保守主義から見れば、合理主義は、人間とその社会の制御不能性を閉脚した、理性の専制支配に外ならず、また、個体主義は、人間とその社会の還元不能性を無視した、個体のアナーキーに外ならない。 《近代》保守主義は、このように合理主義と個体主義とを懐疑することによって、《近代》進歩主義の蛇蝎の如く忌み嫌う、伝統や偏見や権威やへの信仰を擁護するのである。 本書は、このような保守主義の、20世紀における新たな相貌を彫塑してみたい。 元来、保守主義は、その時代における進歩主義の様々な意匠に応じて、幾度となく変貌を繰り返しながら、進歩への疑いを懐き続けて来た。 保守主義の歴史は、進歩への懐疑という動機による、変奏曲の歴史なのである。 従って、我々の時代の保守主義もまた、進歩主義の新機軸に応じて、新たな衣装を纏いつつ立ち現われている筈である。 本書は、そのような20世紀末の新しい保守主義の容貌を、明瞭に写し撮ってみたいのである。 何故ならば、保守主義を論ずることは、産業化と民主化の行き着く処まで行き着いてしまったかに見えるこの時代、技術的な管理と快楽的な大衆ばかりが跳梁跋扈するこの時代を懐疑する、最も確かな立脚点となり得るからである。 さらにまた、保守主義を論ずることは、合理主義と個体主義とによって塗り固められた、《近代》社会科学の城壁に、蟻の一穴を穿つ社会哲学の、最も確かな橋頭堡となり得るからである。 ◆2.自生的秩序・ルール・言語行為我々の時代の保守主義を論ずることは、しかし、かなり逆説的な課題である。
バークが《近代》保守主義の生誕を高らかに宣言した時代には、その背景に、土地と議会を支配したジェントルマン達の貴族主義が、確固として存在していた。 保守主義は、ブルジョワ的産業主義と大衆的民主主義に反対する、ジェントルマンのイデオロギー足り得たのである。 しかし、ニ世紀に亘る、産業化と民主化の津波のような進撃が、あらゆる種類の貴族主義を粉砕し尽くし、技術と大衆が完全に勝利を収めた、我々の時代の保守主義には、いかなる階層的な基盤も期待し得ない。 我々の時代の保守主義は、支配階層のイデオロギーといったものではあり得ないのである。 我々の時代を支配しているのは、むしろ技術と大衆なのであって、それらを称揚する思想は、進歩主義でこそあれ、保守主義などでは全くあり得ない。 我々の時代の支配的なイデオロギーは、支配的であるがゆえに保守的であるという訳には、必ずしもいかないのである。 しかし、支配的であるものを擁護することが、必ずしも保守的であるとは限らないという状況は、かなり逆説的であると言う外はない。 このような状況において、保守主義は、いかに立ち現われるのであろうか。 我々の時代の保守主義を論ずるためには、この問いを避けて通る訳にはいかない。 これが、保守主義を20世紀末の今日において論ずることの引き起こす、差し当たりの困難である。 保守主義を論ずることは、しかし、より根本的な困難を孕んでいる。 保守主義を論ずることは、取りも直さず、自然発生的に形成される伝統や、合理的には言及し得ない偏見や、個体的には帰属し得ない権威やを論ずることに外ならないが、これらの伝統や偏見や権威やは、むしろ言葉によっては語り得ず、ただ行為において示される類いのものなのである。 すなわち、保守主義を論ずることは、語り得ぬものを語らねばならぬという困難を抱え込むことに等しいのである。 しかし、この困難は、保守主義が、合理主義と個体主義を否定することにおいて始めて成立したという、その出生の秘密の内に、既に孕まれたアポリア(※注釈:aporia 論理的正解を見出し辛い難問)である。 すなわち、保守主義は、客観的には言及し得ず、主観的には帰属し得ない、主客いずれでもあり得ない、言い換えれば、「~ではない」としか語り得ないものとして、この世に産み落とされたのである。 従って、保守主義を論ずることは、極めて逆説的な作業となる。 すなわち、保守主義は、進歩主義の称揚する諸価値を否定する作業の積み重ねの彼方に、いわば描き残された空白として、立ち現われて来るのである。 この意味において、保守主義の擁護する伝統は、《空の玉座》である。 すなわち、一切の存在は玉座を指し示しているにも拘わらず、そこに鎮座すべき王は永遠に不在なのである。 現代の保守主義を論ずることに纏わる、これらの困難を切り抜けるために、本書は、20世紀における、必ずしも保守主義者とは自認していない、合理主義と個体主義の批判者達の言説を取り上げてみたい。 何故ならば、現代の保守主義は、支配的なイデオロギーを喧伝している、自称保守主義者達の言説によく現れているとは考え難いからであり、また、現代の保守主義と言えども、合理主義と個体主義とを否定する言説の隙間にしか、決して立ち現われ得ないからである。 本書は、このような現代における啓蒙の批判者として、F・A・ハイエク、H・L・A・ハート、J・L・オースティンの三者を取り上げることにする。 言うまでもなく、現代における合理主義と個体主義の批判は、この三者のような、ウィトゲンシュタインに近い筋や日常言語学派からのそれのみならず、現象学や解釈学からのそれ、あるいは、構造主義やポスト構造主義からのそれといった、様々な潮流によって担われている。 20世紀思想の主だった潮流は、押しなべて合理主義と個体主義の批判に従事していると言っても、決して過言ではないのである。 それらの諸潮流の中から、主としてイギリス(あるいは英米圏)をその活躍の舞台とした、ハイエク・ハート・オースティンの三者を選択する理由は外でもない。 このニ世紀の間、《近代》進歩主義に抗して、最も激しく戦い抜いてきた、イギリス保守主義の伝統に、ささやかな敬意を表したいからである。 イギリスは、産業革命と民主革命の祖国であるとともに、《近代》保守主義のいつかは還るべき《イェルサレム》なのである。
彼ら三者は、無視し得ない差異を留保しつつも、合理主義あるいは実証主義と、個体主義あるいは主権主義とに対する懐疑を共有している。 すなわち、彼らは、その力点の置き方にかなりの相違を認めるとしても、世界に対する、合理的な制御あるいは言及の可能性を疑い、また、社会の、個体的な意志への還元あるいは帰属の可能性を疑っているのである。 さらに、彼らが、そのような懐疑の立脚点として提出する、自生的秩序、ルール、言語行為の諸概念もまた、ある幾つかの特徴を共有している。 すなわち、これらの諸概念は、行為の結果として慣習的に生成されるにも拘わらず、(制御や言及やといった)行為の対象とはなり得ない暗黙的な事態であり、かつ行為を妥当させる規範的な根拠となる、といった諸特徴のいずれかを、必ず指し示しているのである。 このような自生的秩序・ルール・言語行為の諸概念が、ウィトゲンシュタインの言語ゲームの概念と、言わば家族的に類似していることは、注目されてよい。 言語ゲームは、人間の行為の遂行は総て言語ゲームの遂行とならざるを得ないという意味において、行為を拘束する(規範的な)事態であり、また、自らの総体を対象とした(その正当化をも含む)いかなる言及をも許さないという意味において、暗黙的な事態である。 すなわち、言語ゲームとは、自らにあらゆる行為を従属させるとともに、自らは如何なる根拠をも保持し得ない、いわば慣習的な事態なのである。 このような言語ゲームの概念は、自生的秩序・ルール・言語行為の諸概念と、そのかなりの特徴を共有している。 保守主義を論ずるに当たって、言語ゲーム論は、極めて魅力的な題材を提供しているのである。 しかし、本書は、ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論を、明示的には取り扱わない。 一つには、ウィトゲンシュタインのテクストを解釈する作業が、解釈の可能性それ自体をも含めて、かなりの錯綜した課題と見受けられるからであり、二つには、言語ゲーム論と、わけてもハートのルール論との相互関係をめぐる、極めて鮮やかな分析が、近年、橋爪大三郎によって為されているからである(※原注1:橋爪大三郎『言語ゲームと社会理論-ウィトゲンシュタイン・ハート・ルーマン-』勁草書房 1985)。 従って、本書に現れる言語ゲーム論は、ハイエク・ハート・オースティンのテクストの解釈に投影された、その射影に過ぎない。 しかし読者は、本書に落とされた、ウィトゲンシュタインの長い影を、やはり鮮やかに見いだす筈である。 何故ならば、ウィトゲンシュタインこそが、20世紀思想の諸結果と、保守主義の伝統とを結び付ける、あの《失われた環》(※注釈:missing link)に外ならないと想われるからである。 以上のような、ハイエクの自生的秩序論、ハートのルール論、オースティンの言語行為論、さらには、ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論が、現代における保守主義の在処(ありか)を発見する、最も有力な手掛かりとなることは明らかであろう。 保守主義の変わらぬ拠り処は、遂行的に生成される伝統であり、合理的には言及し得ぬ偏見であり、個体的には帰属し得ぬ権威であった。 自生的秩序やルールや言語行為やさらに言語ゲームといった、20世紀思想の指し示すものは、遂行的に生成される慣習的な事態であり、合理的には言及し得ぬ暗黙的な事態であり、個体的には帰属し得ぬ規範的な事態である。 従って、保守主義とこれら20世紀思想の間には、ほとんど完全な同型対応が存在していることになる。 あるいは、これら20世紀思想は、むしろ保守主義の現代における新たな表現であると言ってもよい。 すなわち、保守主義は、これら20世紀思想に身を託して、この20世紀末の現代に立ち現われた、と言って言えないことはないのである。 しかし、これらの議論の当否は、本論に委ねることにしよう |
| + | ... |
◆1.産業主義と合理主義産業主義と民主主義を懐疑することなど、しかし、この20世紀末の現代において、果たして可能なのだろうか。 我々の日々の生は、産業化と民主化の奔流の中で、ただ木の葉のように翻弄されているに過ぎないのではないか。 我々は誰しも、もちろん私自身をも含めて、何程かは、効率的な経済人であり、また、快楽的な大衆人なのである。 このような我々の日常を懐疑することは、つまるところ、我々の日常の一切を否定し去ることになるのではないか。 しかし、およそ保守主義を論じようとする姿勢の内に、我々の日常の一切を否定し去ろうとする態度の含まれよう筈もない。 いやしくも保守主義と呼びうる思想には、いまここに生きられている現実への肯定が、何程かは含まれている筈である。 従って、現代における保守主義もまた、この産業主義と民主主義に魅入られた20世紀末の現実の唯中に、肯定すべき某(なにがし)かの価値を見い出していることになる。 あるいは、そのように肯定されるべき現実こそが、産業主義と民主主義に対する懐疑の疑い得ぬ立脚点なのである、と言い換えてもよい。 保守主義とは、いまここに生きられる世界に定位して、この世界の合理的な制御や個体的な還元やの、むしろ幻影であることを暴き出す営為に外ならないのである。 それでは、産業主義と民主主義の幻影は、何故に疑い得ぬ現実の姿を取って、立ち現れ得るのであろうか。 言うまでもなく、産業主義とは、絶えざる技術革新を起爆力とする、人間と社会の不断の再組織の運動である。 この運動によって追求されているのは、自然や社会や人間自身に対する制御能力の拡大、生産力の増強、効率の上昇、合理化といった、目的達成のために利用可能な手段の拡大と、その有効適切な選択の推進である。 この手段的な可能性の拡大と、その効率的な利用を追求する態度こそ、合理主義と呼ばれるに相応しい。 マックス・ウェーバーの言う目的合理性であり、タルコット・パーソンズの言う能動的手段主義である。 すなわち、産業革命によって解き放たれたこの産業主義という運動は、合理主義をその中核的な価値としているのである。 もっとも、合理主義という言葉は、効率的な手段の追求という意味に限定されている訳ではない。 元来、合理主義とは、人間理性の尊重、あるいは理性による支配の貫徹の謂であって、その理性をどのように捉えるかによって、様々な意味に分散し得る。 理性を、目的に対して効果的な手段を選択する能力として捉えるならば、いまここで述べた合理主義の意味が出て来よう。 この意味における合理主義を、他と区別する場合には、手段的あるいは機能的合理主義と呼ぶことが多い。 この手段的合理主義と、いわゆる近代合理主義との関係は、いささか微妙である。 なるほど、手段的合理主義は、主体がその目的い適合するように客体を制御する能力を良しとするのであるから、主体と客体の分離を前提するという意味においては、近代合理主義と軌を一にしている。 しかし、手段的合理主義は、必ずしも論理整合的に推論する能力としての理性のみによって、効率的な手段を選択し得るとは考えないのであって、近代経験主義と対立する意味における近代合理主義とは、一線を画しているのである。 この意味においては、手段的合理主義は、むしろ近代経験主義の後裔をもって自認している、各種の実証主義に近しい。 主観とは分離された客観的な事実によって、その真偽を検証し得る命題のみが有意味であるとする実証主義(※注釈:論理実証主義 logocal positivism)は、選択した手段のもたらす結果についての実証的な知識こそが、効果的な手段の選択には不可欠であると考える手段的合理主義の、認識論的な前提となっているのである。 あるいは、むしろ検証可能性の拡大こそが人間の進歩であると考える実証主義は、制御可能性の拡大こそが人間の進歩であると考える手段的合理主義の、最も典型的な現れであるとも言えよう。 行為論における手段的合理主義と、認識論における実証主義とは、言わば同型的に対応しているのである。 ハイエクが批判するのは、このような手段的合理主義である。 ハイエクの用語系では、手段的合理主義は、構成的合理主義(constructivist rationalism)と呼ばれる(※注釈:ハイエク著『法と立法と自由』では「設計主義的合理主義」と翻訳されているが、こちらの方が良訳である)。 構成的合理主義とは、およそ人間の行為と社会は、何等かの目的の達成のために、意識的に組織され管理され計画され操作され制御され構成されており、また、そうされるべきだとする考え方である。 すなわち、人間の行為と社会は、それを対象として捉える人間の理性によって、意識的に構成し得るし、また、すべきだと言うのである。 ハイエクによれば、この構成的合理主義の淵源は、デカルトの合理主義に遡り得る。 デカルトによる思考する主体と思考される客体の分離は、構成的合理主義の必要条件を準備するものであり、また、明証的な前提から論理的に演繹された知識のみが、疑い得ぬ確実な知識であるとするデカルトの合理主義的確証主義は、意識的に計画され構成された行為のみが、目的達成にとって有効な行為であるとする構成的合理主義と、その精神の態度を共有するものである。 すなわち、明晰で意識的な理性によって根拠付けられたもののみを信仰するという態度において、構成的合理主義は、デカルト的合理主義の紛れもない後裔なのである。 しかし、そうであるからといって、この構成的合理主義が、実証主義と対立する訳ではいささかもない。 実証主義とは、客観的な事実によって検証可能な知識のみが、疑い得ぬ確実な知識であるとする経験主義的確証主義なのであって、明晰な理性によっても疑い得ぬ絶対確実な知識を希求する確証主義という意味においては、デカルト的合理主義と選ぶ処はないのである。 従って、構成的合理主義とは、意識的な理性によっては確証され得ない一切のものを懐疑する、過激な懐疑主義の運動なのであるともいえよう。 このような構成的合理主義から見れば、伝統や慣習といった、必ずしも意識的に設計された訳ではない社会制度は、合理的な根拠のない偏見や因習として侮辱される。 伝統や慣習の軛(くびき)から解き放たれて、社会を合理的に再編成していく能力こそ、人間の理性には相応しいと言うのである。 ハイエクは、何等かの具体的な目的を達成すべく意識的に設計された社会秩序を、組織(organization)あるいはタクシス(taxis)と呼ぶ。 すなわち、組織とは、あらゆる行為を、達成されるべき目的によって評価し、配列する社会である。 ハイエクによれば、社会主義はもとより、ケインズ的なマクロ経済政策や規制などのミクロ経済政策といった、市場経済への政府介入もまた、たとえば経済的福祉という目的を達成するために、社会を一つの組織に再編成しようとする試みに外ならない。 すなわち、福祉主義をも含むあらゆるタイプの社会主義(コミューン主義、民主社会主義、ケインズ主義、国家社会主義、福祉国家、行政国家など)は、社会の総ての行為を、組織の目的に対する貢献によって評価し、配列しようとする試みなのである。 構成的合理主義、あるいは様々なタイプの社会主義は、社会を制御するための政策や手段をも含む総ての社会的行為を、それが社会にもたらすであろう帰結の、達成すべき目的に照らした優劣によって評価するのであるから、行為をその帰結によって評価するという意味における帰結主義(※注釈:consequentialism 結果主義。倫理学 ethics において、ある行為の価値は結果の良し悪しによって定まるとする学説)を含意している。 因みに、福祉主義あるいは功利主義は、典型的な帰結主義である。 この帰結主義が成功し得るためには、様々な行為のもたらす社会的な帰結の予測し得ることが不可欠である。 社会の制御を目指す政策や手段を含む様々な行為が、如何なる帰結を社会にもたらすかを予測し得て始めて、その合目的的な評価も可能になるのである。 従って、帰結主義、さらには構成的合理主義が、社会を合目的的に組織し得るか否かは、社会現象の予測可能性に懸かっていることになる。 言うまでもなく、意識的な理性に全幅の信頼を置く構成的合理主義は、社会現象の具体的な予測も原理的には可能であると、誇らしげに主張するのである。 この社会現象についての予測能力こそ、実証主義を標榜する社会科学の求めて止まぬものである。 実証主義的な社会科学は、社会を合理的に組織するための前提として役に立つ、社会予測を提供することを、その最終的な目的としているのである。 このような社会科学が標榜する実証主義とは、科学的な命題は、明証的な前提から論理的に演繹し得る命題か、あるいは、客観的な事実によって検証可能な命題のいずれかのみであるとする知識論である。 すなわち、社会をめぐる知識に対しても、真なる知識は、明晰な理性によっても疑い得ない絶対確実な根拠に基づいて判定されねばならぬとする、確証主義を要請しているのである。 ハイエクは、社会をめぐる知識に対する、このような実証主義あるいは確証主義の要請を、科学主義(scientism)と呼ぶ。 ハイエクによれば、経済学を始めとして、あらゆる近代社会科学は、この科学主義によって色濃く染め上げられている。 しかし、社会についての実証(確証)的な知識は、果たして可能なのであろうか。 あるいは、社会を、科学(主義)的な認識の対象となり得る、客観的な事実として把握することは、そもそも適切なのであろうか。 すなわち、社会制御の不可欠な前提である社会予測は、原理的に可能な行為なのであろうか。 ◆2.実証主義と記述主義ここで、社会哲学においてしばしば混乱を引き起こす、認識論上の実証主義といわゆる法実証主義との関連について触れておきたい。 認識論上の実証主義とは、言うまでもなく、これまで述べてきた実証主義のことである。 これに対して、法実証主義(legal positivism)とは、最広義には、自然法(natural law)に対立する実定法(positive law)のみが法であるとする立場を意味する。 この最広義の意味における法実証主義は、自然法論の対抗思想という以上の意味を持たないので、むしろ、自然法論に対立させて、実定法論と呼ぶべきである。 この実定法論と呼ぶべき法実証主義は、自然法あるいは実定法の様々な解釈に依存して、極めて多義的であり得る。 その内には、ハートの擁護する法実証主義も、また、ハイエクの批判する法実証主義も含まれる。 次節以降に述べるように、ハートの擁護する法実証主義はより広義の、また、ハイエクの批判する法実証主義はより狭義のそれである。 このハイエクの批判するより狭義の法実証主義こそが、認識論上の実証主義と密接に関連しているのである。 詳しい議論は次節に譲るが、ハイエクの批判する法実証主義は、あらゆる法は人間が意図的に設定したものであるとする立場のことであり、さらには、それと関連したいわゆる価値相対主義のことである。 前者の立場は、言うまでもなく、構成的合理主義の法領域における現れであり、従って、認識論上の実証主義とは、意識的な理性の支配を貫徹させるという意味において、その精神の態度を共有している。 また、後者の価値相対主義は、事実と価値の峻別をさしあたり前提とすれば、認識論上の実証主義の、価値論における論理的な帰結となっている。 ハイエクの批判する法実証主義は、まさに法的な実証主義と呼ばれるに相応しいのである。 しかし、ハートの擁護する法実証主義は、必ずしも認識論上の実証主義と関連している訳ではない。 ハートの擁護する法実証主義は、むしろ実定法論と呼ばれるに相応しいのである。 ハートの擁護する法実証主義は、法が、人々の行為の当否を判定する法的な理由として有効でるか否か、あるいは、法が、現行の法体系の下で法としての効力を持つか否かという問題と、法が、道徳や慣習やさらには自然法やといった、実定法以外の当為規範から見て正しいものであるか否かという問題とを峻別する立場である。 すなわち、法が(その法体系の究極の承認のルールによる承認によって)法として妥当することと、それが道徳的に不正でないこととは、まったく別の問題だと言うのである。 この立場は、法の妥当性を、実定法体系の内部問題として捉えるという意味において、典型的な実定法論となっている。 しかし、ハートの言う実定法体系は、後に述べるように、実は慣習の一種である究極の承認のルールを含む、様々なルールの体系のことであって、制定法や判例法やあるいは慣習法やといった、普通にイメージされる実定法を、遥かに超えたものなのである。 このように拡張された実定法論は、認識論上の実証主義(あるいは確証主義)とは、関連がないと言うよりも、むしろ対立するものである。 何故ならば、後に詳しく議論するように、究極の承認のルールは、意識的な理性によっては語り得ぬ、ただ行為において示されるのみ(従って確証不能)のルールをも含んでいるからである。 ハートは、法の妥当性とその道徳的な価値を峻別するからといって、法の正邪についての道徳的な批判を認めない訳では些(いささ)かもない。 むしろ、そのような批判を明晰に行うためにこそ、法と道徳を峻別するのである。 言うまでもなく、自然法論は、法の妥当性をその道徳的な価値によって判断する。 すなわち、道徳的に不正な法は法ではないと言うのである。 従って、道徳的に不正な法には、それが法ではないから従わないということになる。 これに対して、ハートは、道徳的に不正な法も法である、しかし、それに従うか否かは(法的ではなく)道徳的な選択の問題である、と主張する。 ハートにとって、問われるべきは、不正な行為は為すべからずという一つの道徳的要請と、妥当な法には従うべしというもう一つの道徳的要請との間の選択である。 ハートによれば、自然法論は、このような道徳的選択の問題を、法の妥当性という問題にすり替えることによって、議論を混乱させていることになる。 自然法論の誤りは、以上に尽きるものではない。 自然法論は、法の妥当性を判断する根拠となる道徳的な価値規範を、自然法と呼ぶ。 この自然法は、自然法則と同様に、意識的な理性によって発見され得る客観的な存在であると見做されている。 しかし、客観的な存在事実から当為規範を発見し得るとする目論見は、事実命題「~である」から当為命題「~すべし」は演繹し得ないとするいわゆる方法二元論によって、容易に挫折させられる。 いわゆる自然主義的誤謬である(※注釈:naturalistic fallacy 非倫理的な[事実的]前提から倫理的結論を導くことができるとする誤謬。G. E. ムーアの仮説)。 ハートの批判する自然法論は、およそこのようなものである。 しかし、ハートは、法理論における重要な対立が、自然法論と実定法論との対立に限られると主張したい訳ではない。 むしろハートは、法理論における主要な対立を、実定法論の内部にあると見ている。 ハートは、広義の法実証主義の一部に、誤れる法理論が存在すると見ているのである。 このハートの批判する法理論は、次節以降に述べるように、ハイエクの批判する狭義の法実証主義と極めて近い。 ハートも、そしてまたハイエクも、自然法論ではなく、狭義の法実証主義でもない、第三の法理論を探求しているのである。 それはさておき、(認識論上の)実証主義は、極めて素朴なレベルでかなりの信頼を得ているようである。 たとえば、実証主義は、経験に学ぶ謙虚な態度であって、極めて当然のことだといった具合である。 実証主義が、経験に学ぶ謙虚な態度であるどころか、生きられる経験を閑却した理性の傲慢以外の何ものでもないことは、次章において詳しく展開するが、しかし、実証主義が、一見、当然のことに思えてくる事情については、少しく検討するに値しよう。 確かに、実証主義は、手段的合理主義の認識論における現れである。 認識もまた人間の行為の一つなのであるから、意識的な理性によって操作可能な行為のみが有効な行為であるとする手段的合理主義が、意識的な理性によって確証可能な認識のみが有効な認識であるとする実証主義を含意することは見やすい。 しかし、実証主義への素朴な信頼は、それが手段的合理主義の現れであることのみによる訳ではない。 そこには、認識に、わけても言語による認識に固有の事情が介在する。 我々は、言語を、何等かの事実を記述するものであると素朴に考えている。 あるいは、言葉の意味は、その言葉が指示する対象的な事実にあると考えている。 従って、ある言葉が意味を持つためには、その言葉が何等かの事実(ある事態が存在しないという事実も含む)と対応していなければならぬと考えていることになる。 さらに、ある言葉が真実であるか否かを判定するためには、その言葉と対応する事実が存在するか否かを確かめればよいと考えていることも多い。 このような言語に対する考え方を、オースティンは、記述主義と呼ぶ。 この記述主義こそが、実証主義への素朴な信頼を支える言語観なのである。 オースティンによれば、記述主義(descriptivism)とは、あらゆる言明は何等かの事実の記述であるかあるいは無意味であり、かつ、有意味な言明は真か偽のいずれかであるとする立場である。 言うまでもなく、この立場は、真偽の検証可能な言明のみが有意味であるとする、実証主義とほとんど同じ立場である。 あるいは、むしろ各種の実証主義に共通する言明観を抽象したものが記述主義であると言ってもよい。 オースティンは、次章で見るように、この記述主義の言語観を、まず、徹底的に解体するのである。 オースティンは、また、記述主義の批判と並行して、記述主義的な言語観が何処からよって来るのかについても検討している。 この記述主義の由来についての検討は、素朴な実証主義の蔓延を、よく説明するように思われる。 オースティンによれば、我々が「言葉を発する」あるいは「何かを言う」ということは、以下の三つの行為を同時に遂行することに外ならない。 一つは、ある一定の音声を発する行為(音声行為)であり、 二つは、ある一定の語彙に属し、ある一定の文法に適った、ある一定の音声すなわち語を発する行為(用語行為)であり、 三つは、ある程度明確な意味(sense)と指示対象(reference)とを伴って語あるいはその連鎖としての文を発する行為(意味行為)である。 オースティンは、この三つの行為を同時に遂行する「何かを言う」という行為を、発語行為(locutionary act)と呼ぶ。 しかし、ここでは、さしあたり意味行為のみが問題になるので、音声行為及び用語行為を捨象して、発語行為の意味を、意味内容のみを指示対象とするように限定して用いることにする。 すなわち、発語行為という語によって、意味行為という語を指示するのである。 このような発語行為という概念によって言及されているのは、我々が「何かを言う」行為は、取りも直さず、何かを指示する行為に外ならないという事態である。 すなわち、発語することは、何等かの事態を指示することなのである。 このような指示機能は、我々の言語に、紛れもなく存在している。 たとえば、ウィトゲンシュタインのように、言葉の意味は他の意味との関係の内でしか決定し得ず、言葉によって指示される事態は、言葉に先立って存在するのではなく、言葉の意味と同時に分節されると考えたとしても、言葉が、何等かの事態(言葉とは独立の客観的な事実である必要はいささかもない)を指示するということは認められる。 オースティンによれば、この紛れもなく存在する言葉の指示機能すなわち発語行為の位相のみにおいて、言語を巡るあらゆる問題を取り扱おうとする所に、記述主義が生じるのである。 すなわち、あらゆる発話は何等かの事態を指示するか、さもなくば無意味である、記述主義風に言い換えれば、あらゆる発話は何等かの事実を記述するか、さもなくば無意味である、ここまでは必ずしも誤りではない。 しかし、ここから、従って、発話を巡るあらゆる問題は、事態の指示あるいは事実の記述のみを巡る問題である、と結論する処に、記述主義が始まる 記述主義は、発話を巡るあらゆる問題を、発語行為の位相に還元し尽くそうとするのである。 しかし、オースティンによれば、発話という行為は、発語行為に還元し尽くされるものではない。 後に詳しく述べるように、発話行為は、「何かを言う」ことすなわち何等かの事態を指示することである発語行為の遂行であるのみならず、「何かを言う」ことが慣習的な文脈の下で何等かの社会的な効力を持つ(発語それ自体とは別の)行為でもある発語内行為(illocutionary act)の遂行でもあり、さらに、「何かを言う」ことを手段あるいは原因として何等かの目的あるいは結果を達成する行為でもある発語媒介行為(perlocutionary act)の遂行でもある。 発話行為は、以上の三つの行為を同時に遂行しているのである。 従って、オースティンによれば、発話行為を発語行為あるいは事実の記述に還元する試みは、発話行為が慣習的(発語内的)あるいは意図的(発語媒介的)な行為の遂行でもあるという事態を、全く等閑視することになる。 言い換えれば、あらゆる発話を事実の記述に還元する記述主義の成否は、発話を巡る諸問題が、発話に伴う、しかし発話それ自体とは区別される行為の遂行に、どこまで拘わっているかに依存することになる。 果たして、発話は、その社会的な文脈や話者の意図とは独立に、その意味あるいは指示機能のみによって、どこまで理解し得るのであろうか。 ◆3.民主主義と個体主義手段的合理主義は、与えられた目的を最大限に達成すべく社会を組織する。 すなわち、社会のあらゆる行為を、与えられた目的に対する手段としての有効性によって評価する。 しかし、達成されるべき目的そのものは、いかにして与えられるのであろうか。 そもそも、手段的合理主義とは、手段としてのある行為が帰結する社会状態についての知識と、様々な社会状態を評価する規準としての目的とを前提して、目的に照らして最も高く評価される社会状態をもたらす手段を選択するという立場である。 さらに、行為の社会的な帰結についての知識の拡大それ自体を目的とする立場も、(そのような知識はいかなる目的にとっても手段になり得るとすれば)、手段的合理主義に含まれる。 しかし、最終的に達成されるべき社会状態を決定する目的そのものは、手段的合理主義にとって、その外部から与えられざるを得ないのである。 何故なら、手段的合理主義によれば、手段とその帰結についての知識は、実証主義的な手続きによってその真偽を確証し得る客観的な知識である。 これに対し、目的による社会の評価は、価値判断あるいは当為判断「~すべし」なのであって、客観的な知識としての事実判断「~である」とは峻別される。 従って、万人によって受け容れられる確証可能な知識は、事実判断と演繹論理のみであるとする実証(確証)主義と、事実判断から当為判断は演繹し得ないとする方法二元論とを認めるとすれば、当為としての目的は、万人によって受け容れられ得る客観的(確証可能)な知識ではありえないことになる。 言うまでもなく、手段的合理主義は、実証主義(と方法二元論)をその認識論的(あるいは価値論的)な前提としているのであるから、達成すべき目的は、万人によって受容され得る客観的な知識ではあり得ない。 すなわち、手段的合理主義は、意識的な理性によって確証し得ない一切のものを拒絶するがゆえに、その達成すべき目的を、自らの内部からは原理的に導き出し得ないのである。 それでは、達成されるべき目的は、いかにして与えられるのであろうか。 手段的合理主義によれば、およそ行為の目的は、主観的あるいは個体に相対的なものである。 何故なら、手段的合理主義が前提している主客二元論に基けば、およそ客観的でないものは主観的であらざるを得ないからである。 このような立場は、ほとんどの場合、行為の目的を、個体の意志や情緒や欲求やに帰着させる。 言い換えれば、このような立場は、行為を、個体の意志や情緒や欲求やの表出であると捉えるのである。 個体の意志や欲求やは、言うまでもなく個体に相対的、主観的なものであって、もとより普遍的、絶対的、客観的なものではあり得ない。 このような個体の意志から、少なくとも複数の個体によって構成される社会の全体が達成すべき目的が、果たして導出し得るであろうか。 この問題は、近代合理主義に特有の問題である。 あるいは、近代合理主義と主客二元論という卵を同じくする一卵性双生児である、近代個体主義に特有の問題であると言ってもよい。 すなわち、目的や価値や当為やは、客観的、普遍的、絶対的なものでは全くあり得ず、主観的、個体的、相対的なものに外ならない(価値相対主義)。 さらに、目的志向的な行為や価値判断や当為言明やは、個体の意志や情緒や欲求やの表出として捉えられる(表出主義)。 従って、社会全体の目的や価値や当為やは、個体の意志や情緒や欲求やに還元し得るし、また、されねばならぬ(個体主義)。 以上の条件を総て充たすような社会全体の目的を導出せよ。 これが問題である。 この問いに対する、近代特有の答えが、近代民主主義なのである。 民主主義とは、言うまでもなく、多数者すなわち大衆の支配のことである。 民主主義にあっては、個体の意志の集計において多数を占めた者が、究極的には無制限の権力を掌握する。 最高、無制限の権力を主権(sovereignty)と呼ぶことにすれば、民主主義とは、個体の意志の集計にこそ主権が存すると見る立場に外ならない。 従って、民主主義においては、社会全体の達成すべき目的は、もしそれがあるとするならば、個体の意志の集計に還元されねばならないのである。 何故なら、社会のあらゆる行為をその達成への貢献によって評価し得る目的とは、その社会における主権者(sovereign)の意志であると言ってもほとんど言い過ぎではないからである。 言い換えれば、民主主義とは、個体の意志の集計によって、社会全体の目的を選択する、社会的選択の装置なのである。 ハイエクが批判するのは、多数者の意志に主権を付与する、このような無制限の民主主義である。 元来、近代の立憲主義は、権力の制限を目的としていた筈である。 なるほど、近代憲法は、人権の保障と権力の分立とを規定することによって、権力の制限を目指してはいる。 しかし、近代立憲主義は、憲法をも含めたあらゆる法を制定し得る究極的な権力としての(いわゆる憲法制定権力をも含めた)主権の制限という問題に対して、確定した解答をほとんど持ち合わせていない。 そもそも、最高、無制限の権力としての主権の制限を云々すること自体が自己矛盾なのである。 ハイエクによれば、このような自己矛盾が生じて来るのは、あらゆる法は人間によって意図的に制定し得るし、また、すべきであると考えることによる。 すなわち、あらゆる法に立法者が存在すると考えるならば、その立法者自身が従う法にも立法者が存在する筈である。 従って、ある立法者が従う法の立法者をその立法者より上位の立法者と呼ぶことにすれば、より上位の立法者の存在しない立法者、言い換えれば、究極(最上位)の立法者は、いかなる法にも従わないことになる。 何故なら、究極の立法者の従う法が存在するならば、その法の立法者も存在することになり、より上位の立法者の不在という究極の立法者の定義に矛盾するからである。 言い換えれば、あらゆる法が人間によって意図的に制定されると考えるならば、究極的な法制定主体の(立法)権力を法によって制限することは、論理的に不可能となるのである。 従って、究極的な立法者は、無制限であらざるを得ない。 すなわち、最高(究極)かつ無制限の(立法)権力としての主権の存在は、あらゆる法は人間によって意図的に制定されるとする立場の、必然的な帰結なのである。 従って、たとえ憲法といえども、いずれかの主体によって意図的に制定されたとする限り、(究極的な立法者としての)主権者を制限することなど不可能なのである。 近代立憲主義は、あらゆる法に制定主体が存在すると考える限り、主権者の権力の制限に、原理的に失敗するのである。 このような主権者すなわち究極的かつ無制限な立法者の存在を必然的に帰結する、あらゆる法は人間によって意図的に設定されるとする立場は、言うまでもなく、構成的合理主義のコロラリー(※注釈:corollary 必然的に推論される帰結)となっている。 すなわち、法もまた、社会一般と同じように、理性によって意図的に制御されるべきだ、あるいは、社会全体の目的を達成する手段として有効に設定されるべきだ、という訳である。 さらに、究極的に法を設定するのは主権者なのであるから、このような法の捉え方は、法とは主権者の目的あるいは意志の表出に外ならないと主張していることになる。 言い換えれば、このような立場は、法とは主権者の命令であると主張しているのである。 確かに、命令は当為言明の一種であると言い得るので、当為言明としての法を命令として捉えることは一見尤(もっと)もらしい。 しかし、法を命令わけても主権者の命令と見ることに、何の不都合も生じ得ないのであろうか。 次節で詳しく述べるように、ハートもまた、この問いとほとんど同じ問いを問うのである。 ところで、民主主義においては、主権者とは、言うまでもなく、多数者大衆である。 すなわち、民主主義における主権は、大衆の意志の集計に存するのである。 従って、国民主権を標榜する民主主義においては、国民大衆の(究極的な)権力は原理的に無制限である。 言い換えれば、民主主義とは、大衆が無制限の権力を掌握した社会なのである。 究極かつ無制限の権力としての主権概念そのものは、確かに、構成的合理主義の論理的帰結である。 しかし、大衆の意志に主権を付与する民主主義的な主権概念は、必ずしも合理主義のみから帰結する訳ではない。 民主主義の前提には、近代合理主義の精神的な双生児である近代個体主義が準備されている筈である。 ハイエクによれば、無制限な民主主義の前提には、価値相対主義が準備されていることになる。 ハイエクは、あらゆる法は人間によって意図的に設定されるとする考え方を、法実証主義と呼ぶ。 すなわち、ハイエクは、構成的合理主義の法への適用を、法実証主義と呼ぶのである。 このような法実証主義によって、ハイエクは、ベンサムやオースティン(本書で取り上げるJ・L・オースティンではなく、19世紀のイギリスの法理学者で、ベンサムの友人のJ・オースティン)、あるいはケルゼンの法実証主義を指示している。 このハイエクの言う法実証主義、わけてもケルゼンの法実証主義こそが、価値相対主義を明らかに含意しているのである。 このような法実証主義が前提している、認識論上の実証主義、あるいはより広く確証主義の立場に立てば、法命題を含むあらゆる当為命題は、万人によって一致して受け容れられ得る、確実に証明された命題ではあり得ない。 当為言明は、意識的な理性によっては、その正当性を確証し得ないのである。 このように客観的、普遍妥当的ではあり得ない当為言明は、つまるところ、個体の意志や情緒や欲求やの表出なのであって、主観的、相対的であらざるを得ない。 従って、法あるいは当為をめぐる問題は、客観的、普遍的な理性の問題であると言うよりも、むしろ主観的、個体的な意志の問題であると言うことになる。 しかし、法といい当為といい、ある社会を構成する総ての個体の行為を拘束する規範の問題である。 個体的な意志の問題として法や当為やを取り扱う視点から、いかにして社会的な規範の問題としての法や当為やを捉えるか。 ここに、価値相対主義を民主主義に結び付ける契機が存在するのである。 民主主義とは、社会を構成する諸個体の意志を集計することによって、社会全体の意志を形成する社会的装置である。 従って、法や当為の言明を、民主主義的に形成された社会全体の意志の表出であると考えるならば、価値相対主義は、社会規範としての法や当為の問題をも一貫して取り扱えることになる。 すなわち、社会規範としての法や当為を、その時点における多数者の意志に相対的なものとして捉えるのである。 言い換えれば、価値相対主義は、民主主義と結び付くことによって、あらゆる法や社会的当為は、(究極的には)多数者大衆の意志に還元されると主張するのである。 もっとも、価値相対主義は、必ずしも常に民主主義と結び付く訳ではない。 価値相対主義とは、価値あるいは当為の問題は、客観的、普遍的な認識あるいは理性の問題ではなく、主観的、個体的な実践あるいは意志の問題であるという主張以上のものではない。 従って、価値相対主義は、個体的な意志から、いかにして社会的な規範あるいは社会全体の意志が形成されるかという問題に対して、その幾通りもの解答と両立し得るのである。 しかし、価値相対主義は、万人が一致して受け容れ得る理性的な論証のみによっては、社会規範あるいは社会全体の意志が形成されることは、決して有り得ないと考えるのであるから、理性的な論証以外の方法によって社会全体の意志を形成する解答としか両立し得ないことは言うまでもない。 そもそも、個体の意志や情緒や欲求やは、さらには、個体の価値や利益や目的やは、一致するどころか、一般的には共存さえしていない。 従って、このように対立する価値や利益や目的やが犠牲にされざるを得ないことになる。 理性的な論証によるこの問題(社会全体の意志を形成する問題)の解決は不可能だというのであるから、そこでは、何等かの実力による解決が要請されることになろう。 まさに、民主主義とは、この問題を、人間の頭数の多寡という実力によって解決しようとする試みなのである。 もちろん、票数以外にも様々な実力があり得る。 その究極的な形態は、いうまでもなく、赤裸々な暴力に外ならない。 いずれにせよ、価値相対主義は、社会全体の意志を形成するという問題に対して、何等かの実力による決着という解答を帰結せざるを得ないのである。 言うまでもなく、民主主義は、そのような解答の有力な一つとして位置付けられる。 すなわち、民主主義とは、多数者大衆の実力によって、社会全体の意志や利益や目的を決定Sる、パワー・ポリティックスに外ならないのである。 このような、何等かの実力による社会的意志決定を帰結する、価値相対主義と、究極かつ無制限の主権を帰結する、あらゆる法は意図的に設定されるとする考え方が、互いに結び付けられることによって始めて、多数者大衆は無制限の権力を掌握するのである。 何故なら、価値相対主義の下では、究極の社会的意志決定者である主権者とは、自らの実力によって社会全体の意志を決定し得る者に外ならないからである。 まさに、カール・シュミットの言うように、主権者とは、(実力行使をも辞さない)非常事態において、全体的な決断を下し得る者なのである。 それが、多数者大衆自身であるか、あるいは大衆の歓呼によって迎えられたその指導者であるかは、問題ではない。 構成的合理主義の法への適用と、その一卵性双生児である価値相対主義との結合が、大衆に無制限の権力を委ねるという事態を帰結することに、いささかの変りも無いからである。 ハイエクは、構成的合理主義の法への適用とともに価値相対主義をも含意する言葉として、法実証主義を用いることがある。 このように用いられた法実証主義が、大衆を主権者の高みに昇らせる、充分な前提となっていることは言うまでもない。 ハイエクが、根底的に批判するのは、まさに、このような意味における法実証主義なのである。 しかし、ハイエクは、このような法実証主義を批判するからといって、必ずしも自然法論に与する訳ではない。 ハイエクは、ハートによる自然法論の批判に、ほとんど全く同意している。 この意味においては、ハイエクもまた、ハートの言う実定法論者なのである。 ハイエクは、さらに、法実証主義と自然法論という二分法それ自体が、そもそも誤りなのであると主張する。 ハイエクは、(次節に述べるように、ハートもまた)法実証主義でも自然法論でもない、第三の法理論を指向しているのである。 ◆4.主権主義と表出主義人間によって意図される対象としての客観的なものと、意図する人間主体の在りかとしての主観的なものとを峻別する、いわゆる方法二元論は、近代合理主義と同時に、近代個体主義をも産み落とした。 すなわち、主客二元論は、近代合理主義、わけても、あらゆる知識はそれに対応する客観的なものに根拠付けられねばならぬとする客観主義と、近代個体主義、わけても、あらゆる行為はそれを意図する主観的なものに帰属されねばならぬとする主観主義という、一卵性双生児の母なのである。 認識論上の実証主義がこのような客観主義の、また、ハイエクの言う法実証主義がこのような主観主義のコロラリー(※注釈:必然的帰結)であることは言うまでもない。 ハートの批判する法の主権理論もまた、このような主観主義のコロラリーなのである。 ハートの批判する法理論は、法とは、主権者によって発せられた威嚇を背景とする命令であるとする立場である。 縮めて言えば、法とは、主権者の強制命令であるとする立場、あるいは、法の主権者命令説である。 ここで言う主権者が、最高かつ無制限の立法権力を有する者であることは言うまでもない。 このハートの批判する法の主権者命令説は、あらゆる法体系には、それを設定する最高、無制限の主権者が存在すると考える主権理論と、あらゆる法は、その逸脱に対する制裁の威嚇によって強制された命令であると考える命令理論との、大きく二つの部分に分けられる。 この法の主権理論こそが、近代個体主義あるいは主観主義の論理的帰結なのである。 あらゆる法は、主体によって意図的に設定されるとする立場から、最高かつ無制限の主権の存在が論理的に帰結することは、既に前節において見た通りである。 この、あらゆる法は、主体によって意図的に設定されるとする立場は、あらゆる行為は、それを意図する主体あるいは主観の存在を含意しているとする主観主義(主体主義)の、法における現れであると見ることが出来る。 何故なら、法もまた、人間の(必ずしも意図的とは限らない)行為の帰結であることに変わりは無いからである。 従って、最高かつ無制限の主権の存在は、このような主観主義の論理的な帰結であるとも考え得るのである。 すなわち、ハイエクの批判する法実証主義も、ハートの批判する法の主権理論も、このような主観主義の論理的な帰結となっているのである。 ハートは、法の主権理論に対して、様々な角度から疑問を提出する。 法とは、最高かつ無制限の立法権力を有する主権者によって、意図的に設定されたものであるとしよう。 このとき、主権者を主権者たらしめる根拠は、もはや法ではあり得ない。 何故なら、主権者が法によって主権者たり得るとするならば、その法を設定した主権者が存在することになり、主権の最高性と矛盾するからである。 あるいは、そもそも法を根拠とする主権は、主権の法的無制限性に矛盾すると言ってもよい。 いずれにせよ、主権者は、法以外の根拠によって主権者たり得るのである。 従って、憲法などの法によって立法権力を付与される立法府のような主体が、主権者たり得ることはあり得ない。 それでは、主権者とは一体誰であるのか。 それは、立法府を選挙する国民であるのか。 あるいは、何が法であるかを最終的に判定し得る司法府であるのか。 あるいは、大衆の歓呼によって推戴された大統領であるのか。 しかし、司法府はもとより、選挙民もまた、憲法によって授権された機関なのであって、主権者たり得よう筈もない。 なるほど、(憲法上の機関としての選挙民とは区別される)国民大衆あるいはその指導者は、主権者たり得るかも知れないが、このとき、大衆に主権を付与する根拠は一体何なのか。 言うまでもなく、主権理論は、ここで、自然法論(あるいは自然権論)を持ち出す訳にはいかない。 主権理論によれば、自然法もまた法である限り、いずれかの主権者によって設定された筈のものだからである。 それでは、大衆を主権者に推戴し得るのは、一体いかなる根拠によるのか。 主権理論の内部においては、そのような根拠は遂に示し得ない。 主権理論は、この、誰が主権者たり得るのかという問題を、常に開かれた疑問として留め置かざるを得ないのである。 主権者は、いかなる法によっても制限され得ないのであるから、当然、自己自身の設定した法によっても制限され得ない。 主権者は、自己自身を法的には制限し得ないのである。 従って、たとえば、主権者が、過去において制定した立法手続を、未来において遵守しなかったとしても、それは法的な責務に対する違反とはなり得ないし、また、主権者が、過去において締結した条約を、未来において履行しなかったとしても、それも法的な責務に対する違反とはなり得ない。 主権者が、過去において設定した法を、未来において無視したとしても、それは主権者の意志が変更された、つまりは気が変わったということに過ぎない。 主権者の意志の変更が、立法の名宛人や条約の相手方との約束に、たとえ違背することになったとしても、それは決して法的な責務に対する違反とはなり得ないのである。 すなわち、主権理論によれば、主権者の行為に対して、法を根拠として責務を問う可能性は、決して存在し得ないのである。 主権理論をめぐるこれらの問題、すなわち、主権者を主権者たらしめる法的な根拠は存在し得ないという問題、あるいは、主権者は自己自身を法的には制限し得ないという問題は、主権者という存在が、法体系の内部においては、遂に根拠を持ち得ないということを指し示している。 むしろ、主権者とは、法体系の外部から、法体系それ自体を根拠づけるものとして与えられて来たのである。 従って、主権者が、法体系の内部にその根拠を持ち得ないのはむしろ当然である。 主権者とは、法体系の外部にあって、法体系そのものを根拠づける、たとえば政治的な存在なのである。 しかし、法体系の根拠を問うに際して、このような主権者の存在は、果たして必然なのであろうか。 言い換えれば、法の根拠には、それを意図的に設定する主体が、不可避的に要請されるのであろうか。 言うまでもなく、このような主体の要請は、あらゆる行為には、これを意図する主観が不可避的に要請されるとする主観主義の必然的な帰結である。 ハートは、法の根拠を問うに際して、このような主観主義の要請が、全く不要であることを明らかにする。 法の主権理論は、法現象の最も中核的な部分を把握することに失敗すると言うのである。 しかし、ハートの法理論は積極的な展開は、以下の諸章の課題である。 ハートは、また、法とは威嚇を背景とした命令である、すなわち、法とは強制的命令であるとする法の命令理論を徹底的に批判している。 ハートによれば、法は、 第一に、その制定者自身にも適用されるという点において、 第二に、責務のみではなく権能をも付与するという点において、 第三に、慣習法のように意図的な立法にはよらないものが存在するという点において、 強制的命令と同一視する訳にはいかない。 さらに、ハートは、これらの問題点を踏まえて修正された命令理論をも一蹴する。 すなわち、第三の問題点を修正した、黙示の命令という考え方、第二の問題点を修正した、あらゆる法は公機関に向けられた命令であるとする立場、第一の問題点を修正した、公的資格において命令する立法者と私的資格において命令されるそれとを区別する試みの、一切を否定し去るのである。 しかし、ハートの命令理論批判それ自体は、本書の主題と必ずしも密接に関連する訳ではないので、主権理論批判に必要な限りにおいて触れることに留めたい。 ハートの批判する法の主権理論、あるいはハイエクの批判する法実証主義を帰結する主観主義は、あらゆる知識はそれに対応する客観的なものによって根拠付けられねばならぬとする客観主義の、一卵性の兄弟/姉妹であった。 オースティンの批判する言語の記述主義が、この意味における客観主義のコロラリーであることは言うまでもない。 オースティンもまた、ハイエクやハートと同じように、客観主義と切り結んだ刀で、主観主義とも渡り合っている。 この客観主義と主観主義という、近代のロムルスとレムスとの闘いにおいては、二正面作戦以外の如何なる戦力もあり得ないのである。 オースティンの批判する記述主義は、言葉とは何等かの事実を記述するものであり、その真偽はそれが記述する事実の存否によって検証し得るとする考え方であった。 オースティンによれば、このような記述主義の淵源には、何等かの事態を指示する(言及する、記述する)という言葉の機能、すなわち言葉の指示機能のみに、言葉の持つあらゆる機能を還元しようとする態度が存在していた。 あるいは、オースティンの用語系に即して言い換えれば、記述主義とは、発話という行為を、指示行為(意味行為)という意味における発語行為に還元し尽くそうとする態度なのであった。 このような記述主義が、言葉についての客観主義であることは明らかであろう。 すなわち、言葉は、客観的な事実を記述することによって始めて意味を持つという訳である。 これに対して、オースティンの批判する、言葉についての主観主義とは、言葉とは(発話主体の)主観的な意図や情緒や欲求やの表出であると考える、言語の表出主義(expressivism)に外ならない。 言うまでもなく、言語には、発話主体に係わる何等かの事情(必ずしも主観的な心理とは限らない)を表現するという機能が、紛れもなく存在している。 従って、ある発話を了解するに当たって、その発話に表現されている発話主体の主観的な意図を無視してよい訳では些かもない。 しかし、あらゆる発話を、発話主体の主観的な意図に還元して理解するとなると、問題はまた別である。 表出主義とは、あらゆる発話を、発話主体の主観的な意図の表出に還元し尽くそうとする、言い換えれば、言葉の持つあらゆる機能を、その表現機能に還元し尽くそうとする態度に外ならないのである。 このような表出主義が、発話という行為には、それを意図する主観が必ず存在せねばならないと考える点において、言葉についての主観主義であることは明らかであろう。 オースティンは、記述主義とともに、このような表出主義をも根底的に批判するのである。 オースティンの用語系に即して言い換えれば、表出行為とは、発話という行為を、発話を手段として何ごとかを達成する行為である、発語媒介行為に還元し尽くそうとする態度に外ならない。 もっとも、オースティンの言う発語媒介行為は、必ずしも発話主体によって意図された行為のみに限られる訳ではない。 オースティンの言う発語媒介行為は、それが意図されたものであるか否かにかかわらず、発語の帰結として何等かの効果を達成する行為なのである。 もちろん、オースティンにおいても、何等かの帰結あるいは目的を達成すべく意図された発語媒介行為が重要であることは言うまでもない。 しかし、オースティンは、意図されざる帰結をもたらす発語媒介行為をも、その射程に捉えているのである。 それでは、発語によって何等かの帰結を達成する(発語それ自身とは区別された)行為は、総て、発語媒介行為となるのであろうか。 発語が何等かの社会的な効力を持つ(発語それ自身とは区別された)行為である発語内行為と、発語媒介行為は一体どこが違うのであろうか。 オースティンによれば、発語によって何等かの効果を達成する発語媒介行為と、発語が何等かの効力を獲得する発語内行為とは、発語のもたらす効果が、慣習的(conventional)なものであるか否かによって区別されるのである。 すなわち、発語媒介行為において達成される効果は、発語に後続することが、必ずしも慣習的には期待され得ないのに対して、発語内行為において獲得される効力は、発語に随伴することが、慣習的な規則によって支持されているのである。 言い換えれば、発語媒介行為の効果は、慣習以外の何ものか(たとえば威嚇や強制や)によって達成されるのに対して、発語内行為の効力は、それを有効適切なものとする慣習の存在を俟ってはじめて獲得されるのである。 オースティンの言う慣習(convention)は、もちろん、本書の問う慣習と密接に関連するものであるが、後に述べるように、むしろ、ハートの言うルールに極めて近い概念である。 従って、オースティンの言う発語媒介行為とは、発語によって何等かの帰結を達成する行為の内で、いかなる慣習にも依存せず、またルールにも従わない類いのものを指し示していることになる。 このような発語媒介行為は、確かに、発話行為によって意図された行為である場合が最も重要なのではあるが、しかし、意図されない行為をも明らかに含むものである。 従って、あらゆる発話を発語媒介行為に還元しようとする態度と、あらゆる発話を(発話主体の)主観的な意図の表出に帰着しようとする表出主義とは、必ずしも正確に一致する訳ではない。 発語媒介行為一元論は、表出主義をも包含する、より広い概念なのである。 このような発語媒介行為一元論を批判することによって、オースティンは、表出主義をもその批判の射程に収めていると言うことも出来よう。 しかし、慣習あるいはルールに依存も服従もしない行為(発語媒介行為)の内で、その主観的な意図のみによって了解し得る行為(表出行為)を除いたものが、差し当たり緊要であるとも思われないので、以下の行論においては、誤解の怖れの生じない限り、発語媒介行為一元論と表出主義とを互換的に用いることにしたい。(このことについては、後に再び述べる機会があると思われる。) すなわち、発語媒介行為一元論の批判は、取りも直さず表出主義の批判に外ならないのである。 以上に見てきたように、産業主義と民主主義、あるいは、合理主義と個体主義は、我々の近代社会において、極めて当然のこととして受け容れられている。 しかし、以上に見てきたことが示しているのは、我々が当然のこととして受け容れている合理主義と個体主義には、ある特徴的な前提が共有されているということである。 その前提とは、およそ人間とその社会は、目的志向的(intentional)な理性の客体であるか或いは主体であるとするものの見方である。 このようなものの見方に立って、人間とその社会を、目的志向的な理性の客体と捉える処に、手段的合理主義や実証主義あるいは確証主義、さらには記述主義といった、一連の客体主義あるいは客観主義(objectivism)が生じるのであり、また、人間とその社会を、目的志向的な理性の客体と捉える処に、個体主義や主権主義あるいは価値相対主義、さらには表出主義といった、一連の主体主義あるいは主観主義(subjectivism)が生じるのである。 このようなものの見方それ自体を、(近代)合理主義と呼ぶことも、かなり一般的ではあるが、合理主義は広狭様々な意味に用いられるので、ここでは、このようなものの見方を、志向主義(intentionalism)と呼ぶことにしたい。 いかにも熟さない命名であるが、本書の立場である慣習主義(conventionalism)との対比を意識してのことである。 従って、産業主義と民主主義の近代は、志向主義をその哲学的な前提としていることになる。 産業主義と民主主義は、志向主義という双面神の二つの顔である客観主義と主観主義の、もう一つの《ペルソナ》なのである。 |
| + | ... |
◆1.暗黙的秩序 - ハイエク -人間とその社会を、理性によって意図的に制御し得る対象であると考える、構成的合理主義や、また、人間とその社会についての知識を、客観的な事実によって確証し得る言明であると考える、実証主義やは、我々の社会のほとんど自明な前提となっている。
しかし、果たして社会は、意図的に制御し得る対象であり得るのか。 あるいは、社会についての知識は、客観的に確証し得る言明であり得るのか。 ハイエクの問いは、ここから始まる。 ハイエクによれば、社会は、目的を達成すべく意図的に構成された秩序、すなわち彼の言う組織には留まり得ない。 社会には、意識的な目的を持たず、また、意図的に設計された訳でもない秩序が、必ず存在しているのである。 言い換えれば、社会には、差し当たり何に役立つのか(当の本人達にも)分からない、自然発生的(spontaneous)に生成された秩序が、常に存在しているのである。 ハイエクは、このような秩序を、自生的秩序(spontaneous order)あるいはコスモス(cosmos)と呼ぶ。 ハイエクによれば、自生的秩序は、通常の個体の行為はもとより、組織それ自体の行為をも含んだ秩序として、社会全域を覆っている。 すなわち、構成的合理主義の、社会全域を一個の組織によって覆い尽くし得るとする考え方に対して、ハイエクは、社会とは、一個の組織によってはついに覆い尽くせない、(組織をその要素として含み得る)自生的秩序に外ならないと主張するのである。 自生的秩序は、自然発生的に生成された秩序である。 しかし、言うまでもなく、自生的秩序は、人間の行為から独立した、自然と同様の、客観的な事実ではあり得ない。 すなわち、自生的秩序とは、行為の持続的な遂行が、(意図せざる)結果として秩序を生成しているという事態に外ならないのである。 しかし、自生的秩序が、行為の遂行的な結果に外ならないからと言って、必ずしも、それが、行為の主観的な意図に還元され得る訳ではない。 自生的秩序は、それを結果する行為の主観的な意図を超越し、それに先行するのみならず、行為を規範的に拘束しさえするのである。 しかし、自生的秩序のこの側面については、次章で詳しく検討したい。 この章では、自生的秩序の、行為の持続的な遂行の(意図せざる)結果として生成されるという特徴から導かれる、もう一つの側面のみに、議論を限定したい。 自生的秩序のこの側面こそ、構成的合理主義さらには実証主義との闘いに際して、最も有力な橋頭堡となり得るからである。 行為の持続的な遂行の(意図せざる)結果として生成される秩序を、手短に、遂行的(performative)な秩序と呼ぶことにしょう。 すなわち、自生的秩序は、遂行的な秩序として特徴付けられるのである。 遂行的な秩序としての自生的秩序には、たとえば、市場、貨幣、法、権威、社交、言語、技能、偏見、儀礼、流行、慣習、伝統などといった社会秩序が含まれる。 これらの社会秩序は、それぞれの領域における人々の行為の持続的な遂行が、結果的に、それらの行為の従うべき何等かのルールを生成し、従ってルールに従う行為の集合としての秩序を生成するという意味において、明らかに遂行的な秩序となっている。 さらに、これらの社会秩序は、それぞれの領域において秩序を形成するルールに、人々が従うべき理由あるいは根拠が、人々がそれらのルールに従うという行為を持続的に遂行していること以外には、(究極的には)存在し得ないという意味においても、紛れもなく遂行的である。 言い換えれば、こられの社会秩序は、(それらの秩序を形成する)ルールに従う行為の持続的な遂行によって、ルール(あるいはそれが形成する秩序)それ自体が繰り返し生成されているという事態のみを、ルール(あるいはそれが形成する秩序)の存立する究極的な根拠としているという意味において、まさに遂行的な秩序と呼ぶべきなのである。 すなわち、自生的秩序とは、行為の持続的な遂行の結果として生成されるのみならず、行為の持続的な遂行をその究極の根拠として存立する社会秩序なのである。 このような遂行的秩序としての自生的秩序が、いわゆる自然と同じ意味における客観的実在性、あるいは、理性によっては疑い得ない絶対的確実性を持ち得ないことは言うまでもない。 自生的秩序は、そのような秩序を生成する行為が繰り返し遂行されているという事態以外の何ものであもないのであって、遂行されている行為が変化すればそれに伴って変化する、行為の遂行に相対的なものである。 すなわち、自生的秩序は、歴史的あるいは地域的な行為の遂行に相対的な秩序なのである。 (このことから、必ずしも価値相対主義が帰結される訳ではないことは、次章に詳しく述べるが、さらに、このことから、いわゆる文化相対主義が帰結される訳ではないことも、次章以降に述べる機会があると思われる。) 従って、このような自生的秩序に、自然法則と同じ意味における、客観的、普遍的な法則を見い出そうとする試みの、挫折せざるを得ないことは、もはや旧聞に属そう。 ところで、遂行的秩序においては、行為の遂行によって生成される秩序が、いかなるものであるかについて、行為者自身が意識している必要は些かもない。 自生的秩序は、行為遂行の意図せざる結果として生成されるのであって、行為主体は、そのような結果について意識し得る筈もないのである。 さらに、自生的秩序においては、行為の遂行において事実上従われているルールが、いかなるものであるかについても、行為者自身が意識している必要は些かもない。 自生的秩序を形成するルールは、その遂行において実践的、経験的に従われているのであって、行為主体が意識的、合理的に従っている訳ではないのである。 言い換えれば、自生的秩序のルールは、言葉(あるいは意識的な理性)によっては語り得ぬ、行為において示し得るのみの、暗黙的(tacit)な事態なのである。 たとえば、典型的な自生的秩序である言語について見るならば、我々は、言語のルールについてほとんど意識せず、またその総てを語り得ないとしても、正しいルールに従った発話を遂行し得るのであり、ましてや、我々の遂行する個々の発話が、言語総体にいかなる結果をもたらすかなどということは、通常全く意識しておらず、またし得るものでもない。 このことは、その他の典型的な自生的秩序である技能や慣習においても、全く同様である。 技能とは、言葉によっては遂に説明し得ず、実践的(遂行的)にのみ従い得る、従って、実践的(遂行的)にのみ学び得るルールに外ならないし、慣習とは、まさに暗黙的、遂行的な事態そのものであって、それを繰り返し生成する行為が、そもそも如何なる意図の下に為されたものであったかが忘却されることによって、益々その安定を強めるといった代物である。 すなわち、行為の遂行によって繰り返し生成される、遂行的な秩序とは、取りも直さず、言葉(あるいは意識的な理性)によってはその全体をついに把握し得ない、暗黙的な秩序に外ならないのである。 従って、我々は、言語によっては分節し得ないが、行為においては遂行し得るルールを知っていることになる。 この意味において、我々は、語り得る以上のことを知っているのである。 この語り得ぬ、ただ示されるのみの、暗黙的あるいは遂行的な知識は、意識的あるいは理性的な認識のみによっては獲得し得ない。 何故なら、意識的、理性的な認識といえども、人間の行為には違いないのであるから、何等かの自生的秩序(あるいはそのルール)を繰り返し生成している筈である。 このことは、意識的、理性的な認識も、他の行為と同様に、自生的秩序のルールに遂行的に従っていることを意味する。 すなわち、意識的、理性的な認識もまた、自生的秩序(あるいはそのルール)に規範的に拘束されているのである。(この点については、次章で改めて述べる。) 従って、ある特定の自生的秩序とそのルールが、意識的、理性的な認識によってたとえ分節され得たとしても、当の意識的、理性的な認識それ自身の従うルールは、分節され得ないままにただ遂行されるものとして残ることになる。 すなわち、自生的秩序とそのルールを、意識的、理性的に認識し尽くそうとする試みは、いかなる認識といえども、自分自身が遂行的に従っているルールを(自分自身によっては)ついに分節し得ないという事情によって、挫折せざるを得ないのである。 言い換えれば、ある特定の自生的秩序とそのルールならいざ知らず、総ての自生的秩序とそのルールを、意識的な理性によって分節し尽くすことは原理的に不可能なのである。 このような訳で、自生的秩序とそのルールは、(究極的には)語り得ぬ、ただ示されるのみの事態であらざるを得ない。 遂行的な秩序は、暗黙的な秩序であらざるを得ないのである。 ハイエクは、このような自生的秩序として、社会を捉える。 自生的秩序としての社会が、構成的合理主義やあるいは実証主義やの対象となり得ないことは、容易に理解し得よう。 自生的秩序としての社会は、理性によって意図的に制御し得る対象ともなり得ないし、また、それについての言明を客観的に確証し得る対象ともなり得ないのである。 何故なら、自生的秩序とは、語り得ぬ、暗黙的な秩序なのであって、それ(その全体)を意図的に制御するための情報を、制御主体が獲得することは、原理的に不可能だからであり、ましてや、それ(その全体)についての言明を、客観的に確証することなど、ほとんど形容矛盾だからである。 あるいは、意図的、合理的な制御もまた、人間の行為には違いないのであって、何等かのルールに遂行的に従っている筈なのであるから、意識的、理性的な認識の場合と全く同様に、自生的秩序(あるいはそのルール)の全体を、意図的、合理的に制御し尽くすことは、原理的に不可能なのである。 自生的秩序としての社会は、遂行的あるいは暗黙的な秩序であるがゆえに、構成的合理主義やあるいは実証主義やといった客観主義の対象には、決してなり得ないのである。 このようなハイエクの自生的秩序論が、ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論に極めて接近していることは、注目に値する。 ウィトゲンシュタインの言う言語ゲームは、ここで言う遂行的あるいは暗黙的な事態と、ほとんど過不足なく重なり合っている。 すなわち、言語ゲームは、そのようなゲームが遂行されているという事態以外のいかなる根拠も持ち得ず、また、その全体を対象にして言及する可能性を原理的に拒否しているのである。 さらに、言語ゲームは、人間のあらゆる行為は、何等かの言語ゲームの遂行とならざるを得ないという特徴を、自生的秩序と分け持っている。 すなわち、自生的秩序もまた、人間のあらゆる行為は、何等かの(自生的秩序を形成する)ルールの遂行とならざるを得ないという特徴を持っているのである。 自生的秩序のこの特徴は、その規範的(normative)な側面と呼ばれる。(この側面の検討は次章の課題である。) この意味において、言語ゲームは、また、規範的な事態とも重なり合っているのである。 このように、ハイエクの自生的秩序論と、ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論は、家族的類似と言い得る程度にも親しい関係にある。 ハイエクとウィトゲンシュタインは、その思想圏における最も中心的な領域を、ほとんど同じくしているのである。 しかし、ハイエクとウィトゲンシュタインの思想圏は、必ずしも完全に重なり合っている訳ではない。 彼らの思想圏は、その周辺的な領域において、かなりのずれを見せている。 わけても、このずれは、ハイエクの、進化への傾斜において著しい。 ハイエクによれば、自生的秩序としての社会を形成するルールは、変化する環境への適応や、他のルールの形成する(自生的秩序としての)社会との競合やを通じて、淘汰され選択される。 すなわち、ルールは、それが形成する(自生的秩序としての)社会に、勝利と繁栄をもたらすか否かによって、淘汰され選択されるのである。 ハイエクは、このような淘汰と選択を経て、ルールとそれが形成する(自生的秩序としての)社会が、進化し発展すると主張する。 ルールを遺伝子に置き換え、(自生的秩序としての)社会をそれによって形成される生命体に置き換えれば、この主張は、生命進化論とほとんど異ならない。 ハイエクの社会進化論とは、およそこのようなものである。 しかし、社会進化論を主張するからといって、ハイエクは、社会を意図的に進化させ得ると考えている訳では些かもない。 あるルールに従うことが、その社会にいかなる帰結をもたらすかは、自生的秩序としての社会においては原理的に不可知である。 すなわち、あるルールが、社会にとって何の役に立つかは、事前には知り得ないのである。 従って、あるルールに従うことが、社会に成功をもたらすか否かは、そのルールを暗黙的に遂行した結果として始めて知られ得ることになる。 言い換えれば、ルールは、それに従う社会が成功することによってはじめて、その進化論的な優位を証明し得るのであって、進化論的な優位が予知されることによって、それに従う社会が成功する訳ではないのである。 それゆえに、あるルールの採否を、それが社会にもたらす得失の予測に基づいて決定するといった、(たとえばルール功利主義のような)意図的な社会進化の試みは、不可避的に失敗するのである。 もっとも、ハイエクは、ある特定のルールを意図的に改良する可能性までも否定する訳ではない。 ある特定のルールに限るのであれば、それを対象として意識的に言及したり、意図的に改良したりすることは、もちろん可能である。 むしろ、何が従うべきルールであるのかをめぐって紛争が生じた場合など、遂行的に従われているルールを意識的に分節し、その不確定な部分を確定すべく、新しいルールを意図的に設定すべきでさえある。 しかし、このような分節や設定やが可能なのは、あくまで、ある特定のルールについてのみであって、決して、ルールの全体についてではあり得ない。 ルールを分節し設定する行為もまた、何等かのルールに従っているのであって、分節あるいは設定行為自体の従うルールを、当の行為者自身が分節しあるいは設定することは不可能だからである。 (あるいは、そのようなルールの分節/設定は、また別のルールに従っているのであって、いずれにせよ、すべてのルールを分節/設定し尽くすことは不可能なのである。) 言い換えれば、ある特定のルールを意識的に分節し意図的に設定する行為は、その他の総てのルールを暗黙的、遂行的に前提して始めて可能になるのである。 すなわち、ルールのあらゆる改良は、遂行的に従われているルールの全体を、無批判的に受け容れることによって始めて可能になるのである。 さらに、ルールの改良は、それが(自生的秩序としての)社会にいかなる帰結をもたらすかを予測しつつ為されるものでは、決してあり得ない。 そんなことが不可能であることは、既に述べた通りである。 ここで言うルールの改良とは、何が従うべきルールであるかを巡って紛争が生じた場合に、そのような紛争を解決すべく、ルールの不確定な部分を確定するということ以上のものではない。 このようなルールの境界確定において考慮されるのは、それが社会全体にもたらすであろう便益の予測ではなく、たとえばそれが現行のルールの総体と整合するか否かといった原理である。 すなわち、ルールの改良において考慮されるのは、その社会的な帰結ではあり得ず、その内在的な整合なのである。 なるほど、その社会的な効果に配慮しつつ、ルールを改定することもあるには違いない。 しかし、そのルールがいかなる意図によって設定されたかということと、果たしてそれがいかなる自生的秩序を形成するのかということは、(自生的秩序は意図的には構成し得ないのであるから)実は全く無関係なのであって、むしろ、その設定の意図が忘却されることによって始めて、ルールは安定した自生的秩序を形成し得るとも言い得るのである。 従って、ルールの改良は、遂行的に前提されているルールの総体との、内在的な整合性のみを考慮しつつ、言わば(社会的な)結果を顧みずに為されざるを得ないのである。 これが、ハイエクの言う、ルールの意図的な改良における整合性(coherency)の原理に外ならない。 ◆2.外的視点 - ハート -人間の行為の集合に秩序(order)が存在するということは、そこに何等かの規則性(regularity)、構造(structure)、型(pattern)といったものが見い出されることに外ならない。
同様に、人間の行為の集合がルールに従っているということも、差し当たり、そこに何等かの規則性が見い出されることを意味している。 すなわち、行為の集合にルールが存在するということは、差し当たり、行為が整然と規則正しく(regularly)遂行されていることに外ならないのである。 ハートの言うルールもまた、差し当たり、行為が規則性を持って遂行されている事態として捉え得る。 ハートによれば、ある人間の集団がルールに従っているという事態は、その集団の外部に立って観察するならば、そこでは行為が規則性を持って遂行されているという事態として見えて来る筈である。 言い換えれば、あるルールが存在するということは、そのルールには従っていない外部の視点から見るならば、そこで遂行されている行為に、何等かの規則性が観察されるということ以外の何ものでもないのである。 このように、ルールの存在を、そこにおける行為の規則性として観察する、外部からの観察者の視点を、ハートは、外的視点(external point of view)と呼んでいる。 すなわち、外的視点とは、観察の対象となるルールには従わない、あるいは、そのルールの形成する社会的秩序には内属しない、いわば異邦人の視点なのである。 このような異邦人の視点(外的視点)から見た、ルールの、行為における規則性の存在として観察される側面を、ハートは、ルールの外的側面(external aspect)と呼ぶ。 従って、ルールが、単なる行為の観察可能な規則性に見えることがあるとすれば、それは、外的視点に立って、その外的側面のみを見ている場合なのである。 あるルールの形成する秩序に内属しない外的視点、あるいは、そのような外的視点から観察される、ルールの外的側面という概念を立てるからには、ルールの形成する秩序に内属する内的視点、あるいは、そのような内的視点から把握される、ルールの内的側面という概念もまた反射的に立てられよう。 ハートは、あるルールに従っている人々の視点、すなわち、そのルールを根拠あるいは理由として、自らの行為の当否を判定している人々の視点を、そのルールについての内的視点(internal point of view)と呼んでいる。 この内的視点から見るならば、ルールは、単に行為の規則性を持った遂行として観察されるのではなく、自らの行為の妥当性を理由付ける(根拠付ける)規範として把握されることになる。 このように規範として把握されるルールの側面こそが、ルールの内的側面(internal aspect)に外ならない。 しかし、ルールについての内的視点、あるいは、ルールの内的側面の検討は、次章の課題である。 本章では、ルールについての外的視点、あるいは、ルールの外的側面の検討に、議論を限定したい。 ルールわけても法的なルールについての客観主義的理論を論駁するに際しては、ルールについての外的視点に立つことが、最も効果的であると思われるからである。 ところで、あるルールについて、その外的視点に立つことは、そのルールを自らの従うべき規範とは見なさずに、そのルールの形成する秩序の外側に身を置いて、そのルールを観察する、言わば異邦人の立場を取ることである。 この異邦人の視点からは、ルールは、繰り返し観察される行為の規則性、あるいは単なる習慣と見なされるに過ぎない。 しかし、このような視点に立つことによって、あるルールに従っている人々の行為を、かなりの蓋然性を持って予測することが可能になる。 すなわち、行為における規則性の認識は、たとえば、ある条件の下では、いかなる行為が遂行され易いか、さらには、ある行為の遂行は、どの程度の(敵対的な)反作用を被るかといった予測を、かなりの精度において可能にするのである。 ここに、ルールわけても法的ルールについての客観主義的な理論の可能性を見い出す向きも、あるいはあるかも知れない。 しかし、ある特定のルールに対して外的視点を取る観察者は、如何なるルールにも内属しないという訳ではない。 観察もまた一つの行為である以上、如何なるルールについての内的視点も取らない、すなわち、あらゆるルールに対して外的視点を取る観察者など、決して存在し得ないのである。 従って、何等かの予測が可能になるのは、ある特定のルールに従う行為(とその行為に帰責可能な範囲の帰結)についてのみであって、任意のルールに従う総ての行為(さらにはその社会全体に対する帰結)についてでは、全くあり得ないのである。 そのうえ、ルール一般とは区別される、法的ルールにおいては、人々の行為の当否を判定する根拠となるルール(一次ルール)に対して、意識的に外的視点を取ることによって、そのルールを変更したり、解釈したり、あるいは(ルールそれ自体の妥当性を)承認したりする行為が本質的に重要となる。 しかし、それらの行為もまた、何等かのルール(二次ルール)に遂行的に従っているのであって、自らの従っているルールについては、内的視点以外取り得ようもないのである。 いずれにせよ、あるルールに対して外的視点に立ついかなる者も、何等かのルールに従った内的視点に立たざるを得ないのである。 ハートは、人々の行為の当否を判定する理由となるルールそれ自体を対象として、それに変更を加えたり、それに基づいて裁定を下したり、さらには、それがルールとして妥当することに承認を与えたりする行為と、そのような行為自身の従うルールの存在が、法あるいは法体系の概念を定式化するに当たって、不可欠の要件であると考えている。 すなわち、ハートは、通常の行為の従うルールを一次ルール(primary rule)と呼び、一次ルールを対象とする変更や裁定や承認やの行為の従うルールを二次ルール(secondary rule)と呼んで、法(体系)とは、一次ルールと二次ルールとの結合であると定式化する。 法わけても一次ルールは、変更や裁定や承認やという意図的な行為の対象になることを、その本質としているという訳である。 しかし、法体系を構成する二次ルールは、(変更や裁定や承認やという)意図的な行為の対象とは、ついになり得ない。 このことを、二次ルールの内でも際立って重要な位置を占めている、承認という行為の従うルール、すなわち、ハートの言う、承認のルール(rule of recognition)について見てみよう。 あるルールを承認するとは、そのルールが人々によって従われるべきであると判定する、言い換えれば、そのルールがルールとして妥当(valid)であると評価することに外ならない。 従って、承認のルールは、何が妥当な(一次)ルールであるかを評価する規準を与えることになる。 すなわち、(一次)ルールは、承認のルールの与える規準を充たすことによって始めて、ルールとして妥当し得るのである。 言い換えれば、承認のルールは、(一次)ルールを妥当させる根拠となっているのである。 それでは、承認のルールそれ自体は、如何なる根拠によって、妥当し得るのであろうか。 容易に確かめられるように、この問いに答えることは、どこかで断念されざるを得ない。 すなわち、あるルールの妥当性を、他のルールの与える規準によって評価しようとする試みは、どこかで断念されない限り、無限後退に陥るのである。 ハートは、その妥当性を根拠付け得る如何なるルールも存在しない、従って、その妥当性を全く評価し得ない承認のルールを、究極の(ultimate)承認のルールと呼ぶ。 すなわち、究極の承認のルールとは、それ自体の妥当性を承認する根拠は決して持ち得ないが、その法体系に属する如何なるルールの妥当性をも承認する(究極的な)根拠となり得るルールなのである。 言い換えれば、究極の承認のルールは、承認という意図的な行為の対象とは、ついになり得ないルールなのである。 それでは、このような究極の承認のルールは、何故に、その他のルールを妥当させる根拠となり得るのであろうか。 究極の承認のルールは、自らを妥当させる如何なる根拠も持ち得ないという意味において、まさしく無根拠である。 このように自らは無根拠な究極の承認のルールが、如何にして、他のルールを妥当させる根拠となり得るのであろうか。 究極の承認のルールといえども、ルールである以上、その外的側面を持っている筈である。 すなわち、究極の承認のルールもまた、その外的視点(承認の視点ではなく、単なる観察の視点)から見るならば、繰り返し遂行される行為の規則性、あるいは慣習(practice)以外の何ものでもないのである。 言い換えれば、究極の承認のルールは、その法体系に属するルールの妥当性を承認する行為において、繰り返し示される規則性、あるいは習慣的に遂行される慣習として捉え得る側面を持っているのである。 この、究極の承認のルールの、慣習(practice)としての側面、すなわち遂行的(performative)な事態としての側面こそが、その(法体系に属する)他のルールを妥当させる根拠としての側面、すなわち規範的(normative)な事態としての側面と、表裏一体をなしているのである。 あらゆる法体系には、それに属するルールが、ルールとして妥当するか否かを決定し得る、承認(recognition)という行為が必ず存在している。 自らに属する一切のルールの当否を決定し得て始めて、一個の法体系と呼び得るという訳である。 この承認という行為が、繰り返し遂行されることの内に、何がルールとして妥当し得るかを決定する規準、すなわち承認のルールが示されるのである。 言い換えれば、承認という行為は、その持続的な遂行を通じて、何等かのルールを、自らの従うべきルールとして、受容していることを示すのである。 このことは、究極の承認のルールが、その外的視点から見るならば、承認という行為の持続的な遂行に外ならないにもかかわらず、承認という行為を遂行する側、すなわちその内的視点から見るならば、他のルールを妥当させる根拠として、自らが従うべき規範でもあり得る事態を指し示している。 すなわち、究極の承認のルールは、承認という行為の持続的な遂行であると同時に、その同じ事態が、他のルールの妥当性を根拠付け得る、(承認という行為の当否を判定し得る)規範ともなっているのである。 従って、究極の承認のルールが、その法体系に属する他の総てのルールの妥当性を根拠付け得るのは、それが、承認という行為の持続的な遂行の内に、繰り返し示されているからに外ならないことになる。 言い換えれば、究極の承認のルールが、他のルールの当否を決定し得る規範たるにおいては、それに従う行為が持続的に遂行されていること以外の、いかなる根拠もあり得ないのである。 究極の承認のルールは、その内的視点から見れば、他のルールを妥当させる根拠となる規範であるが、その外的視点から見れば、承認という行為の持続的な遂行であるという二つの側面を持つ、一個の事態に外ならない。 究極の承認のルールは、その持続的な遂行において始めて、他のルールの妥当根拠たり得るのである。 これに対して、承認のルールを含む二次ルールと対比される、一次ルールは、それが(通常の)行為の当否を判定する根拠となるに当たって、その持続的な遂行を必ずしも前提とされる訳ではない。 一次ルールが、行為の当否を判定する根拠たり得る、言い換えれば、ルールとして妥当し得るのは、それが、持続的に遂行されているからではなく、承認という行為によって意識的に承認されているからなのである。 すなわち、一次ルールは、たとえ、かつて一度も遂行されたことが無いとしても、承認されている限り、行為の自らに従うべきことを正当化し得るのである。 しかし、このように、承認という意図的な行為によって正当化し得るルールは、一次ルールと二次ルールの結合としての法体系における、一次ルール以外にはあり得ない。 一般のルールは、その妥当性を、如何なる(意図的な)行為によっても、根拠付け得ないのである。 この意味において、一般のルールは、究極の承認のルールとその位相を同じくしている。 あるいは、むしろ究極の承認のルールこそが、法体系に属するルールの内で(究極的であるがゆえに)唯一その外部に開かれているという意味において、一般のルールと同相なのである。 一般のルールと、究極の承認のルールとの違いは、前者が、(一般の)行為の当否を判定する根拠となっているのに対して、後者が、(一次)ルールの当否を判定する根拠となっているという点のみにある。 いずれのルールも、その持続的な遂行によって始めて、当否判定の根拠たり得るという点においては、いささかの違いもないのである。 従って、究極の承認のルールについて、これまでに述べてきた議論は、一般のあらゆるルールについても、ほとんどそのままの形で成立し得ることになる。 すなわち、法体系として構成される以前の法的ルールはもとより、社交や言語や技能や儀礼や流行や道徳や慣習や伝統やといった、あらゆるルールに対して、究極の承認のルールをめぐるハートの理論は、適切な議論となり得るのである。 加えて、ハートは、究極の承認のルールが、従ってまた(二次ルールの対象としての一次ルールを含まない)一般のルールも、語り得ぬ、ただ示されるのみの事態であることを強調している。 すなわち、ハートは、究極の承認のルール、さらには一般のルールが、慣習(practice)という遂行的な事態であるとともに、言明し得ぬ暗黙的な事態でもあると主張するのである。 究極の承認のルールは、承認という行為の習慣的な遂行を通じて、経験的(遂行的)に従われているのであって、対象として言及されることによって、意識的に従われている訳ではない。 すなわち、究極の承認のルールには、それを客観的な対象として言及し、その上で、それを従うべきルールとして意識的に受容する、いかなる手続きも存在し得ないのである。 これは、究極の承認のルールが究極的であることの、ほとんど自明な帰結である。(因みに、究極の承認のルールは、承認という意図的な行為の対象とは、ついになり得ないのであった。) 従って、究極の承認のルールは、遂行的に従われていることによって、暗黙的に受け容れられているのである。 言い換えれば、究極の承認のルールは、遂行的な事態であるがゆえに、暗黙的な事態ともなっているのである。 このような遂行的かつ暗黙的な事態としての究極の承認のルールが、いずれかの主体による意図的な制御の対象となり得ないことは、言うまでもなかろう。 究極の承認のルールを、意図的に設定したり変更したり廃棄したりする試みは、不可避的に失敗するのである。 (もっとも、究極の承認のルールといえども、部分的には、意図的な制御の対象となり得る場合のあることを、ハートは指摘している。これは、ハイエクの言う、整合性の原理が適用される場合と、ほとんど同じである。しかし、この場合についての検討は、次章に委ねたい。) 従って、究極の承認のルールは、それが遂行的に示されている行為の変化に伴って、変化することになる。 すなわち、究極の承認のルールは、行為の習慣的な遂行の(意図せざる)結果として、生成し、また消滅するのである。 ところで、究極の承認のルールについて、その外的視点に立つ観察者が、それを対象として言及することは、もちろん可能である。 もし、このことが不可能であるならば、そもそも、社会哲学など存立し得る筈もない。 しかし、そうであるからと言って、究極の承認のルールが暗黙的であることに、些かの変りもない。 差し当たり、外的視点に立つ観察者といえども何等かのルールに従わざるを得ないという問題は措くとしても、究極の承認のルールは暗黙的なのである。 何故ならば、観測者が、究極の承認のルールを、いかに正確に分節し得たとしても、観察者の分節という行為によっては、究極の承認のルールの従われるべきことは、少しも正当化され得ないからである。 すなわち、観察者の行為は、あくまで観察に過ぎないのであって、その対象となるルールの妥当性を根拠付け得る(承認の)行為とは、決してなり得ない。 従って、そのルールが観察者によって如何に正確に言明され得たとしても、自らがそのルールに従うべき根拠は、少しも対象として意識され得ないのである。 言い換えれば、あるルールに遂行的に従っている行為者にとっては、観察者がそのルールを分節し得るか否かに拘わらず、そのルールを暗黙的に受け容れさるを得ないのである。 それゆえに、その外的視点にたつ観察者が、たとえ、何等かのルールを対象として分節し得たとしても、その内的視点に立つ行為者にとっては、そのルールに従うことは、依然として暗黙的な事態なのである。 ◆3.発語的行為 - オースティン -言葉は、つまるところ、何等かの事実を記述している。
あるいは、言葉の意味は、それが記述する対象である、さらには、言葉は、それが記述する事実の存否によって、その真偽を確定しうる、あるいは、言葉は、その真偽の確定し得る場合にのみ、有意味である、といった記述主義の言語観を、オースティンは批判する。 オースティンの用語系によれば、記述主義とは、差し当たり、言葉を発すること、すなわち発言(発話)の総ては、事実を記述し、真偽を確定し得る、事実確認的(constattive)発言に還元されるか、さもなくば、ナンセンスに帰着するという主張に外ならない。 しかし、あらゆる発言を、事実確認的発言に還元し尽くすことは、果たして可能なのだろうか。 たとえば、何等かの権能に基づいて指図する場合の指図や、あるいは、何等かの判定理由を明らかにして審判する場合の審判の発言や、さらには、何等かの行為の履歴を約束する場合の約束の発言やは、事実を記述している訳でもないし、また、その真偽が問題となっている訳でもない。 しかし、これらの発言が、社会生活において、極めて重要な種類の発言であることは論を俟たない。 財産権や人格権の行使や、契約や、あるいは、それらを巡る裁判やは、社会生活の根幹を成している。 記述主義は、このような指図や審判や約束やの発言を、その焦点から外してしまっているのである。 (もちろん、記述主義が、これらの発言に、何の位置付けも与えていない訳ではない。前章で述べたように、記述主義から見れば、これらの発言は、主観的な意図の表出に外ならないことになる。しかし、この点についての検討は、次章の課題である。) 指図や審判や約束やの発言は、その発言を遂行することそれ自体が、指図や審判や約束やといった、社会的行為そのものを遂行することになる種類の発言である。 たとえば、「~を約束します」と発言することは、取りも直さず、約束という社会的行為を遂行することに外ならない。 すなわち、これらの発言においては、言うことが、行うこととなっているのである。 このように、発言することが、(発言という行為とは区別される)社会的行為を遂行することになる種類の発言を、オースティンは、差し当たり、行為遂行的(performative)発言と呼ぶ。 事実確認的発言に焦点を合わせている記述主義は、この行為遂行的発言を捕捉し得ないのである。 行為遂行的発言は、もとより、事実を記述している訳ではなく、従って、その真偽も確定し得ない。 行為遂行的発言は、真偽いずれでもないのである。 しかし、行為遂行的発言であれば、いかなるものでも、社会的行為として効力を発揮するという訳でもない。 たとえば、指図する権限のない者による指図や、判定理由を示し得ない審判は無効であり、約束された行為が履行されない約束は不実である。 すなわち、行為遂行的発言は、何等かの条件を充たすことによって始めて、社会的行為としての効力を獲得するのである。 オースティンは、この、行為遂行的発言を社会的行為として発効させる条件を、行為遂行的発言の適切性(felicity)の条件あるいはルールと呼んでいる。 従って、行為遂行的発言は、それを発効させるルールを根拠として、適切あるいは不適切のいずれかに判定されるのである。 しかし、いかなる行為遂行的発言が適切であるかを決定するルールの検討は、次章に委ねられる。 ここでは、事実確認的発言と対比される意味での行為遂行的発言の検討に議論を限定したい。 行為遂行的発言の概念こそが、記述主義の批判に対して、最も有力な手掛かりを与え得るからである。 この行為遂行的発言の概念と、言語行為(speech act)の一般理論との関係は、オースティン本人においても、かなり微妙である。 もちろん、行為遂行的発言の発見なしには、言語行為の一般理論が構想され得なかったであろうことは言うまでもない。 しかし、言語行為の一般理論が構成されるに及んで、行為遂行的発言の概念が後景に退けられたこともまた明らかである。 行為遂行的発言と言語行為とは、果たして、如何なる関係に置かれているのであろうか。 前章で述べたように、オースティンによれば、言葉を発すること、すなわち発言(発話、発語)することは、以下の三種の行為を同時に遂行することに外ならない。 言い換えれば、言うことは、以下の三種の位相において、行うことなのである。 その第一は、発語という行為それ自体が、何等かの事態を意味する、すなわち何等かの事態を指示する行為に外ならないという発語行為(簡単のために、ここでは、音声行為および用語行為を捨象して、発語行為を意味行為あるいは指示行為に限定している)の位相であり、 第二は、発語することが、何等かの社会的な効力を持つ(発語それ自身とは区別される)行為を遂行することになるという発語内行為の位相であり、 第三は、発語することを手段として、発語主体の意図する、何等かの結果を達成することが目指されるという発語媒介行為(ここでは、発語主体の意図せざる結果を捨象している)の位相である。 オースティンは、以上の三種の行為を総称して、言語行為と呼んでいる。 すなわち、言語を発話することは、以上の三種の位相において、行為を遂行することなのである。 行為遂行的発言と発語内行為、さらには、事実確認的発言と発語行為が密接に関連していることは一見して明らかであろう。 しかし、両者は同じものではあり得ない。 何故なら、行為遂行的発言と事実確認的発言との区別は、ある一つの発言をいずれかのカテゴリーに分類するための区別であるのに対して、発語内行為と発語行為との区別は、ある一つの発言を幾つかの(行為の)位相に分解するための区別だからである。 すなわち、ある一つの発言が、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言のいずれに分類されたとしても、その発言には、発語内行為および発語行為(さらには発語媒介行為)の位相が常に存在し得るのである。 従って、行為遂行的発言も、発語行為の位相を持つという意味において、何等かの事実を指し示していることになるし、また、事実確認的発言も発語内行為の位相を持つという意味において、何等かの行為を遂行していることになる。 このような、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言と発語内行為あるいは発語行為との関係を、つぶさに検討することによって、記述主義を乗り越える言語行為論の射程が、詳(つまび)らかにされるのである。 ところで、何等かの社会的効果を帰結する点においては共通している、発語内行為と発語媒介行為との相違は、前章で述べたように、発語内行為の効力が、そのような効力を発生させる根拠となる、何等かの慣習によって支えられているのに対して、発語媒介行為の結果は、そのような慣習に支えられなくとも達成され得るという点にある。 言い換えれば、発語内行為は、慣習に従う限りにおいて、その社会的な効力を発揮し得る言語行為の位相であるのに対して、発語媒介行為は、慣習に従うか否かに拘わらず、その(発語主体の意図する)社会的な結果を達成し得る言語行為の位相なのである。 ここに言う慣習が、すでに述べた、行為遂行的発言にちての適切性のルールと同じものであることは、確認されねばならない。 すなわち、発語内行為の効力の存否を判定する根拠は、(行為遂行的発言についての)適切性のルールなのである。 従って、発語媒介行為は、発語行為のように、それが指示する事実に基づいて、その真偽を判定し得る訳ではなく、また、発語内行為のようにそれが従うルールに基づいて、その当否(適切・不適切)を判定し得る訳でもない、言語行為の第三の位相ということになる。(実は、発語媒介行為は、それが達成しようとする発語主体の意図に基づいて、その成否を判定し得るのであるが、この点についてはここでは触れない。) しかし、発語内行為の当否を判定し、また、発語内行為と発語媒介行為とを区別する、慣習あるいは適切性のルールについての検討は、次章の課題である。 ここでは、発語内行為と行為遂行的発言との関連、および、発語内行為と発語行為との区別に議論を限定したい。 それでは、行為遂行的発言あるいは事実確認的発言と発語内行為および発語行為とは、いかなる関係に置かれているのであろうか。 まず、事実確認的発言は、言うまでもなく、事実を記述し、その真偽を、それが記述する事実の存否に基づいて判定し得る種類の発言なのであるから、紛れもなく、発語行為の位相を保有している。 このような事実確認的発言は、果たして、発語内行為の位相をも保有しているのであろうか。 たとえば、「現在のフランス国王は禿である。」という発言を考えてみよう。 この発言は、典型的な記述命題であって、明らかに事実確認的発言である。 しかし、現在のフランスに国王など存在しないのであるから、その国王が禿であるか否か、言い換えれば、この発言の真偽を、事実に基づいて判定することは不可能である。 それでは、この発言は、無意味であろうか。 否である。 この発言の指示する対象は(それが事実として存在しているか否かに拘わらず)明瞭である。 この発言が奇異な感じを与えるのは、それが無意味だからではなく、むしろ、事実として存在していない対象についての記述命題が、発言として不適切だからである。 すなわち、記述命題という事実確認的発言は、それが術定する対象(ここでは現在のフランス国王)が、事実として存在し得るという条件を充たすことによって始めて、有効あるいは適切な発言として遂行されるのである。 これは、たとえば指図という行為遂行的発言が、指図する権能が存在するという条件を充たすことによって始めて、社会的な効力を有する適切な発言として遂行されるという場合に類似している。 言い換えれば、事実確認的発言と言えども、その真偽が問題とされる以前に、事実確認あるいは記述という社会的行為を遂行する発言として、有効/適切であるか否かが問題とされるのである。 従って、事実確認的発言においても、行為遂行的発言と同様に、その発言が、社会的な効力を持つか否か、あるいは、適切であるか否かが問われる位相が存在することになる。 すなわち、事実確認的発言にも、発語内行為の位相が、確かに存在するのである。 また、「現在のフランス国王は禿である。」という発言は、「禿でないならば現在のフランス国王ではない。」という発言を論理的に帰結する。 従って、ひとたび前者の発言を遂行したならば、後者の発言を拒否することは、論理のルールに違反することになる。 これは、ある行為の履行を約束する発言を遂行したならば、その行為を履行しないことは、約束のルールに違反することになる場合に類似している。 すなわち、いずれの場合においても、ある発言の遂行が、何等かの行為の遂行を義務付け、その行為の遂行を拒否した場合、何等かのルール違反に問われるのである。 言い換えれば、約束と言う行為遂行的発言が、その目的あるいは帰結としての行為の履行されなかった場合に、不誠実あるいは不適切(ルール違反)になるのと同様に、記述という事実確認的発言もまた、その(論理的な)帰結としての行為の履行されなかった場合、不適切(ルール違反)になるのである。 従って、ここでもまた、事実確認的発言は、その真偽を問われる以前に、社会的行為を遂行する発言として、適切であるか否かを問われることになる。 すなわち、事実確認的発言には、発語内行為の位相が、確かに存在しているのである。 続いて、行為遂行的発言を取り上げよう。 行為遂行的発言に、発語内行為の位相が存在していることは、言うまでもなかろう。 それでは、行為遂行的発言に、果たして、発語行為の位相は存在するのであろうか。 たとえば、判決という行為遂行的発言を考えてみよう。 判決という発言は、言うまでもなく、ある行為の当否を、潜在的には明示し得る判定理由に基づいて判定するという社会的行為の遂行である。 通常の場合、この判決理由は、あるカテゴリーに属する行為の当否を規定している一般ルールと、問題となっている行為がそのカテゴリーに属するか否かについての判断から構成されている。 すなわち、当該行為は、ある一般的なルールの違反に該当する故に、妥当ではないと判決するといった具合である。 このとき、問題となっている行為が、一般的なルールに違反するカテゴリーの行為に該当するか否かについての判断は、記述命題の真偽についての判断と極めて類似している。 いずれの判断も、それが指示する事実に基づいて、その分類が決定されるからである。 因みに、前者の判断は、後者の判断と同じく、事前判断と呼ばれることも多い。 従って、判決という行為遂行的発言は、その社会的な効力を根拠付ける判定理由の核心において、事実確認的発言あるいは発語行為を常に前提せざるを得ないのである。 また、判決という行為遂行的発言は、たとえば、「甲は乙に損害賠償を支払うべし。」といった当為命題であることが多い。 このような当為命題は、「甲は乙に損害賠償を支払う。」という記述的あるいは指示的(phrastic)と、「~すべし」という指図的あるいは承認的部分(neustic)とに分解することが常に可能である。 ここで言う記述的あるいは指示的部分が、発語行為の位相を持っていることは明らかであろう。 すなわち、当為命題という行為遂行的発言は、その記述的あるいは指示的部分が常に存在するが故に、発語行為の位相を必ず内包しているのである。 行為遂行的発言における発語行為の位相の存在についてのこのような説明は、オースティン本人のそれと言うよりも、むしろ、ヘアあるいはサールによるものである。 他の点はいざ知らず、この点に関しては、ヘアあるいはサールの議論は、オースティンの言語行為論の理解にとって、極めて有効な視座を提供していると思われる。 行為遂行的発言を、記述的あるいは指示的部分という発語行為の意味を指定する核心部分と、指図的あるいは承認的部分という発語内行為の効力を指定する境界部分に分解して理解することは、ある一つの言語行為には、常に三種類の(行為の)位相が存在していると考える、言語行為論の着眼を、より明晰な分析枠組みに高めるものである。 記述主義は、このような分析枠組みの獲得によって、ようやく乗り越えられることになるのである。 これまで述べてきたように、事実確認的発言もあるいは行為遂行的発言も、発語内行為および発語行為の位相を同時に保有していることが明らかになった。 従って、事実確認的発言と行為遂行的発言との区別は、実は相対的なものであって、むしろ、両者は、発語行為の位相をその核心部分に持ち、各々に種類の異なる発語内行為の位相をその境界部分に持つ、一連の言語行為の二つの種類であると考えられるのである。 言い換えれば、事実確認的発言は、記述(言明解説)という発語内行為を遂行する言語行為なのであり、行為遂行的発言は、指図(権能行使)や判決(判定宣告)や約束(行為拘束)やという発語内行為を遂行する言語行為なのであって、また、いずれも、何等かの事態を指示する部分として発語行為を内包する言語行為なのである。 このような言語行為論の視点から見れば、記述行為は、言語行為という多元的な現実を、その記述的あるいは指示的な部分のみに一元化して把握しようとする、対象指示一元論あるいは意味行為一元論であることが明らかになる。 記述主義は、言語行為の唯一つの位相しか捉えていないのである。 しかし、我々の言語の現実の在り方である言語行為は、対象指示に還元し尽くされる筈もない。 如何なる対象指示と言えども、発語内行為の種類が指定されることによって始めて、言語行為、すなわち、発話として社会的に発効するのである。 従って、記述の発話と言えども、それが社会的な効力を有する適切な発話であるためには、何等かのルールに従っていなければならないことになる。 しかし、言語行為の従うルールについての検討は、次章の課題である。 |
| + | ... |
◆1.規範的秩序 - ハイエク -あらゆるルール、わけても法的ルールは、主権者と呼ばれる主体によって、意図的に設定されたものである、あるいは、あらゆる法は、主権者の意志の表出である、と考える法の主権者意志説は、主権者の権力の無制限を帰結した。
多数者としての大衆が主権者の高みにある今日においては、これは、多数者大衆に無制限の権力を委ねることに等しい。 しかし、総ての(法的)ルールを主権者が意図的に設定することなど、果たして可能なのであろうか。 あるいは、如何なる(法的)ルールによっても制限され得ない主体など、果たして存在し得るのであろうか。 ハイエクは、この問いに対して、如何なる行為、あるいは、如何なる主体と言えども、何等かの先験的なルールあるいは形式に従うことによって、始めて行為あるいは主体足り得るという議論を以て答える。 すなわち、ハイエクは、あらゆる行為(主体)は、カントの言う先験的カテゴリーに類似した、先験的なルール(あるいは形式)を前提することによって、始めて存在し得ると言うのである。 ハイエクによれば、あらゆる行為は、あるカテゴリーに属する行為の当否を決定する一般的なルールが、無数に重ねあわされることによって、特定されたものである。 言い換えれば、ある特定の行為は、ある一般的なクラスに属する行為の是非を判定する抽象的なルールが、幾層にも積み重ねられることによって、構成(constitute)されるのである。 従って、ハイエクの言う抽象的なルールは、具体的な行為に常に先行し、行為を行為足らしめるという意味において、それを構成するものである。 すなわち、ハイエクの言う抽象的なルールは、カントの意味において、まさに先験的なのである。 この意味において、ハイエクは、紛れもないカント主義者であると言えよう。 ハイエクは、ある特定の具体的な行為が、一般的、抽象的なルールの重ね合わせによって構成されるとする彼の主張を、抽象的なるものの優位性(primacy of the abstract)と呼んでいる。 抽象的なるものは、具体的なるものから、主体的な行為によって、作成されたものではなく、むしろ、主体的な行為をも含む具体的なるものこそが、抽象的なるものによって、そのものとして構成されると言うのである。 言わば、ハイエクは、あらゆる行為を、何等かの抽象的なルール群によって構成された、社会的なゲームの具体的な遂行であると考えているのである。 従って、あらゆる行為は、社会的なゲームを構成する先験的なルールを前提として始めて存在することになる。 しかし、ハイエクは、具体的な行為に対する抽象的なルールの先験性を主張するからと言って、必ずしもカントの議論の総てを引き受ける訳ではない。 ハイエクにとって、先験的なルールは、決して絶対的なものではあり得ない。 前章で見たように、ハイエクの言うルールは、行為の持続的な遂行を通じて生成され、また、経験的に遂行されていること以外には、それに従うべきいかなる根拠も持ち得ない、相対的なものである。 すなわち、ハイエクの言うルールは、行為の歴史的あるいは地域的な遂行に相対的である、遂行的な秩序なのである。 ここで、行為の持続的な遂行にのみ根拠を持つルールが、何故、行為を先験的に構成し得るかという疑問が、当然、生じて来ると思われる。 行為によって生成されるルールが、何故、行為を構成し得るのか、まことに当然な疑問である。 しかし、この問いに答えることは、本節の後半まで、しばらく預けて置くことにしよう。 ここでは、行為を構成する先験的なルールの存在が、法の主権者意志説に現れている主体主義あるいは個体主義に対して、いかなる含意を持ち得るかを、まず検討してみたい。 さて、ルールの、行為の当否を判定して、行為の秩序を構成するという側面を、その規範的(normative)な側面と呼ぶことにする。 すなわち、ルールは、暗黙的な側面とともに規範的な側面を持つ秩序なのである。 ところで、ルールが存在すると言うことは、行為に何等かの秩序が存在すると言うことに外ならないのであるから、ルールの存在と、ルールに行為が従うことによって形成される自生的秩序の存在とは、実は、同じ一つの事態に外ならないと言い得る。 自生的秩序は、ルールの構成する社会的なゲームであると見なし得るので、これは、あるルールの構成するゲームの記述と、あるゲームを構成するルールの記述とが、同等である、と言うに等しい。 従って、ルールが、規範的な側面を持つということは、取りも直さず、自生的秩序もまた、規範的な側面を持つということに外ならないことになる。 すなわち、自生的秩序もまた、暗黙的であるとともに規範的でもある秩序なのである。 言い換えれば、自生的秩序は、行為の内に黙示され、行為の意識的な対象とななり得ない秩序であるとともに、行為の外に前提され、行為を規範的に拘束する秩序なのである。 このような、ルールと、それに行為が従うことによって形成される自生的秩序とに、規範的な側面が存在することの主張は、たとえば法の主権者意志説に対して、いかなる含意を持っているのであろうか。 あらゆる行為には、その行為を行為として発効させる、先験的なルールが前提されるのであるとすれば、主権者による法の制定という行為もまた例外ではあり得ない。 すなわち、主権者による法の制定もまた、(主権者自身の制定に因らない)何等かのルールに従っている筈である。 この意味においては、主権者と言えども、なるほど無制限ではあり得ない。 しかし、この意味において主権者を拘束するルールは、たとえば、法は言語によって記述されねばならず、法の制定は言語のルールに従わねばならない、といった極めて抽象的なレベルのルールを含むものである。 従って、この意味におけるルールに、何の限定も加えないとするならば、なるほど、主権者は何等かのルールによって制限されてはいるが、法的には全く無制限である、ということにもなりかねない。 たとえば、日本語で立法しさえすれば、いかなる法でも立法し得るといった具合である。 すなわち、主権者を制限するルールが、実質的な意義を持ち得るのは、あくまで、それが法的なレベルにおけるルールである場合なのである。 それでは、主権者の立法に先行し、主権者の立法を制限する、法的なルールとは、いかなるルールであるのか。 それは、主権者が意図的に設定する(法的)ルールを、(法的)ルールとして妥当させる理由あるいは根拠となるルールである。 すなわち、主権者の法を制定する際に従うべき手続きや、主権者の制定する法の充たすべき一般的な内容といった、法が法として発効するための要件を規定する(法的)ルールによって、主権者は制限されるのである。 このようなルールは、言語によって記述された憲法をもちろん含み得るが、決して、それに留まるものではあり得ない。 何故なら、このようなルールは、書かれた憲法のように、主権者によって意識的に制定されたものではありえないからである。 すなわち、法の主権者意志説が主権者の無制限を帰結することの対偶を取れば明らかなように、主権者を制限し得るルールは、主権者によって設定されたものではついにあり得ないのである。 主権者を制限し得る法的ルールは、主権者の意図的に設定したものではないとすれば、主権者の遂行的に従っているそれ以外にはあり得ない。 すなわち、主権者の、その行為において、慣習的に遂行しているルールこそが主権者を制限し得るのである。 言い換えれば、主権者の行為は、自らの遂行的に従う、慣習的なルールを根拠にして始めて、主権者の行為として法的に発効し得るのである。 従って、この場合、主権者の遂行的に従うルールが、その行為を規範的(あるいは先験的)に構成するルールに転化していることになる。 しかし、このような、遂行的なルールの規範的なルールへの転化の問題は、本節の最後で取り上げることにする。 ここでは、主権者の行為を法的に発効させる根拠となるルールによって、主権者が法的に制限されるという事態が、あらゆる法的なルールは主権者によって意図的に設定されたものであるとする、法の主権者意志説を、真っ向から覆すものであることを確認しておきたい。 すなわち、主権者の行為を(法的に)構成するルールの存在は、主権者の無制限を帰結する法の主権者意志説とは、決して両立し得ないのである。 言い換えれば、法の主権者意志説に現れた主体主義あるいは個体主義は、主体あるいは個体それ自体を構成するルールの存在によって、その理論的な貫徹を、阻止されざるを得ないのである。 このような、主権者の行為を制するルールを、ハイエクは、(法的)ルールが(法的)ルールとして妥当するために充たすべき一般的な条件についての、世間一般の意見(opinion)と呼んでいる。 言い換えれば、主権者は、世間一般の意見によって制限されるのである。 ハイエクの言う、世間一般の意見は、世間一般の意志(will)とは明確に区別される、かなり独特な概念である。 すなわち、世間一般の意志が、たとえばルールの可否をめぐる投票などによって、意識的に表出されるのに対して、世間一般の意見は、主権者の設定したルールがルールとして実際に従われるか否かによって、遂行的にのみ示されるのである。 従って、主権者の制定する法は、世間一般の意見によって拒否されない限りにおいて、法足り得ることになる。 今日においては、多数者大衆が主権者なのであるから、世間一般の意志と主権者の意志は一致していると考えてよい。 この場合、世間一般の意志によって設定されたルールと言えども、世間一般の意見によって拒否されるのであれば、ルールとしては発効し得ないことになる。 すなわち、世間一般の意見は、世間一般の意志をも制限し得るのである。 この意味において、ハイエクのいう世間一般の意見は、アナール学派の言う集合的心性(mentalite)に、かなり近しい概念である。 何故ならば、いずれも、行為を規範的に限定し得るとともに、自らは遂行的にのみ存在し得る、集合的な精神の秩序に外ならないからである。 それでは、本節の前半で残して措いた問題を取り上げることにしよう。 すなわち、行為の持続的な遂行の意図せざる結果として生成されるルールが、何故に、行為を先験的に構成する規範たり得るのか、という問題である。 あるいは、この問題を、自らに従う行為の持続的に遂行されていること以外には、いかなる根拠をも持ち得ないルールが、何故に、行為の社会的に発効し得るか否かを決定する根拠たり得るのか、と言い換えてもよい。 すなわち、この問いは、行為の発効し得るか否かを決定する根拠それ自身が、行為の結果として生成されるということに、果たして何の矛盾も生じ得ないのか、という疑いから発せられているのである。 このような疑いには、充分な根拠がある。 何故ならば、もし行為の発効し得るか否かを決定する根拠が、行為自らによって与えられるとするならば、行為の有効/無効を決定するのは行為自らである、という事態が生じ得るからである。 たとえば、「私の決定(行為)は無効である」と私は決定(行為)する、といった事態が生じ得るのである。 このような事態は、明らかにパラドックスを孕んでいる。 すなわち、もし、「私の決定は無効である」という私の決定が有効であるとするならば、私の決定は無効であることになり、逆に、「私の決定は無効である」という私の決定が無効であるとするならば、私の決定は有効であることになる。 従って、このような事態においては、私の決定の発効し得るか否かを決定することは、論理的に不可能となるのである。 このパラドックスは、いわゆる自己言及(self-reference)のパラドックスと同型のパラドックスとなっている。 すなわち、自己の決定の発効し得るか否かは、自己自身によっては決定不能であるという事態は、自己言及による意味の決定不能性と同型の構造を持っているのである。 従って、行為の有効/無効は、行為自らによっては決定し得ないのであるから、行為の発効し得るか否かを決定する根拠が、行為自らによって与えられるような状況においては、行為の社会的な効力など、全く決定不能であるように考えられる。 すなわち、行為の社会的な発効の条件を規定するルールが、行為の持続的な遂行の結果として生成されるという状況においては、行為の社会的に発効し得るか否かは、ついに決定し得ないように思われるのである。 しかし、このような帰結が導かれるように見えるのは、実は、行為の発効し得るか否かを決定するルールを、行為自らによって意図的に設定(決定)し得ると考えているからに外ならない。 すなわち、行為の発効条件を規定するルールを、決定や制御や言及やといった行為の意識的な対象となり得ると考えるが故に、行為の発効し得るか否かを、行為自らが決定するという事態が生じているように見えるのである。 言い換えれば、ルールが行為の意識的な対象として(意図的に)設定されるという事態であると見なすが故に、行為の有効/無効を行為自らが決定しているように見えるのである。 従って、行為の有効/無効を決定するルールが、行為の結果として生成されるにも拘わらず、行為によって意図的には設定(決定)し得ない事態であると考えるならば、この問題(自己言及の非決定性)は、ひとまず解消することになる。 すなわち、行為の社会的な効力を決定するルールが、行為の持続的な遂行の結果であるにも拘わらず、行為の意識的な対象とはなり得ないという意味において暗黙的であるならば、行為の発効し得るか否かは、ひとまず決定可能となるのである。 言い換えれば、ルールが、行為の有効/無効を、とりあえず決定し得るとするならば、それは、ルールが、暗黙的であるからに外ならないのである。 以上の議論から、遂行的に生成されるルールが、にも拘わらず、行為を規範的に拘束し得るとするならば、それは、ルールの暗黙的である場合に限られることが明らかになった。 言い換えれば、行為が、自らを行為として発効させるために、何等かのルールに依存せねばならぬとするならば、そのようなルールは、暗黙的たらざるを得ないのである。 ここで注意すべきは、この、行為が自らを発効させるために、何等かのルールに依存せねばならぬ、という(次々節で行為の文脈依存性と呼ばれることになる)命題は、ここでは単に仮定されているだけなのであって、何の論証も為されている訳ではないということである。 すなわち、ここでは、行為が自らの発効をルールに依存していることが、とりあえず仮定されるならば、そのようなルールは暗黙的であることが帰結される、という議論をしているのである。 従って、行為は自らの発効をルールに依存しているのか否かという問いが、また改めて問われねばならない。 しかし、この問いを問うことは、次節以下に委ねたい。 ここでさらに注意すべきは、行為の発効を根拠付けるルールが、たとえ暗黙的であったとしても、いわゆる自己言及の非決定性が、完全に解消する訳ではないということである。 なるほど、行為の有効/無効を決定するルールが、行為自らの言及(決定)対象とはなり得ないとすることによって、行為の発効し得るか否かは、確かに決定可能となった。 しかし、そのことによって、ルールそれ自体は、自らの有効性あるいは妥当性を決定し得る、いかなる根拠をも与えられるわけではない。 何故ならば、ルールそれ自体の妥当性を、(行為ではなく)ルールに根拠を置いて決定することは、明らかに自己言及のパラドックスを引き起こすからである。 従って、ルールそれ自体の妥当し得るか否かは、依然として決定不能なのである。 言い換えれば、行為の有効/無効を決定するルールが暗黙的であるとすることによって、行為についての(自己言及の)非決定性は、確かに解消されたのであるが、それは、(自己言及の)非決定性を、ルールについてのそれに、ただ先送りしたに過ぎないのである。 あるいは、ルールが暗黙的であるということは、取りも直さず、ルールそれ自体の妥当性が決定不能であるということに外ならない、と言い換えてもよい。 すなわち、ルールの暗黙性とはその自己言及性に外ならないのである。 いずれにせよ、自己言及の非決定性は、行為についてのそれからルールについてのそれへと、そのレベルを変更しただけであって、パラドックスそのものは、少しも解消していない。 自己言及性は、(次々節に述べる文脈依存性と共に)人間とその社会にとって、ついに逃れ得ない、言わば運命的な特質なのである。 ◆2.内的視点 - ハート -ルールが存在するということは、取りも直さず、行為に何等かの秩序あるいは規則性が見い出されるということに外ならなかった。
前章で述べたように、ハートは、この、行為に何等かの規則性を見い出す視点を、ルールに対する外的視点と呼んだのであった。 また、ハートは、ルールの、行為に規則性が存在する事態として捉えられる側面を、その外的側面と呼んだのであった。 しかし、ハートによれば、ルールがルールとして存在し得るためには、行為に規則性が見い出される以外に、ルールが行為の当否を判定する根拠あるいは理由として、(行為主体に)受け容れられておらねばならないのである。 言い換えれば、ハートの言うルールは、その外的側面が観察される以外に、行為の妥当性を評価する規準となる、その内的側面が確認されて始めて、ルールとして存在し得るのである。 ルールは、そのルールには従わない、言い換えれば、そのルールの構成する社会的なゲームには内属しない外的視点によって、行為に規則性が存在する事実として観察されるその外的側面と、そのルールに従う、言い換えれば、そのルールの構成する社会的なゲームに内属する内的視点によって、行為の妥当性を判定する当為として受容されるその内的側面と言う、二つの側面が合わさって始めてルールと呼び得る。 すなわち、ハートによるルールの概念は、ルールの事実として従われていることが観察されることのみならず、ルールの当為として従われるべきことが受容されていることをも、その構成要件とするのである。 この、事実としてのルール、すなわち、ルールの外的側面と、当為としてのルール、すなわち、ルールの内的側面とは、いずれか一方から他方が導き出されるといった関係にはなく、ルールという一つの事態を、外的/内的という二つの視点から見ることによって現れた、その二つの側面なのである。 従って、その外的視点から見るならば、ルールは、それが従われているという単なる事実に過ぎず、従うべき当為では些かもあり得ないのに対して、その内的視点から見るならば、それは、自らの従うべき当為なのであって、それが事実として従われているか否かは、規範逸脱の事実認定においてのみ問題とされるのである。 いずれにせよ、ルールが、行為の当否を判定する根拠あるいは理由となり得るのは、その内的視点から見た場合なのである。 ところで、行為の妥当性を判定する根拠となる内的側面を持つ、ルールそれ自体の妥当性は、いかなる根拠によって正当化されるのであろうか。 法的ルールの場合、前章で述べたように、あらゆる法体系には、それに属する総てのルールの妥当性を根拠付け得る承認のルールが、常に存在しているというのが、この問いに対するハートの答えであった。 すなわち、法体系を構成する(一次)ルールは、承認の(二次)ルールによって、その妥当性を理由付け得るのである。 しかし、ルールの妥当性の、このような正当化の方法は、無限後退に陥らない限り、どこかで断念されざるを得ない。 言い換えれば、無限後退を避けるためには、他のあらゆるルールを正当化し得るが、自らは如何なるルールによっても正当化され得ない承認のルールが、どこかで要請されざるを得ないのである。 前章で述べたように、ハートは、このような承認のルールを、究極の承認のルールと呼んだのであった。 すなわち、究極の承認のルールは、そのルールの妥当性を根拠付け得る如何なるルールも存在し得ないという意味において、究極的なのである。 究極の承認のルール、あるいは、法体系には属さない一般のルールは、その妥当性を判定し得る如何なる根拠も持ち得ない。 言い換えれば、このようなルールは、それ自体を対象として規範的に評価し得る、如何なる内的視点をも持ち得ないのである。 従って、このようなルールそれ自体を対象とし得るのは、それが遂行的に存在しているという事態を認識し得る、その外的視点以外にはあり得ない。 すなわち、このようなルールは、(それ自体を対象として見れば)ただ事実として遂行されているという事態以外ではあり得ないのである。 しかし、このようなルールの規範性と遂行性との関係については、前章に詳しく検討したので、ここでは触れない。 むしろ、本節では、ルールわけても究極の承認のルールに従う内的視点の存在が、ハートの批判する法の主権者意志説に対して、果たして如何なる含意を持ち得るのかを問題としたい。 あらゆる法は、主権者の意図的に設定したものである、さらに、その論理的な帰結として、そのような主権者は、法的に無制限な主体である、これが法の主権者意志説であった。 これに対して、究極の承認のルールは、あらゆる法に、それが法として妥当するための根拠を与えるルールである。 従って、たとえば、主権者の制定した法は妥当するといったルールもまた、究極の承認のルールであり得る。 因みに、ある法が主権者によって制定されたものであるか否かを、その法の妥当性を判定する究極的な規準とする法体系は、近代国家においてはむしろ通例である。 しかし、この場合、主権者は決して無制限ではあり得ない。 このような法体系においては、主権者は、主権者の設定する法は有効であるという、究極の承認のルールを根拠として始めて、自らの設定する法の妥当性を理由付け得るのであり、さらに、そもそも自らの主権者たり得た根拠それ自体も、主権者たるの要件を規定する、究極の承認のルールを待って始めて与えられるのである。 言い換えれば、主権者は、自らの行為の法的な効力のみならず、自らの存在それ自体をも、究極の承認のルールによって与えられているのである。 すなわち、究極の承認のルールの存在する法体系においては、主権者はついに無制限ではあり得ず、究極の承認のルールに従う、その内的視点を取らざるを得ないのである。 あるいは、このことを、主権者によって制定された法が、法として妥当し得るか否かは、究極の承認のルールに依存する、と言い換えてもよい。 すなわち、主権者による法の制定という行為が、行為として(法的に)発効し得るか否かは、究極の承認のルールという文脈に依存しているのである。 この命題は次節に述べる(発語内)行為の文脈依存(context-dependence)性という命題と、全く同型の構造を持っている。 たとえば、主権者の「私は~を法とする」という発話が、法を制定する行為として発効し得る(~を法として妥当せしめる)ためには、立法の権限が主権者にあらかじめ与えられていることや、立法の発話が適切な手続きに従って為されていることなどといった、様々な条件が充たされておらねばならない。 次節では、このような条件を、(発話内)行為の文脈と呼ぶことにするが、究極の承認のルールとは、まさに、この意味における(法の妥当性の承認という)行為の文脈に外ならないのである。 すなわち、主権者による法の制定という行為が、行為として(法的な)行為として発効し得るか否かは、究極の承認のルールという文脈に依存している、という事態は、発話という行為が、(社会的な)行為として発効し得るか否かは、その文脈に依存している、という事態(発語内行為の文脈依存性)の、法領域における現れとして捉え得るのである (発語内)行為は、その主観的な意図とは独立に、何等かの文脈が与えられて始めて、自らの社会的な効力を確定し得る。(この命題については次節で詳しく検討する。) 同様に、主権者による法の制定は、その主観的な意図とは独立に、究極の承認のルールが与えられて始めて、自らの法的な効力を確定し得る。 すなわち、主権者の行為の(法的な)効力は、その主観的な意志ではなく、その社会的な文脈に規定され、あるいは、制限されているのである。 従って、究極の承認のルールの存在は、あらゆる法を主権者の意図的に設定したものであると考える、法の主権者意志説を、真っ向から否定することになる。 何故ならば、究極の承認のルールの存在は、法の主権者意志説の論理的帰結である、主権者の法的無制限という事態と、全く両立し得ないからである。 すなわち、法の主権者意志説に従えば、第一章で見たように、主権者の法的無制限を帰結せざるを得ないのであるが、究極の承認のルールの存在する法体系においては、主権者は法的に無制限ではあり得ないのであって、その必要条件を否定される法の主権者意志説は、棄却されざるを得ないのである。 言い換えれば、主権者の行為が、究極の承認のルールに依存せざるを得ないとするならば、法を主権者の意志の表出としてのみ捉えることは、もはや不可能となるのである。 また、法の主権者意志説においては、あらゆる法は、究極的には主権者によって意図的に設定されたと考えるのであるから、法が、法として妥当し得る根拠もまた、それが、究極的には主権者によって意図的に設定されたという事実以外にはあり得ない。 すなわち、法の主権者意志説は、法の究極的な制定目的が主権者の意志にあると主張するのみならず、法の究極的な妥当根拠もまた主権者の意志にあると主張するのである。 このような主権者は、いかなる法によっても決して制限され得ず、従って、如何なる法体系の内部においても、その(主権者たる)根拠を持ち得ない存在である。 言い換えれば、このような主権者は、あらゆる法体系の外部にある、いわば超法規的あるいは政治的な存在なのである。 従って、法の主権者意志説は、法の究極的な妥当根拠を、法によっては制限も根拠も与えられ得ない、超法規的あるいは政治的な存在である主権者の意志に、委ねざるを得ないことになる。 これに対して、究極の承認のルールは、言うまでもなく、法の究極的な妥当根拠となる、法的なルールである。 従って、究極の承認のルールが存在しさえすれば、法を究極的に妥当させる、法的に無制限な主権者の存在など、些かも必要とされないことになる。 言い換えれば、たとえ法の主権者意志説を取らないとしても、究極の承認のルールさえ存在するならば、法体系の理解にとって、些かの支障もないのである。 従って、法の主権者意志説は、究極の承認のルールの存在と両立し得ないばかりではなく、それが全くの誤りであるか否かはいざ知らず、究極の承認のルールが存在しさえするならば、少なくとも不必要な議論なのである。 しかし、究極の承認のルールそれ自体は、いかなる法的な根拠も持ち得ない、いわば法体系の外部に開かれているルールであった。 このような究極の承認のルールの存在と、法的な根拠を持ち得ない、言わば超法規的な主権者の存在とは、一体どこが違うというのであろうか。 そもそも、法の妥当し得るか否かを究極的に確定するためには、法によってはついに根拠付け得ない存在が、不可避的に要請されるのではなかったのか。 この問いに答えるためには、主権者の行為は究極の承認のルールに依存している、という命題の成立していることが、まず確認されねばならない。 すなわち、主権者の行為は、その当否を、究極の承認のルールによって始めて決定され得る、という事態である。 それでは、その逆である、究極の承認のルールは、その妥当根拠を、主権者の行為によって始めて付与され得る、という事態は、果たして成立し得るのであろうか。 この問いに対して、もし、究極の承認のルールにその妥当根拠を与え得る主権者の行為があるとするならば、その主権者の行為に妥当根拠を与える究極の承認のルールが存在することになり、究極の承認のルールの究極性に矛盾する、といった答えを与えることも、確かに適切である。 しかし、ここでは、この問題を、別の角度から検討してみたい。 すなわち、この問題を、たとえば、「私(主権者)の制定する法は妥当しない」という法(究極の承認のルール)を私(主権者)は制定する、といった自己言及の問題として捉えるのである。 このように問題を捉えてみるならば、究極の承認のルールが、主権者の、(たとえば法の制定という)行為によってその妥当根拠を与えられる、という主張は、まさに、前節に述べた、自己言及の非決定性を帰結することが明らかとなろう。 従って、前節の議論を援用すれば、究極の承認のルールは、主権者の行為の意図的な対象とはなり得ないという意味において、暗黙的であることが結論されるのである。 すなわち、究極の承認のルールは、主権者の意図的な行為によっては、その妥当根拠をついに与え得ない、根拠付け不能な事態なのである。 しかし、(承認という)行為の持続的な遂行においてのみ存在し得る、遂行的な事態としての究極の承認のルールが、行為の意図的な対象とはなり得ないという意味において、暗黙的な事態でもあることは、既に前章において詳しく見た処である。 むしろ、本章において見るべきは、遂行的な事態としての究極の承認のルールが、(承認という)行為の法的に発効し得るか否かを決定するという意味において、まさに、規範的な事態でもあることなのである。 すなわち、究極の承認のルールは、行為の社会的(法的)な効力を、その主観的な意図とは独立に決定する、まさしく慣習的な文脈に外ならないのである。 ところで、究極の承認のルールは、人々の行為の当否を判定する根拠となる(一次)ルールそれ自体の、妥当性を判定する根拠となる(二次)ルールであった。 従って、ある行為の当否判定において、その根拠となるルールをめぐる紛争の生じた場合に、究極の承認のルールは、いかなるルールが従われるべきかを決定することのよって、その紛争を常に解決し得ることになる。 たとえば、ある行為の当否について、現行のルールがいかようにも解釈し得る場合、究極の承認のルールは、ある一つの解釈をルールとして妥当させる根拠を与え得るのである。 すなわち、現行のルールに、行為の当否について、何等かの不確定な部分が存在する場合、究極の承認のルールは、その部分を確定することによって、事実上新たなルールを設定する根拠を与え得るのである。 ハートは、ルールがこのように不確定な部分を常に有していることを、ルールの開かれた構造(open texture of rule)と呼んでいる。 従って、究極の承認のルールは、(一次)ルールの開かれた構造を、常に閉じ得る装置であるとも言い得ることになる。 しかし、究極の承認のルールもルールである以上、ルールの開かれた構造の例外ではあり得ない筈である。 すなわち、究極の承認のルールもまた、何等かの不確定な部分を常に有しているのである。 そこでは、究極の承認のルールの不確定な部分は、如何にして確定されるのであろうか。 たとえば、そのような確定が、いずれかの主体によって意図的に遂行されるとしてみよう。 この場合、究極の承認のルールの不確定な部分を確定する行為は、究極の承認のルールの(部分的な)不在という場面において、それを意図的に設定する行為となってはいないか。 言い換えれば、そのような行為の主体は、究極の承認のルールによっては制限され得ない、無制限な主権者と呼び得る存在ではないか。 すなわち、究極の承認のルールの開かれた構造を閉じるためには、つまりところ無制限な主権者の存在が要請されるのではあいか。 究極の承認のルールの開かれた構造は、このような一連の疑問を当然に生み出すのである。 しかし、究極の承認のルールが、たとえ開かれた構造を持っているとしても、そのことから直ちに、究極の承認のルールそれ自体を設定する、無制限な主権者が要請されるとは限らない。 究極の承認のルールが不確定なのは、あくまでその一部分なのであって、残りの大部分においては、何が妥当なルールであるかの規準は、差し当たり充分に確定しているのである。 ハートは、ルールの不確定な部分を、その不確定な半影部分(penumbra of uncertainty)と呼び、また、ルールの確定している部分を、その確定した核心部分(core of certainty)と呼んでいる。 究極の承認のルールにも、このような半影部分と核心部分の両方が備わっているのである。 従って、究極の承認のルールの不確定な半影部分を確定する行為は、残りの確定した核心部分を不問の前提にしていると考えてよい。 すなわち、そのような行為は、その対象とはならない部分の究極の承認のルールに従っている、という意味において、決して無制限ではあり得ないのである。 言い換えれば、究極の承認のルールの開かれた構造を閉じる行為は、あくまで究極の承認のルールの一部分のみを対象とするのであって、その全体を対象とすることは決してあり得ず、従って、究極の承認のルールに、たとえ開かれた構造が存在したとしても、それを閉じるために、無制限な主権者が要請される必要は、必ずしもない訳である。 しかし、それにしても、究極の承認のルールの不確定な半影部分を確定する行為は、極めて微妙な行為である。 それは、自らの従うルールの一部分を、自らの対象として言及する行為に外ならない。 このような行為が、自らの従うルールの全体に対してはついに不可能であることは、前章において、ルールの暗黙性として詳しく検討した処である。 すなわち、自らの従うルールの全体を、自らが意図的に変更することは不可能なのである。 しかし、ここで述べられたことは、たとえ自らの従うルールであっても、その一部分であるならば、自らの意図的に変更することが必ずしも不可能ではない、ということである。 ルールの一部分に変更が要請される場合とは、新たに生じた問題に対して、現行のルールが確定した解答を与えられない場合なのであるから、ルールの一部分が変更可能であることは、新たな状況に対するルールの適応のためには、むしろ必要でさえある。 しかし、自らの従うルールを、たとえ部分的であったとしても、自らが意図的に変更する行為は、依然として、かなり微妙な行為であることに変わりはない。 このような行為は、果たして、如何なる根拠あるいは規準によって、新たなルールを生成し得るのか、あるいは、このような行為の意図と、結果として生成されるルールとの間には、(行為の意図が達成されることは全くあり得ないが)果たして、如何なる関係があるのか、といった様々な疑問がすぐにでも涌いてくる。 これらの問題は、実のところ、前章で述べた、ハイエクの言う整合性の原理の問題と、全く同型の構造を持っている。 すなわち、これらの問題に対する回答こそが、まさに、ハイエクの言う整合性の原理に外ならないのである。 ◆3.発語内の力 - オースティン -言葉を発する、すなわち発話するという行為は、既に見たように、それ自身とは区別される社会的な行為の遂行でもある。
すなわち、発話行為(言語行為)は、発語行為の遂行であるとともに、発語内行為の遂行でもある。 しかし、あらゆる発話行為が、常に社会的な行為としての効力を持つ訳ではない。 発話行為が、何等かの発語内行為の有効適切な遂行であり得るためには、ある慣習的なルールを充たさねばならないのである。 それでは、発話行為を、社会的な行為として発効させる慣習的なルールとは、いかなるルールであるのか。 また、そのようなルールには、いかなる分類があり得るのか。 ところで、ある発話行為が、そのようなルールから見て、たとえ不適切であったとしても、それが何等かの社会的な結果を発生させ得ることまで否定される訳ではない。 すなわち、発話行為は、慣習的なルールに従っているか否かに拘わらず、自らを原因とする何等かの社会的な結果を発生させ得るのである。 このような発話行為の社会的な結果と、その社会的な効力とは、果たして、如何なる関係にあるのか。 言い換えれば、発話によって社会的な結果を達成する発語媒介行為と、発話が社会的な効力を獲得する発語内行為とは、どのように区別され得るのか。 これら一連の問いが、本節で問われる問いに外ならない。 これらの問いに答えることが、取りも直さず、言語における主観主義としての表出主義に対する、決定的な論駁を準備するのである。 オースティンによれば、発話行為が、それ自身とは区別される何等かの社会的な行為として発効する条件は、大きく三つに分類される。 その第一は、ある発話が、何等かの社会的な効力を持つ行為の遂行であるために充たすべき、慣習的な手続きあるいはルールが存在していることである。 たとえば、「~せよ」という発話が、従うべき命令として社会的な効力を持ち得るのは、そこに何等かの手続きに根拠付けられた命令権限が存在し、そのような命令権限を持つ者によって、その発話が遂行される場合に限られる、といった具合である。 従って、「~せよ」という発話が、命令権限の存在しない領域において、あるいは、命令権限のない者によって、遂行されたとしたならば、そのような発話は、命令としての社会的な効力を持ち得ない。 すなわち、何等かの手続きあるいはルールがその背景に存在しない発話行為は、それ自身とは区別される社会的な行為としては無効あるいは不適切なのである。 その第二は、発話を社会的な効力を持つ行為の遂行とするための手続きが、正しくかつ完全に従われることである。 たとえ、発話を社会的な行為として発効させる手続きが、疑いもなく存在していたとしても、それが正しくかつ完全に従わないような発話は、(それ自身とは区別される)社会的な行為としては無効あるいは不適切なのである。 そもそも、ルールが存在するということは、それに従っているか否かによって、行為の当否あるいは適切/不適切が判定され得るということなのであるから、ルールの従われていることを要請する、この第二の条件は、(第一の条件が成り立っているならば)当然と言えばあまりに当然な条件である。 しかし、この条件を敢えて独立させた背景には、司法的な判断に代表される判定宣告型の発語内行為(後述する)が、主としてこの条件の成否に拘わる社会的な行為であることへの配慮があったと思われる。 その第三は、発話がある手続きを充たすことによって社会的な効力を獲得したとき、何等かの後続する行為が義務付けられる場合、そのような行為が引き続き遂行されることである。 たとえば、「私は~を約束します」という発話が、約束を巡って存在するルールに正しくかつ完全に従うことによって、約束という社会的な行為として発効するとき、そこには、約束した行為を引き続いて遂行する責務が生じることになる。 もし、このように義務付けられた後続行為が遂行されないとするならば、「私は~を約束します」という発話は、約束という社会的な行為の遂行としては不適切である。 もちろん、このような発話は、約束という社会的な行為を発効させはする。 すなわち、このような発話は、前期の二つの条件を充たすことによって社会的な行為としての約束を成立させはする。 従って、このような発話は、社会的な行為として無効である訳ではない。 しかし、義務付けられた後続行為が遂行されないとするならば、約束という社会的な行為は、確かに成立してはいるが、完了していない、あるいは履行されてはいない。 このように未完了あるいは不履行となる約束を成立させる発話は、無効ではないが、不適切あるいは義務違反なのである。 すなわち、義務付けられた後続行為の遂行されないような行為を発効させる発話は、社会的な行為の遂行としては不適切なのである。 さらに、オースティンは、この第三の条件に、後続行為の遂行が、発話主体によって、主観的に意図されていることをも含めている。 たとえば、約束の発話が為される場合、約束の履行が発話主体によって主観的に意図されていることが、その発話が社会的な行為として適切であるための必要条件になる、と言うのである。 しかし、後続行為が事実として遂行されることと、それが主観的に意図されることとの間には、厳密に区別されるべき、重大な相違が存在する。 すなわち、行為の事実的な遂行は、たとえば外的視点から観察可能であるが、行為の主観的な意図は、行為と独立には観察不能であるという相違である。 行為の主観的な意図は、観察される行為の原因として、その背後に仮設される存在なのである。 このような発話主体の意図は、発話が社会的な行為の適切な遂行であるための条件に対して、果たして、どこまで相関的なのであろうか。 むしろ、発話主体の意図の如何に拘わらず、後続行為が事実として遂行されるのであれば、発話は社会的な行為の適切な遂行となるのではないか。 これらの問題は、発話の慣習的なルールに基づく効力と、その主観的に意図された結果との区別と密接に関係している。 従って、これらの問題は、発語内行為と発語媒介行為との区別を検討する過程において、始めてその解答を見い出し得ると思われる。 そのために、発語内行為の社会的な効力が、慣習的なルールに依存しているという事態を、また別の角度から検討してみよう。 たとえば、「私は陳謝します」という発語を伴う(後に態度表明型と分類される)発語内行為を考えてみる。 「私は陳謝します」という発語が、陳謝という社会的な行為として発効するためには、前述の三条件に分類される、様々な条件が充たされていなければならない。 ととえば、第一の条件に分類される、私の行為が(陳謝の)相手に何等かの不利益を与えたという事実の存在、また、その不利益が私の行為によっては回避し得ない不可抗力によるものではないこと、さらに、相手に不利益を与えたとしてもなお私の行為を正当化し得る理由のないこと、といった様々な条件が充たされて始めて、「私は陳謝します」という発語は、陳謝という社会的な行為として発効するのである。 これらの条件のどれか一つ、あるいはその幾つかが充たされていない場合、「私は陳謝します」という発語は、社会的な行為としては、無効あるいは不適切となる。 たとえば、相手に何の不利益も与えていないのに、「私は陳謝します」と繰り返すことは、滑稽な錯誤でなければ、不幸な病気である。 言い換えれば、「私は陳謝します」という発語が、社会的な効力を有するためには、発語をめぐる、発語自身とは独立な状況の、既述のような条件を充たしていることが、必要不可欠なのである。 すなわち、発語内行為の社会的な効力は、それに伴う発語行為の遂行される状況あるいは文脈に、決定的に依存しているのである。 従って、発語内行為は、それをめぐる状況あるいは文脈を参照することなしには、その効力を全く確定し得ないことになる。 この事態を、発語内行為の文脈依存性と呼ぶことにしよう。 発語内行為は、自らの内属する文脈が与えられて始めて、その効力を決定し得るのである。 すなわち、発語内行為の社会的な効力が、慣習的なルールに依存しているというオースティンの指摘は、取りも直さず、発語内行為は文脈依存的であるという事態の発見に外ならないのである。 ここで留意すべきは、発語内行為が、社会的に発効するための条件には、当の行為の主観的な意図は、必ずしも含まれていないということである。 たとえば、「私は陳謝します」という発語が、社会的な行為として発効するためには、陳謝の主観的な意図は、必ずしも前提されないといった具合である。 すなわち、「私は陳謝します」という発語が、既述のような条件を充たす状況あるいは文脈において遂行されているのであれば、たとえ陳謝の主観的な意図が全く存在しないとしても、陳謝という社会的な行為は成立し得るのである。 あるいは、「私は陳謝します」という発語が、たとえば、私の行為によって相手が如何なる不利益も被っていない状況において、遂行されているとするならば、それが陳謝の主観的な意図に満ち溢れているものであったとしても、陳謝という社会的な行為は決して発効し得ないのである。 すなわち、発語内行為の効力は、それに伴う発語行為が遂行される文脈にのみ依存しているのであって、その主観的な意図からは全く独立しているのである。 陳謝のような、個体の主観的な情緒の表出であると普通は考えられている発話が、その主観的な情緒とは独立に、その社会的な文脈にのみ依存して、自らの効力を確定し得るという事態は、一見、意外に見えよう。 しかし、文脈依存的な発語内行為と、言わば意図あるいは情緒表出的な発語媒介行為とが、共に何等かの社会的な効果を発生させるにも拘わらず、互いに区別されねばならないのは、まさに、このような事態が見い出されるからに外ならないのである。 発語内行為と発語行為との関係については、前章に詳しく検討した。 そこで明らかになったことは、陳述の発話といった事実確認的発話にも、前述の三条件を充たしているか否かによって、その適切性を判定し得る発語内行為の位相が存在すること、また、命令や判定や約束やの発話といった行為遂行的発話と言えども、何等かの事態を指示するという意味において、発語行為の位相が存在することであった。 すなわち、発語内行為と発語行為は、同時に一つの発話の内に存在し得る、発話行為(言語行為)の二つの位相なのである。 この意味においては、発語媒介行為もまた、発語内行為や発語行為やと同様の、発話行為の一つの位相に外ならない。 あらゆる発話は、慣習的に根拠付けられた効力を発揮する行為(発語内行為)の遂行であり、かつ、客観的に対象化された事態を指示する行為(発語行為)の遂行である、と同時に、主観的に意図された結果を達成する行為(発語媒介行為)の遂行でもあり得るのである。 それでは、発語内行為と発語媒介行為とは、如何にして区別されるのであろうか。 両者が、何等かの社会的な効果を発生させる行為である、という点においては共通するにも拘わらず、前者が慣習的なルールによって根拠付けられる行為であるのに対して、後者はそうではない、という点において区別されるということは既に述べた。 オースティン自身は、両者の区別について、実はこれ以上立ち入った検討を加えてはいない。 しかし、このままでは、社会的な効果を発生させる発話行為の内で、慣習的なルールによって根拠付けられる部分以外の総ての残余が、発語媒介行為であるということになる。 これでは、ある発話が、その意図の如何に拘わらず、言わば偶然に何等かの社会的な結果をもたらす場合でも、それは発語媒介行為の概念に包摂されることになり、概念として広きに失すると思われる。 むしろ、発語媒介行為は、発話主体によって主観的に意図された何等かの社会的な結果を、効果的に達成する手段として遂行される発話行為を指示する概念として、より限定的に使用されるべきであると思われる。 すなわち、発語内行為と発語媒介行為とを区別するメルクマールは、前者の社会的な効力を発効させる根拠が、慣習的なルールであるのに対して、後者の社会的な結果を発生させる原因は、(発話主体の)主観的な意図であるという点に求められると考えるのである。 言い換えれば、発語内行為の純粋型が、その慣習的な適切性の問われる、行為の遂行(行為遂行的発話)であり、発語行為の純粋型が、その客観的な真理性の問われる、事態の記述(事実確認的発話)であるのに対して、発語媒介行為の純粋型は、その主観的な誠実性の問われる意図の表出(言わば意図あるいは情緒表出的発話か)であると分類してみるのである。 このように考えてみるならば、あらゆる発話を、発語主体の主観的な意図や情緒や目的やの表出に帰着し尽くし得るとする、言語の表出主義が、如何なる限界をもつ主張であるかが明らかとなる。 すなわち、表出主義は、発話行為の総てを、発語媒介行為の位相に還元し尽くし得るとする主張なのである。 しかし、これまで述べてきたこおから明らかなように、発話行為は、発語行為と発語媒介行為の位相の直和には、ついに分割され得ない。 発話行為には、発語内行為の位相が、紛れもなく存在するのである。 すなわち、記述主義という、いわば言語の物理主義的な理解も、また、表出主義という、いわば言語の心理主義的な理解も、慣習的なルールに従った社会的な行為の遂行としての言語の位相を、ついに捉え切れないのである。 言い換えれば、客観的な事実でもなく、あるいは、主観的な情緒でもなく、ただ、社会的な文脈にのみ依存して、その当否を決定される言語行為の位相の、確かに存在し得ることが、捉え切られねばならないのである。 このように、発語行為とも発語媒介行為とも区別される発語内行為は、それ自身幾つかの類型に区分し得る。 言い換えれば、発話行為の発揮し得る慣習的な効力は、幾つかの種類に分割し得る。 オースティンは、この発話行為の発揮し得る慣習的な効力を、発語内の力(illocutionary forces)と呼び、その分類を、発語内の力の分類と呼んでいる。 以下に見るように、発語内の力の分類は、本節の前半に述べた、発語内行為の適切性の条件の分類と、密接に関係しているとともに、一つの発話行為が、同時に三つの位相を持つという事態とも、深く拘わっているのである。 それでは、発話行為を、それが発揮する発語内の力の類型に対応させて、言い換えれば、それが遂行する発語内行為の類型に対応させて、以下に分類してみよう。 第一の類型は、権限行使型(exercitives)である。 これは、何等かの権能を行使する発話であり、たとえば、命令や許可の発話に代表される。 この類型が、発語内行為が適切であるための第一の条件である、(権能を付与する)ルールの存在という条件を、その発語内の力の根拠とすることは明らかであろう。 第二の類型は、行為拘束型(commissives)である。 これは、何等かの後続行為を義務付けられる発話であり、たとえば、約束や支持の発話に代表される。 この類型が、発語内行為が適切であるための第三の条件である、(義務付けられた)後続行為の遂行という条件を、その発語内の力の根拠とすることは言うまでもなかろう。 第三の類型は、判定宣告型(verdictives)である。 これは、事実的な証拠や規範的な理由といった根拠に基づいて、何等かの判断を述べる発話であり、たとえば、判定や評価の発話に代表される。 この類型は、証拠や理由の開示といった論理的な手続きの充足を、その判断の根拠とするという意味において、発語内行為が適切であるための第二の条件である、手続きの充足という条件を、その発語内の力の根拠としていると考えられる。 第四の類型は、言明解説型(expositives)である。 これは、陳述や記述の発話に代表される類型であるが、オースティン自身の定義は極めて曖昧である むしろ、この類型は、事実確認的発話に差し当たり分類される発話における、発語内行為としての位相を抽出したものである、と考えた方がよいのではないか。 すなわち、この類型は、事実確認的発話の慣習的な適切性が問われる場面を切り取ったものである、と考えられるのである。 第五の類型は、態度表明型(behabitives)である。 これは、発話主体の主観的な態度や情緒を表出する発話であり、たとえば、陳謝や祝福の発話に代表される。 しかし、この類型は、あくまで発話の持つ発話内の力の分類なのであるから、事実確認的発話や行為遂行的発話と同一平面上において対比される、情緒(あるいは意図)表出的発話それ自体ではあり得ない。 むしろ、この類型は、(発語媒介行為の純粋型である)情緒表出的発話に差し当たり分類される発話における、発語内行為としての位相を抽出したものである、と考えるべきではないか。 すなわち、この類型は、情緒表出的発話の慣習的な適切性が問われる場面を切り取ったものである、と考えられるのである。 |
| + | ... |
◆1.慣習あるいは《遂行的なるもの》近代産業を推進する中心的な価値態度としての産業主義や手段主義、あるいは、近代科学を招来した価値態度とされている実証主義や記述主義といった、一連の合理主義とも言うべき世界の捉え方と、近代民主政治あるいは近代主権国家を支持する価値態度としての民主主義や主権主義、さらには、近代的自我あるいは「内面的意識」を析出する価値態度としての情緒主義や表出主義といった、一連の個体主義とも言うべき世界の捉え方とを、同時に懐疑し得る立脚点として、我々は、自生的秩序やルール、あるいは言語行為といった、遂行的に生成される社会秩序の概念を定礎してきた。
本節では、この《遂行的なるもの》とも言うべき概念の持つポテンシャルを、改めて評価してみたい。 すなわち、《遂行的なるもの》が、合理主義や個体主義を含めた概念のシステムの中で、如何なる位置価を持ち得るかを、正確に測定してみたいのである。 まず、合理主義によれば、世界は、ここでは差し当たり人間とその社会は、理性による意識的な制御あるいは言及の対象として捉えられる。 すなわち、世界は、合理的に制御可能あるいは言及可能な客体として把握されるのである。 何等かの目的を達成するために、世界を効率的に制御せんとする産業主義や手段主義、あるいは、総ての発話の真偽を、それが言及する対象の存否によって決定し得るとする実証主義や記述主義が、この意味における合理主義を、その共通の前提としていることは言うまでもない。 しかし、世界を、わけても人間とその社会を、合理的な制御あるいは言及の対象として捉え得るとする態度は、飽くまで一つの価値態度に過ぎないのであって、世界と我々との関係が、この態度のみによって覆い尽くされる筈のないことは、容易に理解されよう。 もちろん、このような態度によって捉え得る世界が、全く存在しないと言う訳ではない。 ただ、そのような世界が、世界の総てである筈はないと言っているのである。 この合理主義によって捉えられる世界を、世界の一つの捉えられ方であることに留意して、ここでは、《世界Ⅰ》と呼ぶことにしよう。 すなわち、《世界Ⅰ》とは、合理的に制御可能あるいは言及可能な対象として捉えられる世界の謂である。 次に、個体主義によれば、世界は、わけても人間の行為とそれによって形成される社会は、行為を遂行する個体の主観的な意図や情緒や目的やに、還元あるいは帰属され尽くし得る事態として捉えられる。 すなわち、人間の行為とそれによって形成される社会は、その個体的な意図や情緒や目的やに還元可能あるいは帰属可能な事態として把握されるのである。 この意味における個体主義が、社会の全体的な意志決定は、その社会を構成する諸個人の合意あるいは主権者の意志に還元され得るし、また、されるべきだと考える、民主主義あるいは主権主義の前提となっていることは言うまでもない。 さらに、このような個体主義は、人間の行為を、その主観的な意図に帰属させて理解する、言い換えれば、人間の行為を、その内面的な意識の表出として解釈する、情緒主義あるいは表出主義の前提をなす世界の捉え方でもある。 すなわち、個体主義は、人間の行為を帰属させ得る場所として、それを遂行する個体の内面に、「自我」と呼ばれる何ものかを仮設し、そのような「自我」の表現として、人間の行為を解釈するのである。 しかし、世界を、あるいは少なくとも人間とその社会を、個体に内蔵された意図や情緒や目的やに、還元あるいは帰属させて捉え得るとする態度によっては、たとえ世界を人間とその社会に限定してみたとしても、世界と我々の関係の、ついに覆い尽くされる筈のないことも、また、少し考えれば明らかであろう。 個体主義も、また、世界の一つの捉え方に過ぎないのである。 この個体主義の態度によって捉えられる世界を、ここでは、《世界Ⅱ》と呼ぶことにしよう、すなわち、《世界Ⅱ》とは、個体的な意識に還元可能あるいは帰属可能な事態として捉えられる世界の謂である。 この合理主義と個体主義とは、人間の行為を、何ものかを目指す志向的な事態であると見なす志向主義の産み落とした、一卵性双生児であると考えられる。 何故ならば、志向主義は、人間の行為を、志向的な事態であると捉えることによって、人間の行為に拘わる世界を、志向のベクトルの吸い込み口である、志向される対象(客体)と、志向のベクトルの涌き出し口である、志向する意識(主体)とに、二分して把握するからである。 すなわち、志向主義は、世界を、合理的な制御あるいは言及という志向的な行為の対象と、その志向的な行為が還元あるいは帰属される個体的な意識とに、二元的に分割するのである。 言い換えれば、志向主義は、世界を、《世界Ⅰ》と《世界Ⅱ》とによって、完全に分割し尽くし得ると主張するのである。 志向主義のもたらす、このような主客二元論こそ、近代の産業主義や科学主義、あるいは民主主義や自我主義に通底する、《近代的なるもの》それ自体に外ならないのである。 従って、志向主義として特徴付けられる、このような《近代的なるもの》から見るならば、世界は、客観的(あるいは合理的に制御可能)な《世界Ⅰ》であるか、さもなくば、主観的(あるいは個体的に還元可能)な《世界Ⅱ》であるかのいずれかであり、また、そのいずれかしかあり得ないことになる。 しかし、世界は、本当に主客いずれかでしかあり得ないのか。 あるいは、行為は、全くの志向的な事態であり得るのか。 この問いに答えるためには、世界を、わけても人間とその社会を、遂行的な事態として捉える視点が、改めて導入されねばならない。 《遂行的なるもの》とは、行為遂行の累積的な帰結として生成される秩序の謂である。 すなわち、《遂行的なるもの》とは、行為自らの生成する秩序なのである。 人間とその社会を、この意味における《遂行的なるもの》として把握する態度は、《近代的なるもの》あるいは志向主義による人間と社会の捉え方を懐疑する、最も確かな立脚点となり得る。 すなわち、《遂行的なるもの》として捉えられる人間と社会は、合理的に制御可能(あるいは客観的)な《世界Ⅰ》でもあり得ず、かつ、個体的に還元可能(あるいは主観的)な《世界Ⅱ》でもあり得ない、世界の第三の可能性を示しているのである。 このような《遂行的なるもの》が、いかなる意味において、制御可能ではあり得ず、また、還元可能でもあり得ないかについては、続いて述べる。 ここでは、客観的でもなく、主観的でもない、遂行的な事態として捉えられる世界を、《世界Ⅲ》と呼ぶことにしよう。 人間の行為を、志向的な事態として把握する態度によっては、ついに捉え得ない人間と社会の在り方こそ、この《世界Ⅲ》という在り方に外ならない。 すなわち、《近代的なるもの》と真っ向から対立する人間と社会の在り方こそ、この《世界Ⅲ》に外ならないのである。 それでは、《世界Ⅲ》すなわち《遂行的なるもの》としての人間と社会は、何故に、合理的に制御可能な事態とも、さらには、個体的に還元可能な事態ともなり得ないのか。 あるいは、人間の行為は、如何なる意味において、志向的な事態ではあり得ないのか。 これらの問いが答えられねばならない。 《遂行的なるもの》は、個体の意図や情緒や目的やに還元あるいは帰属され得ず、むしろ、個体の行為が行為として発効するための根拠となるという意味において、規範的な事態である。 すなわち、《遂行的なるもの》は、行為自らによって生成される秩序であるにも拘わらず、その主観的な意図には、ついに還元不能あるいは帰属不能な事態なのである。 何故ならば、《遂行的なるもの》を生成する行為それ自体の、行為として発効し得るか否かは、その主観的な意図とは全く独立に、その社会的な文脈にのみ依存して決定されるからである。 すなわち、行為の文脈依存的であることとは、取りも直さず、行為の発効し得るか否かが、自らの生成する《遂行的なるもの》を根拠として決定されることに外ならない。 しかし、《遂行的なるもの》の還元不能性を帰結する、行為の文脈依存性という命題において、行為の依存する文脈それ自体が《遂行的なるもの》であるとするならば、そこには、何等かの循環論あるいは論理的なパラドックスをが発生するのではないか。 しかし、この問題の検討は、後段に委ねることにして、差し当たり、行為の依存する文脈それ自体は、行為と独立に与えられていると仮定して置くことにしたい。 行為は、何故に、その主観的な意図に還元あるいは帰属され得ない、文脈依存的な事態であるのか。 たとえば、陳謝という行為のように、主観的な意図の表出以外の何ものでもないと見なされる行為ですら、陳謝の行為として発効しうるためには、その主観的な意図とは全く独立な、幾つかの条件 - 自己の行為によって他者に損害が生じたという事実の存在、他者に損害を与えたとしてもなお自己の行為を正当化し得る理由(たとえば正当防衛など)の不在等々 - を充たさねばならない。 自分が相手に何の危害も加えていない場合や、相手の暴力を避けるため相手に触れた場合やに、陳謝の言葉を発する行為は、たとえ、それが陳謝の主観的な意図に充ち溢れたものであったとしても、滑稽な錯誤の行為であるか、さもなくば、卑屈な追従の行為である、と見なされるのが落ちなのであって、真摯な陳謝の行為としては、決して発効し得ないのである。 あるいは、むしろ、陳謝の主観的な意図そのものでさえ、陳謝という行為が、ある文脈の下で発効することによって始めて、その文脈に応じた内容を持つものとして確定されるといった、文脈依存的な事態なのであると言ってもよい。 すなわち、行為を遂行する個体の内面的な意識は、行為の遂行される文脈が与えられて始めて、その内容を決定し得るのである。 従って、行為は、その主観的な意図に帰属させて解釈し得る筈もなく、その社会的な文脈に依存させて始めて、その効力(あるいは「意味」)の何たるかを決定し得るのである。 ゆえに、行為とそれによって生成される秩序は、個体的に還元可能ではあり得ない。 すなわち、《遂行的なるもの》は、《世界Ⅱ》ではあり得ないのである。 それでは、《遂行的なるもの》は、《世界Ⅰ》であり得るのか。 《遂行的なるもの》は、合理的に制御あるいは言及し得る対象とは、ついになり得ないという意味において、暗黙的な事態である。 すなわち、《遂行的なるもの》は、行為自らによって生成される秩序であるにも拘わらず、その意識的な対象としては、制御不能あるいは言及不能な事態なのである。 何故ならば、《遂行的なるもの》とは、何等かの文脈あるいはルールに依存して、自らの発効し得る否かを決定される、行為の秩序に外ならないのであるから、その全体を対象として制御あるいは言及する行為は、自らの依存しているルールそれ自体をも、その対象として制御あるいは言及せざるを得ないことになる。 すなわち、《遂行的なるもの》を対象として制御あるいは言及せんとする行為は、自らを妥当させる根拠としてのルールそれ自体を、その対象とせざるを得ないという意味において、まさに自己組織(制御)あるいは自己言及の行為に外ならないのである。 従って、《遂行的なるもの》に対する制御あるいは言及は、いわゆる自己組織あるいは自己言及のパラドックスに陥らざるを得ない。 すなわち、《遂行的なるもの》は、それを対象として意識的に制御あるいは言及せんとするならば、制御の効率や言及の真偽をも含む、あらゆる行為の当否を、全く決定し得なくなるという意味において、制御不能あるいは言及不能とならざるを得ないのである。 言い換えれば、《遂行的なるもの》は、それに対する制御あるいは言及が、自己組織あるいは自己言及とならざるを得ないがゆえに、暗黙的となるのである。 行為の当否を決定するルールに対する制御あるいは言及の行為、すなわち、自己組織あるいは自己言及の行為は、何故に、行為の当否を決定不能に、従って、それが生成する秩序を制御不能に陥れるのであろうか。 たとえば、「私の決定は妥当しない」と私は決定する、といった典型的な自己言及(決定)の場合を考えてみる。 この場合、私の決定は妥当すると仮定すれば、私の決定は妥当しないことが帰結され、逆に、私の決定は妥当しないと仮定すれば、私の決定は妥当することが帰結される。 すなわち、この場合、私の決定の妥当するか否かは、決定不能い陥っているのである。 一般に、自己組織、自己言及、あるいは自己回帰といった循環的な事態は、この種の論理的なパラドックスに陥らざるを得ない。 すなわち、自らの妥当し得るか否かを決定する根拠それ自体への制御あるいは言及である。 自己組織あるいは自己言及の試みは、自らの妥当し得るか否かの決定不能を帰結することによって、挫折せざるを得ないのである。 従って、制御や言及やをも含む行為の秩序である《遂行的なるもの》は、合理的に制御可能とも言及可能ともなり得ない。 言い換えれば、《遂行的なるもの》は、《世界Ⅰ》では、決してあり得ないのである。 これまでの考察から明らかなように、《遂行的なるもの》は、《世界Ⅰ》でも、あるいは、《世界Ⅱ》でもあり得ない。 《遂行的なるもの》は、《遂行的なるもの》によってはついに捉え得ない、世界の第三の可能性としての《世界Ⅲ》なのである。 すなわち、《遂行的なるもの》は、行為遂行の累積的な帰結として、行為自らによって生成される秩序であるにも拘わらず、その主観的な意図にも還元され得ず、また、その意識的な対象としても制御され得ない、規範的かつ暗黙的な事態なのである。 言い換えれば、《遂行的なるもの》は、その構成要素たる行為の文脈依存的であるがゆえに、また、それを対象とする行為の自己言及的であるがゆえに、個体的に還元不能かつ合理的に制御不能となるのである。 行為は、何等かの文脈あるいはルールに従うことによって始めて、行為として発効し得る。 言い換えれば、行為は、自らを妥当させる根拠として、何等かの文脈あるいはルールを前提せざるを得ない(文脈依存性)。 この意味において、行為は、文脈やルールやといった秩序から、ついに逃れ得ないのである。 すなわち、行為にとっては、従うべきいかなる文脈やルールやをも見い出し得ない、秩序の全き「外部」など、決して存在し得ないのである。 しかし、行為に、その妥当根拠を与える、文脈あるいはルールそれ自体には、いかなる妥当根拠も在り得ない。 ルールの妥当し得るか否かを決定する根拠を、ルールそれ自体に委ねたとしても、あるいは、ルールを根拠として、自らの妥当し得るか否かの決定される、行為に委ねたとしても、ルールの妥当し得るか否かは、ついに決定し得ないからである(自己言及性)。 すなわち、ルールは、自らの発効し得るか否かを、その「内部」においては、ついに決定し得ない秩序なのである。 しかし、そのような秩序は、《遂行的なるもの》としてしか在り得ない。 すなわち、そのようなルールは、行為遂行の累積的な帰結としてしか在り得ないのである(行為累積性)。 従って、ルールは、行為の結果として生成されるにも拘わらず、行為によっては設定され得ない秩序であることが明らかになる。 言い換えれば、ルールは、行為によって意識的には語り得ず、ただ、行為において遂行的に示される秩序なのである。 《遂行的なるもの》は、行為の当否を決定する根拠であるとともに、自らは如何なる根拠も持ち得ず、行為の意図的な設定にもよらない、行為の累積的な帰結として生成される秩序である。 このような《遂行的なるもの》は、日常言語において、慣習(convention or practice)と呼ばれる事態と、ほとんど過不足なく重なり合っている。 すなわち、慣習とは、規範的、暗黙的かつ累積的な事態に外ならないのである。 あるいは、慣習とは、個体的に還元不能であり、合理的に制御不能でもある、世界の第三の可能性であると言ってもよい。 従って、個体的な主観としての《世界Ⅱ》や、合理的な客観としての《世界Ⅰ》やに対して、《世界Ⅲ》は、慣習的な遂行として捉えられることになる。 個体主義と合理主義とを共に懐疑し得る、《遂行的なるもの》の視点は、いわば慣習主義とでも呼ぶべき視点なのである。 この慣習という概念こそ、ハイエクの自生的秩序、ハートのルール論、さらにはオースティンの言語行為論を通底する、キー・コンセプトに外ならない。 すなわち、自生的秩序論においては、その自己言及性(制御不能性)が、また、ルール論においては、その外的視点から見た自己言及性(無根拠性)とその内的視点から見た文脈依存性(従根拠性)の双方が、さらに、言語行為論においては、その文脈依存性(還元不能性)が強調されつつも、慣習という概念の三つの構成要素である、文脈依存性、自己言及性、行為累積性の総てが、いずれの議論においても等しく登場している。 自生的秩序もルールも言語行為も、文脈依存性、自己言及性、行為累積性のトリニティを、その不可欠の構成要素としているのである。 市場も貨幣も法も権力も社交も言語も技能も儀礼も流行も、およそ社会あるいは文化と呼び得る総ての事態は、人間という事態をも含めて、《遂行的なるもの》として捉えられる。 すなわち、社会も文化もさらには人間それ自体も、慣習という事態に外ならないのである。 この発見は、あまりに当然と思われるかも知れないが、その含意は、極めて重大である。 しかし、その検討は、次節に委ねたい。 ◆2.新しい保守主義保守主義とは、近代啓蒙の批判に外ならない。
近代自然法思想を含めた啓蒙の哲学は、社会と人間の、合理的に制御し得ること、あるいは、個体的に還元し得ることを主張して止まない。 啓蒙の哲学は、社会と人間の合理化と個体化(rationalization and individualization)を称揚する、近代進歩主義の原型なのである。 このような啓蒙の哲学が、その淵源をどこまで遡り得るかについては、様々な議論があり得よう。 しかし、ここでは、それが、17・18世紀の200年を通じて形作られて来た、ある精神の型に過ぎないことを確認しておけば、差し当たり充分である。 むしろ、ここで問題にしたいのは、その啓蒙の精神が、フランス革命、さらには産業革命と民主革命の進行に伴って、我々の文明の最も誇るべき価値であるかのように、この世界に拡散して来たという事態である。 合理化と個体化を称揚する精神は、産業化と民主化の激流に翻弄された19世紀はもとより、20世紀末の今日においても、なお我々の文明の中心に位置するかのように見受けられる。 「情報化」という名の新たな産業化と、「差異化」という名の新たな民主化は、我々の時代を画する進歩の旗印として持てはやされている。 啓蒙の精神は、社会の合理的な管理と人間の個体的な解放というスローガンを高く掲げた、近代進歩主義の運動を、このニ世紀に亘って導いて来たのである。 もちろん、このニ世紀に亘る進歩主義の運動が、極めて多様な傾向を孕んでいることは言うまでもない。 そこには、いわゆる啓蒙主義によって導かれた、自然人権と国家集権を求めるフランス革命の運動もあれば、功利主義によって導かれた、自由化あるいは社会化を目指す漸進の運動もあり、さらには、マルクス主義によって導かれた、人間解放と社会管理のための革命運動もある。 しかし、これらの運動は、社会と人間の、産業化あるいは合理化と、民主化あるいは個体化を、意図的にあるいは結果的に推進したという点において、ほとんど選ぶ処はない。 いわゆる啓蒙主義はもとより、功利主義も、さらにはマルクス主義もまた、近代啓蒙の嫡出子なのである。 保守主義は、このような近代啓蒙の一貫した批判者である。 言うまでもなく、近代保守主義は、フランス革命のもたらした、社会の、理性による専制支配と、原子的個人への平準化の危機に抗して、「自由で秩序ある社会」を擁護すべく、エドモンド・バークによって創唱されたものである。 もちろん、保守主義的な態度が、バーク以前に存在しなかった訳ではない。 未知の変化に抗して、既知の安定を擁護しようとする態度は、むしろ人類と共に古いとも考えられ得るし、啓蒙の精神が形を成して来た、17・18世紀においても、それに対抗する態度は常に存在していたのである。 通俗的に言われるよりも遥かに深く、キリスト教を始めとする中世的あるいは近世的な伝統の内に生きていた、17・18世紀においては、むしろ啓蒙の精神こそが、西欧一千年の伝統から逸脱した、その対抗思想に過ぎなかったとも言えよう。 従って、17・18世紀においては、保守主義の、敢えて名乗りを挙げる必要は、必ずしもなかったのである。 何故ならば、保守主義とは、進歩主義の侵攻が、無視し得ぬまでに拡大して始めて、それを迎撃すべく、自らの重い腰を上げる性質のものだからである。 しかし、フランス革命を境として、進歩主義の侵攻は、もはや何人によっても無視し得ぬ段階に立ち至った。 フランス革命以降、産業主義と民主主義の進行に従って、進歩主義は、貴族制度や大土地所有やキリスト教やといった、あらゆる中世的(あるいは近世的)な伝統に次々と攻撃を加え、「自由で秩序ある社会」を決定的な危機に陥れたのである。 バークの闘った闘いは、このような進歩主義との闘いの緒戦を成すものであった。 フランス革命の啓蒙主義と闘ったバークを皮切りに、進歩主義のもたらす、合理的な専制と個体的なアノミーに抗する闘いは、このニ世紀に亘って、陸続と闘い継がれて来た。 近代保守主義とは、合理化と個体化という革命運動に抗する、不断の闘いそれ自体なのである。 言い換えれば、保守主義とは、啓蒙の精神の産み落とした、合理主義と個体主義の狂気に抗して、何等かの伝統に係留された、「正気の社会」を擁護する、終わりなき闘いの中にしかあり得ないのである。 それでは、保守主義は、何故に合理主義と個体主義を拒絶するのであろうか。 あるいは、また、保守主義は、如何にして啓蒙の精神を否定するのであろうか。 さらに、保守主義は、そのような拒絶や否定を通じて、何故に伝統を擁護することに至るのであろうか。 あるいは、そもそも、保守主義にとって、その擁護すべき伝統とは何であるのか。 これらの問いに答えることが、取りも直さず、前節までの議論と保守主義とを結び付ける、《失われた環》を見い出すことに外ならないのである。 保守主義は、社会と人間の、理性によって制御し得ることを否定する。 社会と人間が存続していくためには、理性によっては認識し得ないが、行為においては服従し得る、何等かの暗黙的な知識が不可欠なのであって、社会と人間の全体を、理性によって制御することなど、自分の乗っている木枝の根元を、自分で切る類いの所業に等しいからである。 言い換えれば、人間の行為は、理性の行使をも含めて、語り得ずただ従い得るのみの知識を前提として、始めて可能となるのであって、その暗黙的な前提をも含めた、自らの総体を制御することなど、全く不可能なのである。 人間の行為の不可欠な前提である、このような暗黙的知識は、理性的な行為の対象とならないがゆえに、その正当性を合理的には根拠付け得ない。 すなわち、このような暗黙的知識は、正当化し得ない無根拠な知識であるという意味において、まさしく偏見(prejudice)に過ぎないのである。 従って、人間の行為は、自らは何の根拠も持ち得ない偏見を前提として、始めて可能であることになる。 保守主義は、人間の生きていくために、暗黙的で無根拠な偏見に従うことの不可避であることを、強く主張するのである。 このような保守主義から見るならば、合理主義とは、合理的に制御し得ないものを制御せんとする、言わば暴力的な試みなのである。 そのような試みを、敢えて実行しようとするならば、制御の主体は、社会に対して、自らの意志を盲目的に強制する以外の、いかなる手段も持ち得ないことになる フランス革命やロシア革命、さらにはナチス・ドイツの経験が明らかにしたように、合理主義の行き着く先は、効率的な暴力を背景とする、野蛮な専制支配の外ではあり得ないのである。 保守主義は、社会と人間の、個人へと還元し得ることを否定する。 人間の行為は、それを取り巻く社会的、文化的な状況が与えられて、始めてその意味を決定し得るのであって、人間の行為の意味を、個人の内面的な意識へと還元することなど、言葉の意味を、他の言葉の意味との対比関係から切り離して、単独に決定する類いの所業に等しいからである。 言い換えれば、人間の行為は、他者の行為との関係をも含む、全体的な状況の中に位置付けられて、始めて成立し得るのであって、その全体的な状況が、個人の行為に還元し尽くされることなど、決してあり得ないのである。 人間の行為の成立/不成立を決定する。このような全体的状況は、行為の成否を決定する根拠となる、あるいは、行為の成立を正当化する理由となる、という意味において、規範的と言い得るものである。 すなわち、このような全体的状況は、行為を根拠付け、行為を正当化し得る、という意味において、まさしく権威(authority)と呼ぶべき事態なのである。 従って、人間の行為は、その根拠として服従すべき権威を前提として、始めて成立することになる。 保守主義は、人間の生きていくために、全体的で規範的な権威に従うことの不可避であることを、強く主張するのである。 このような保守主義から見るならば、個体主義とは、自らの拠って立つ不可避の基盤を見失った、個体の自己過信の外ではない。 個体主義とは、個体的に還元し得ないものを還元せんとする、いわば?神的な営みなのである。 そのような営みを、敢えて遂行しようとするならば、個人は、他者の、従って自己の行為の何であるかを全く了解し得ない、アノミーの深淵に立ちすくむことになるだけではない。 19世紀には絶望とともに予感され、20世紀には希望とともに実現された、高度大衆社会の実現が明らかにしたように、個体主義の精神がもたあすものは、無神論の深淵ではなく、神でも何でも手軽に信じて気軽に忘れる、多幸症の浅薄というアノミーに外ならないのである。 このように合理主義と個体主義を拒絶する、保守主義の橋頭堡としての偏見と権威が、理性によって意図的に設定されたものでも、個人によって意識的に合意されたものでもあり得ないことは言うまでもない。 偏見と権威は、行為の持続的な遂行の累積的な帰結として、自然発生的に生成されるものなのである。 すなわち、偏見と権威は、合理的な設定によらず、個体的な合意によらず、ただ遂行的にのみ生成される、まさに伝統(tradition)と呼ばれるべき事態なのである。 偏見とは、いかなる合理的な根拠も持ち得ない、俗なる伝統に外ならず、権威とは、あらゆる個体の根拠として従うべき、聖なる伝統に外ならない。 伝統とは、自らの如何なる根拠も持ち得ずに、他の一切の根拠として従われるべき、俗にして聖となる歴史の堆積なのである。 言い換えれば、伝統とは、歴史の試練に辛くも耐えて、偏見と権威の内に記憶される、生きられた経験に外ならないのである。 従って、偏見と権威に支えられて始めて成立し得る、人間とその社会は、このような伝統に従うことを、その不可避の条件とすることになる。 保守主義は、人間と社会の生きていくことが、つまるところ、伝統に回帰する以外にはあり得ないことを、強く主張するのである。 近代啓蒙の精神は、このような伝統や偏見や権威やを、蛇蝎の如く忌み嫌う。 因習や俗信や抑圧やから、人間を救済し、理性と自我との赴くままに、世界を革新すること、これが啓蒙の企てなのである。 しかし、保守主義から見るならば、このような啓蒙の企てこそが、合理主義的な抑圧と個体主義的な俗信とをもたらす当のものに外ならない。 近代啓蒙の精神は、不断に進歩することを、まさに因習となすことによって、専制的な抑圧とアノミックな俗信とを、常に帰結せざるを得ないのである。 保守主義のこのような回帰する伝統とは、合理的に制御し得る客観的なものではあり得ず、また、個体的に還元し得る主観的なものでもあり得ない、遂行的に生成される、言わば第三のものであった。 すなわち、伝統とは、客観的な自然でもあり得ず、主観的な意識でもあり得ない、第三の領域なのである。 このような第三の領域は、日常言語において、社会、文化、あるいは制度と呼ばれる領域に外ならない。 保守主義は、伝統に回帰することによって、客観的な自然法に根拠付けられる訳でもなく、主観的な社会契約に還元される訳でもない、社会という領域を再発見したのである。 言い換えれば、保守主義は、啓蒙思想による、理性と個人の発見に幻惑されて、一度は忘却の淵に立たされた、社会という現象を、再び見い出したのである。 社会の発見は、17・18世紀思想における理性と個人の発見に鋭く対比される、19・20世紀思想の鮮やかな特徴をなしている。 もちろん、合理主義と個体主義の哲学は、20世紀末の今日においてもなお有力なのではあるが、18世紀と19世紀の境に起こった転換以来、社会の、合理主義と個体主義によっては、ついに捉え得ない、という了解もまた、我々の共有財産となっているのである。 この意味において、保守主義は、社会についての哲学を、近代において始めて可能とした思想であると言えよう。 保守主義の歴史とは、取りも直さず、近代社会哲学の歴史に外ならないのである。 保守主義は、偏見と権威と伝統とを擁護することによって、合理的な客観としての自然でもなく、個体的な主観としての意識でもない、慣習的な遂行としての社会を、近代において始めて発見した。 すなわち、保守主義は、社会を、自らは如何なる合理的な根拠も保持せずに、自らにあらゆる個体的な行為を従属させる、遂行的な秩序として捉えることによって、近代社会哲学を創始したのである。 保守主義のこのように発見した社会が、前節に述べた《遂行的なるもの》と、ほとんど過不足なく重なり合っていることは明らかであろう。 《遂行的なるもの》とは、あらゆる行為がその成立/不成立を依存せざるを得ない文脈であり、また、いかなる根拠付けも自己に回帰する言及となるがゆえに不能である、遂行的な秩序のことであった。 すなわち、《遂行的なるもの》とは、個体的に帰属し得ず、合理的に言及し得ない、慣習的な秩序のことである。 従って、保守主義の発見した社会は、《遂行的なるもの》と、極めて正確に一致していることになる。 すなわち、保守主義は、偏見と権威と伝統とを擁護することによって、取りも直さず、《遂行的なるもの》を発見していたのである。 あるいは、むしろ、ハイエクの自生的秩序、ハートのルール、オースティンの言語行為、さらにはウィトゲンシュタインの言語ゲームを通底する、《遂行的なるもの》こそが、保守主義のニ世紀に亘って護り続けて来た伝統の、現代における再発見なのであるとも言い得よう。 20世紀哲学の到達した地点は、保守主義の歴史の新たな一ページなのである。 すなわち、ハイエク、ハート、オースティン、さらにはウィトゲンシュタインの到達した哲学は、20世紀末における新しい保守主義に外ならないのである。 もちろん、ハイエクもハートもオースティンも、さらにはウィトゲンシュタインも、自らを保守主義者と名乗っている訳では些かもない。 従って、現代における新しい保守主義を考察するためには、彼らの哲学よりも、むしろ、現代における正統的な保守主義者、たとえばマイケル・オークショットなどの哲学を検討すべきではないのか、という指摘も尤もである。 わけてもオークショットの社会哲学は、イギリス保守主義の掉尾を飾るものとして、是非とも検討されねばならない。 しかし、現代においては、保守主義者を名乗る人々の哲学が、必ずしも保守主義の哲学であるとは限らない。 啓蒙の哲学が、あたかも正統思想であるかのように流布されている現代においては、保守主義を騙って啓蒙を喧伝する輩が、跡を絶たないのである。 保守主義とは、まず何よりも啓蒙の批判に外ならない。 従って、現代における新しい保守主義の探求とは、取りも直さず、現代における反啓蒙の哲学の検討であらねばならぬのである。 ハイエク、ハート、オースティン、さらにはウィトゲンシュタインが、このような現代における反啓蒙の急先鋒であることは紛れもない。 本書は、経済哲学、法哲学、言語哲学を含む社会哲学の、20世紀における大立者達の言説の内に、現代における反啓蒙の、従ってまた、現代における新しい保守主義の可能性を探って見たのである。 20世紀末の保守主義は、自生的秩序やルールや言語行為や、さらには言語ゲームの哲学の内に、その新たな表現様式を見い出しているのである。 このような20世紀末の新しい保守主義が、ニ世紀に亘る保守主義の歴史に、何か付け加えたものがあるとするならば、それは、啓蒙の運動が不可能であることの、新しい表現様式である。 新しい保守主義は、社会と人間が、自らの要素である行為の文脈依存的であるがゆえに、個体的に還元され得ず、また、自らを対象とする行為の自己言及的となるがゆえに、合理的に制御され得ないことを主張する。 すなわち、新しい保守主義は、社会と人間の個体化と合理化という、啓蒙の運動の不可能であることを、言語行為論あるいは言語ゲーム論に準拠して主張するのである。 保守主義は、その誕生以来、時代の進歩主義に対応する、様々な表現様式に身を託して、合理化と個体化の不可能であることを主張し続けて来た。 新しい保守主義の準拠する、言語行為論あるいは言語ゲーム論もまた、20世紀末の進歩主義に対応する、そのような表現様式に外ならないのである。 いずれにせよ、保守主義によれば、社会と人間の合理化と個体化は、原理的に不可能である。 社会と人間に対する、進歩主義の貫徹は、所詮出来ない相談なのである。 そのような進歩主義を、敢えて貫徹しようとするならば、社会と人間は、暴力的な専制と涜神的なアノミーとへの分解によって、破壊し尽くされざるを得ない。 進歩主義は、その建設への意志とは裏腹に、社会と人間を、ついに崩壊へと導かざるを得ないのである。 まさしく、滅びへの道は、善意によって敷き詰められている。 従って、進歩主義と保守主義の対立は、社会と人間の生き方についての、可能な二つの道の対立などでは全くない。 進歩主義の道は、社会と人間の死滅に至る、不可能な道なのであって、社会と人間の辛くも生存し得る、唯一の可能な道は、保守主義の道なのである。 すなわち、進歩主義と保守主義の対立は、社会と人間の存続し得るか否かを賭けた、全く抜き差しならぬ対立なのである。 この命題は、もとより、一般の社会と人間についても成立し得ると思われるが、ここでは、その近代の社会と人間についての成立が確認されねばならない。 すなわち、近代の社会と人間は、あたかも近代の正統思想であるかのように見なされている、進歩主義のみによっては、自らの存続すらをも保証し得ないのである。 言い換えれば、近代の社会と人間が、数世紀に亘って辛くも存続しているとするならば、それは、金ぢあの社会と人間が、己の意識するとしないとに拘わらず、保守主義を、事実として生きてしまっているからに外ならない。 近代の社会と人間は、あたかも反近代の異端思想であるかのように見なされている、保守主義を生きることによって始めて、自らの存続を辛くも保ち得るのである。 これは、何の逆説でもない。 社会と人間は、まさにそのようなものとして、生きられているのである。 ◆3.保守主義とは何でないか前節までで、差し当たり本書の議論は尽くされている。
しかし、保守主義というテーマは、いかにも誤解され易いテーマであって、有り得べき誤解に対して、あらかじめ何等かの釈明を試みて措くことは、あながち無益ではなく、むしろ必要ですらある。 もし、そうであるならば、前節までの行論の中で、当然予想される誤解について、逐一予防線を張って措けばよさそうなものであるが、そうもいかない。 何故ならば、保守主義という言葉は、本論で問題としている議論領域を遥かに越えた、極めて多様なイメージを伴って用いられているのであって、保守主義を巡る誤解もまた、その多様なイメージに因って来るものだからである。 従って、保守主義を巡る誤解についての釈明は、本論の議論水準とは一段異なった、より広い土俵において為されねばならない。 本節では、本論に述べられた意味における保守主義が、自らの呼び醒ます多様なイメージの中にあって、一体何でないのか、すなわち、保守主義とは何でないかを論じることによって、保守主義を巡る幾つかの誤解に対するささやかな釈明を試みて措きたい。 保守主義、わけても新しい保守主義と言えば、いわゆる新自由主義(Neo-Liberalism)のことかと思う向きも、あるいは少なくないかも知れない。 たとえば巷間ハイエクは、新自由主義の泰斗ということにされている。 保守主義と自由主義との関係については、おそらく最も誤解の生じ易い論点であるに相違ないので、是非とも釈明して措かねばならない。 また、保守主義は、近代の産業主義と民主主義、あるいは合理主義と個体主義を根底的に批判する、反啓蒙の思想に外ならない。 それでは、保守主義は、たとえば環境社会主義(Eco-Socialism)に代表されるような、いわゆる反近代の思想なのであろうか。 保守主義と反近代主義との関係については、近代文明における保守主義さらには進歩主義の位置付けを迫る論点であり、是非とも釈明して措かねばならない。 さらにまた、保守主義は、何よりも社会・文化の伝統を擁護せんとする態度である。 従って、保守主義は、たとえば日本の社会・文化に固有な伝統をどのように捉えるか、といった問題を避けて通る訳にはいかない。 保守主義といわゆる日本主義(Japanism)との関係については、保守主義の近代文明における位置付けとも複雑に絡まった論点であり、是非とも釈明して措かねばならない。 本節では、以上の三つの論点について、極簡単に触れることにする。 いずれの論点も、かなり大きなテーマであることもさりながら、本節の狙いは、飽くまで本論に述べられた保守主義を巡る、有り得べき誤解を防いで措くことに限られるからである。 この20世紀末の現代において、保守主義と言えば、自由主義、わけても新自由主義を思い浮かべることは、むしろ当然である。 19世紀の最後の四半分に端を発して1970年代に至る、ほぼ一世紀の長きに亘って、進歩主義の旗印は、福祉社会主義あるいは民主社会主義さらにはケインズ主義を含む、最も広い意味での社会主義によって担われてきた。 20世紀は、経済的成長や社会的平等といった福祉(welfare)を目的として、経済社会を合理的に管理せんとする運動が、言わば最高潮に達したという意味において、まさに社会主義の世紀だったのである。 このような社会主義の進攻に直面した保守主義が、社会主義の対抗思想としての側面を持つ自由主義と、ほとんど分離不可能なまでに接近して見えたということは、あまりに当然である。 保守主義は、19世紀を通じて真剣を交えてきた当の相手である自由主義と、社会主義なる新たな敵を前にして、公然と手を結んだかに見えたのである。 ましてや、さいもの社会主義もようやく陰りを見せ、小さな政府や自由な市場を求める新自由主義の運動が、かなりの勝利を収めたかに見える、20世紀の最後の四半分において、保守主義が、社会主義による積年の抑圧から解放された喜びを、自由主義と共に分かち合っているように見えたとしても、また、極めて当然である。 社会主義との、ほぼ百年に及んだ戦いもひとまず終わり、勝利の美酒を同盟軍と共に酌み交わすひととき、といった具合である。 しかし、保守主義と自由主義との、このような同盟関係は、うたかたの夢に過ぎない。 何故ならば、自由主義とは、19世紀を通じて、保守主義と死闘を繰り広げて来た、進歩主義の尖兵に外ならないのであり、20世紀に入って、進歩主義の旗手たるの地位を、社会主義に追い落とされたと言えども、その啓蒙の嫡出子としての本質には、些かの変りもないからである。 蓋し、自然権としての個人の自由は、人間的自然としての理性による支配とともに、啓蒙の精神の求めて止まぬ処であった。 自由主義の、進歩主義としての性格は、言わば骨絡みなのである。 従って、20世紀における、保守主義と自由主義との接近は、社会主義の凋落が決定的となった今日においては、むしろ両者間の距離にこそ注目すべきなのである。 それでは、保守主義と自由主義わけても新自由主義は、いかなる点において重なり合い、また、いかなる点において袂を分かつのか、このことが問われねばならない。 ここで注意して措かねばならないことは、自由主義と呼ばれる社会思想の中には、必ずしも社会主義と対立せず、むしろ広い意味での社会主義に含まれると言った方が良さそうなものがある、ということである。 たとえば、個人の自由を(形式的にではなく)実質的に保障するためには、個人の自由に任せて措くだけでは全く足りず、国家が、社会に対して(消極的にではなく)積極的に介入し、これを合理的に管理せねばならない、とする類いの自由主義(※注釈:いわゆるリベラリズム=マイルドな社会主義)である。 このような自由主義は、なるほど自由主義を名乗ってはいるが、社会全体に対する合理的な管理を要請するという点において、むしろ広義の社会主義と呼ぶべき主張である。 因みに、このような自由主義は、バーリーンの言う積極的自由を称揚する態度であり、19世紀末には、新自由主義(※注釈:T.H.グリーンらのnew liberalism であり、neo-liberalism とは違うことに注意)と呼ばれた立場である。(世紀末には新自由主義が流行るようだ。) ここでは、このような自由主義を、社会主義に含めて考えることにし、自由主義としては言及しないことにしたい。 自由主義とは、差し当たり、他者による強制のない状態としての自由、すなわち、バーリーンの言う消極的自由を擁護する態度である。 従って、自由主義は、国家が社会全体を合理的に管理せんとする態度と両立しない。 何故ならば、社会全体を合理的に管理することは、たとえば社会全体の福祉といった目的を効率的に達成すべく、社会に内蔵する資源を動員し行為を配列することに外ならないのであって、それは、個人が、自らの資源と行為を自由に処分することと、真っ向から対立せざるを得ないからである。 言い換えれば、社会全体の合理的な管理は、国家による個人に対する何等かの強制、すなわち、国家による個人の自由の制限を、不可避的に含意しているのである。 もっとも、自由主義は、国家による個人に対する強制の総てを否定する訳ではない。 たとえば、個人の行為が、他者の自由を侵害して為される場合、国家が、その行為の差し止めや、他者に与えた損害の賠償などを、個人に強制することは、自由主義と言えども全く否定しない。 むしろ、自由主義とは、個人の自由を他者による侵害から保護することにこそ、国家の役割があるとする主張とさえ言い得る。 しかし、国家が、個人の(消極的)自由を、その侵害から保護することと、個人の(積極的)自由を、たとえば無知や貧困や失業やといった、その障害から解放するために、社会全体を合理的に管理することとは、全く異なる事態なのであって、自由主義は、前者の国家のみを肯定し、後者の国家を厳しく否定するのである。 従って、自由主義は、社会全体の秩序を、(他者の自由を侵害しない限りにおける)諸個人の自由な行為に委ねることになる。 すなわち、自由主義は、社会全体の秩序を、国家が合理的に設定するものではなく、諸個人の自由な行為の累積的な帰結として自然発生的に生成されるものである、と捉えるのである。 因みに、ハイエクの言う自由主義とは、まさにこの意味における自由主義に外ならない。 ハイエクは、社会を合理的に設定された組織として捉える、最広義の社会主義に抗して、社会を自然発生的に生成された自生的秩序として捉える、このような自由主義を擁護するのである。 この意味における自由主義が、保守主義とほとんど過不足なく重なり合っていることは明らかであろう。 すなわち、この意味における自由主義は、社会を合理的に管理せんとする進歩主義に対抗する、保守主義の一局面そのものなのである。 しかし、そうであるからと言って、自由主義のあらゆる局面が、保守主義と一致する訳では必ずしもない。 自由主義には、社会を、個人の意図や情緒や欲求やに還元し得るし、また、すべきであるとする傾きが、避け難く存在している。 たとえば、社会のルールとしての法を、自然権を保有する自由な諸個人の合意に還元する、社会契約論や、さらには、社会のルールとしての法を、何ものにも制限され得ない自由な主権者の意志に帰着する、主権論といった、近代啓蒙の個体主義は、いわゆる自由民主主義として、今日なお、自由主義の内にその命脈を保っている。 自由主義は、なるほど、近代啓蒙の合理主義に対して、保守主義とその批判を共有しているのであるが、しかし、近代啓蒙の個体主義に対しては、必ずしも一線を画してはいないのである。 この意味において、自由主義は、依然として、進歩主義の一翼を担っている。 因みに、急進的な自由主義が、何ものにも制限され得ない国民主権を標榜する、無制限の民主主義に変転する例は枚挙に暇がない。 個人が自らの行為を自由に選択し得るとするならば、自らの属する社会の制度もまた、自らの自由な同意に基づいて選択されるべきだ、という訳である。 保守主義が批判するのは、まさに、このような無制限の民主主義に外ならない。 なるほど、保守主義にとっても、個人の行為は自由に選択され得るものであり得るが、しかし、社会の制度全体は、個人の行為を可能にする前提となりこそすれ、個人の合意によって自由に選択され得るものでは決してあり得ない。 従って、保守主義は、このような無制限の民主主義を帰結する、いわば社会契約論的な自由主義とは、全く両立し得ないのである。 因みに、ハイエクは、このような無制限の民主主義を峻拒している。 すなわち、ハイエクもまた、保守主義と同様に、社会契約論的な意味における自由主義とは、ついに両立し得ないのである。 従って、保守主義は、社会を諸個人の自由な行為の累積によって生成される秩序として捉える、言わば自然発生論的あるいは慣習論的な自由主義とは、ほとんど過不足なく重なり合うが、社会を諸個人の自由な意志の一致によって設定される秩序として捉える、社会契約論的あるいは自然権論的な自由主義とは、全く両立し得ない。 また、保守主義が、社会を諸個人の欲求の自由な実現のために(国家が)制御すべき対象として捉える、いわゆる功利主義的な自由主義(ここでは社会主義に含めた)と、鋭く対立していることは言うまでもない。 言い換えれば、保守主義は、自由主義のヒューム的(慣習論的)な伝統には極めて親しいが、そのロック的(自然権論的)な伝統、さらには、そのベンサム的(功利主義的)な伝統には全く疎遠なのである。 現代における自由主義の復興は、そのベンサム的な伝統を排除することにおいては、なるほど意見の一致を見ているが、そのヒューム的な伝統あるいはロック的な伝統のいずれを継承するかについては、必ずしも意見の一致は見られない。 ハイエクのようにヒューム的な伝統に棹さす者もいれば、ノージックのようにロック的な伝統の嫡流たらんとする者もある。 いずれにせよ保守主義は、自由主義あるいは新自由主義のあらゆる潮流と手を結び得る訳ではない。 保守主義は、自由主義のただ一つの潮流とのみ与し得るのである。 あるいは、そのような自由主義は、自由主義の一つの潮流であると言うよりも、むしろ保守主義そのものであると言うべきなのかも知れない。 蓋し、自由主義のヒューム的さらにはバーク的な伝統こそが、保守主義の本流を形成してきた当のものに外ならないとも言い得るからである。 保守主義は、近代の産業主義と民主主義、あるいは、啓蒙の合理主義と個体主義を懐疑する、反啓蒙の思想である。 それでは、保守主義は、近代文明を否定しまた超克せんとする、反近代の思想であるのか。 ここに、保守主義を巡る、最大の陥穽が潜んでいる。 本書で明らかにしたかったことは、啓蒙の合理主義と個体主義とが、あたかも、その最も誇るべき価値であるかのように見なされている近代社会と言えども、社会という事態である限り、啓蒙の合理主義と個体主義とによってはついに捉え得ない、第三の性質を俟って始めて存立し得るということである。 すなわち、近代文明もまた、一個の文明である限り、啓蒙の精神の最も忌み嫌う、何等かの伝統に係留されて始めて存続し得るのである。 従って、反啓蒙の思想は、必ずしも反近代の思想ではあり得ない。 むしろ、反啓蒙の思想は、近代という社会の存立の秘密に接近し得る、ほとんど唯一の思想なのである。 この反啓蒙の思想と反近代の思想とを取り違えた処に、保守主義を巡る、幾多の悲喜劇が生じたのであった。 なるほど、保守主義を貫く反啓蒙の精神は、時として、近代文明そのものを拒絶しているかのようにも見受けられる。 たとえば、バークが、フランス革命を否定するに当たって、あたかも、中世への復帰を唱導しているかのように見える処がない訳ではない。 あるいは、日本において、伝統への回帰が語られる時、あたかも、古代の復古が号令されているかのように見えることもないとは言えない。 しかし、真正の保守主義は、いまここに生きられている社会をこそ、その存立の秘密の顕わとなる深みにおいて肯定せんとする営みなのであって、いまここに生きられている社会を、少なくともその最深部において否定し去ることなど決してあり得ないのである。 いまここに生きられている社会とは、差し当たり、近代社会の外ではあり得ない。 あうなわち、保守主義は、反啓蒙の精神を採ることによって、いまここに生きられている、近代という社会を、その存立の深みにおいて肯定せんとしているのである。 しかし、そうであるからと言って、近代を肯定することは、古代や中世を否定することでは些かもない。 真正の保守主義は、近代の社会を存立させている秘密と、古代や中世の社会を存立させていた秘密とが、それほど違ったものではあり得ないことを、重々承知しているからである。 社会を存立させる秘密の顕わとなる、その最深部においては、時代の如何に拘わらず、常なるもの、すなわち、伝統が、生きられているのである。 啓蒙の精神とは、古代や中世やさらには近代において生きられている伝統の一切を否定して、人間の理性と個人の自由の下に、全く新しい社会、すなわち、彼らの言う近代社会を建設せんとする試みに外ならない。 保守主義は、啓蒙の精神を懐疑することによって、古代や中世の伝統を生きられたそのままに肯定する一方で、それが、近代社会の存立をその最深部において支えている伝統と、それほど遠いものではなく、むしろ、密かに連なりさえしていることを承認するのである。 すなわち、保守主義は、生きられている伝統を擁護することによって、啓蒙の進歩主義ばかりが如何にも目立つ近代文明を、その最深部において肯定しているのである。 従って、保守主義は、反近代主義ではあり得ない。 保守主義は、たとえばマルクス主義や国家社会主義のように、近代の超克を志している訳でもないし、たとえばロマン主義や環境社会主義のように、前近代の桃源郷を夢見ている訳でもない。 マルクス主義や国家社会主義は、反近代を標榜しているにも拘わらず、実は最も急進的な合理主義を帰結するという意味において、まさしく啓蒙の嫡出子と呼ばれるに相応しいし、ロマン主義や環境社会主義は、なるほど反啓蒙の思想ではあるが、近代文明の唯中に、帰るべき常なるものを見出し得なかったという意味において、ついに反近代の思想でしかあり得ない。 マルクス主義や国家社会主義は言うまでもなく、ロマン主義や環境社会主義もまた、ついに保守主義ではあり得ないのである。 さらに、わけても環境社会主義は、たとえばエコロジーや反原発といった、その反近代の運動において、極めて急進的な個体主義の様相を呈することが、少なくないのであって、むしろ、啓蒙の自然権論を体現していると言っても、ほとんど言い過ぎにはならないのである。 総じて、マルクス主義や国家社会主義、さらには環境社会主義をも含む、比較的狭い意味における社会主義は、最も急進的な啓蒙主義以外の何ものでもない。 保守主義は、このような反近代の仮面を被った啓蒙主義とは、決して両立し得ないのである。 保守主義は、人間とその社会が、何等かの伝統に係留されて始めて存立し得ることを強調する。 しかし、社会やあるいは文化の伝統とは、(本書に述べられた《遂行的なるもの》であるがゆえに)その具体的な様相に一歩でも踏み込もうとするならば、それが遂行されている地域や歴史に相対的なものとして示されざるを得ない。 すなわち、具体的に生きられている伝統は、たとえば、イギリスの伝統であり、日本の伝統であり、あるいは、東京の伝統であり、京都の伝統であり、はたまた、西ヨーロッパの伝統であり、東アジアの伝統なのである。 従って、保守主義が伝統を擁護すると言った場合、その擁護すべき伝統は、具体的には、何等かの地域や歴史に固有な伝統であらざるを得ないことになる。 言い換えれば、保守主義は、具体的には、地域あるいは歴史に固有な保守主義としてしかあり得ないのである。 従って、たとえば日本において保守主義を語ることは、取りも直さず、日本において生きられている伝統を擁護する、日本に固有な保守主義を語ることに外ならない。 それでは、そのような保守主義は、自文化中心主義、ナショナリズム、あるいは日本主義と、どこが違うのであろうか。 日本の保守主義など、皇国主義と大同小異ではないのか。 このような疑問が当然に生じて来ると思われる。 さらに、このような疑問は、日本に特徴的なもう一つの事情によって、いよいよ深まらざるを得ない。 なるほど保守主義は反啓蒙の思想であった。 しかし、そもそも啓蒙思想とは、西欧近代において誕生した、西欧近代に固有の思想に外ならない。(もっとも、啓蒙思想が西欧に固有な思想であるか否かは、なお検討すべき課題である。) 西欧近代は、その色鮮やかな表層のみに目を奪われるならば、あたかも、啓蒙思想一色によって塗り潰されているかのように見受けられる。 言い換えれば、保守主義は、反啓蒙の立場を採ることによって、反西欧の態度を帰結するのではないか。(保守主義が、反近代の態度を帰結し得ないことは既に述べた。) すなわち、保守主義は、その西欧における機能はいざ知らず、日本を含む非西欧においては、啓蒙という名の西欧文化中心主義あるいは西欧文化帝国主義に対抗する、反西欧の思想として機能しているのではないか。 このような推測のしばしば行われていることも、無下には否定し得ない。 もし、このような推測が、当を獲たものであるとするならば、日本の保守主義は、反西欧主義という意味において、ますます日本主義に接近するのではないか。 なるほど、日本主義は、近代の合理主義と個体主義との対極にあるとされる、日本の伝統に立脚した、反啓蒙の思想であることには間違いない。 しからば、日本の保守主義は、反啓蒙の伝統文化の咲き誇る東亜の盟主として、啓蒙の革新文明に堕落したあ西欧に宣戦すべきなのであろうか。 しかし、ここで想い起こすべきは、保守主義が、反近代の思想ではついにあり得ないということである。 すなわち、保守主義が、伝統を擁護すると言った場合、そこで語られている伝統は、いまここで生きられている近代社会の存立を、その深層において支えている伝統に外ならないのである。 従って、日本の保守主義が、日本の伝統を擁護すると言った場合、そこで語られている伝統は、いまここに生きられている日本近代の存立を、その深層において支えている伝統の外ではありえない。 言い換えれば、日本の保守主義は、近代文明の日本における顕現を、その深層において、肯定しているのである。 現代の日本において生きられている社会が、紛れもなく近代社会である以上、日本の保守主義は、日本の近代社会に、肯定すべき何ものかを見出さざるを得ない。 保守主義とは、そういったものなのである。 従って、日本の保守主義は、日本の伝統を、それが反近代であるから擁護するということでは些かもない。 むしろ、それが日本近代の存立に不可欠であるからこそ擁護するのである。 この間の事情は、西欧においても全く変わりはない。 たとえば、イギリスの保守主義は、イギリスの伝統を、それがイギリス近代の存立に不可欠であるからこそ擁護するのである。 このように言えば、イギリスの伝統と日本の伝統とは全く違う、といったお馴染みの議論がすぐにでも思い浮かばれよう。 もとより、イギリスの伝統と日本の伝統とが同じである筈もない。 しかし、近代文明における反啓蒙の橋頭堡という意味においては、彼我の伝統は、いわば機能的に等価なのである。 すなわち、近代文明における啓蒙の精神は、近代文明の圏内においては、ほとんど同一であり、その意味において、普遍的である。 さらに、近代文明が、啓蒙の精神のみによっては存立し得ず、反啓蒙の伝統を俟って始めて存立し得るという事態もまた、普遍的である。 しかし、近代文明の存立に不可欠な反啓蒙の伝統が、具体的に何であるかとなると、これは、近代文明の圏内においても、様々であり得る。 すなわち、近代文明という、いわば地球大の文明の存立に不可欠な伝統は、近代文明の圏内にある様々な文化に固有な伝統以外ではあり得ないのである。 言い換えれば、近代文明とは、それを担う様々な文化に固有な伝統を前提として、始めて可能であるような文明なのである。 従って、近代文明において、啓蒙の進歩主義は、なるほど普遍的であり得るが、反啓蒙の保守主義は、反啓蒙という一点を除いては、決して普遍的ではあり得ない。 近代の保守主義は、反啓蒙という機能においては等価であるが、それを担う実体としては異文化である、固有の伝統のいずれかに係留されざるを得ないのである。 これは、社会あるいは文化の伝統が、本書に述べた《遂行的なるもの》であることの、ほとんど必然的な帰結である。 このような立論は、近代文明と西欧文化との間に如何なる差異も認めない向きにとっては、なかなか理解し難いものであろう。 しかし、近代文明とは、ほとんど全地球を覆う、優れて普遍的な文明なのであって、西欧文化や日本文化をも含む、極めて多様な文化あるいは社会によって担われている、と考えることはそれほど無理なことであろうか。 古代や中世の歴史においては、単一の普遍な文明が、多数の固有な文化あるいは社会によって担われている例は、枚挙に暇がない。 中国文明、インド文明、イスラム文明、ギリシア・ローマ文明など、総て、そのような文明の例である。 そもそも、文明と呼び得る程にも普遍的であり得るためには、その内部に少なくとも複数の分化あるいは社会を包含していることが、ほとんど必須の条件であると言ってもよい。 近代文明もまた、そのような文明の一つなのである。 従って、西欧の社会も、日本の社会も、それが近代文明を担っている社会の一つであるという点においては、些かの相違もない。 しかし、それらの社会が、近代の社会として存立するに当たって、具体的に如何なる伝統を不可欠なものとしているかについては、それぞれに固有の事情が介在しているのである。 たとえば、イギリスの近代社会の存立に当たって、間柄主義の伝統の不可欠である筈もなく、あるいは、日本の近代社会の存立に当たって、アングリカニズムの伝統の不可欠である筈はない。 いずれにせよ、近代の保守主義は、普遍的な近代文明の存立にとって不可欠な伝統を、個別的な地域文化に固有な具体性の中に見出していかねばならないのである。 このような保守主義が、単純な自文化中心主義やナショナリズム、あるいは反西欧主義や日本主義に、そう易々と陥り得ないことは明らかであろう。 保守主義は、いまここに生きられている社会が、近代文明の下にある社会であることを、よく承知している。 さらに、保守主義は、自らの社会に固有な伝統を擁護することが、近代文明の下にある総ての社会にとって、不可避の要請であることも、また、よく承知している。 従って、保守主義は、自らの固有な文化が、近代文明の下にある総ての社会において、生きられるべき普遍の伝統となり得るなどとは夢にも想わない。 ましてや、保守主義は、自らの固有な文化が、近代文明それ自体と対抗せざるを得なくなるとは、全く考えもしない。 保守主義は、自文化中心主義やナショナリズム、さらには反西欧主義や日本主義では、ついにあり得ないのである。 しかし、そうは言っても、近代文明と、それを担っている地域文化、わけても西欧文化との判別は、かなり複雑な課題である。 どこまでが近代文明の普遍的な特徴であり、どこまでが西欧文化の個別的な特徴であるかは、極めて識別の困難な課題なのである。 従って、西欧の保守主義はいざ知らず、日本の保守主義は、近代文明の唯中に極めて分離し難く纏わり付いている西欧に固有な伝統と、自らに固有な伝統との葛藤を引き受けねばならない。 近代文明の下における、地域文化相互間の葛藤は、依然として開かれた問いなのである。 しかし、近代文明が、地域的な固有文化を超えた、全地球的な普遍文明であり得るとするならば、この問題は、必ずや解決されるに相違ない。 そのとき、保守主義の擁護すべきは、地球文明の存立にとって決して逸することの許されない、全地球的に生きられる言わば普遍の伝統であるのかも知れない。 そのときに在っても保守主義は、地球文明のキー・ストーンとして、なお生きられねばならないのである。 |
| + | ... |
◆1.解釈学的社会学へ本書のこれまでの諸章は、オースティンの言語行為論やウィトゲンシュタインの言語ゲーム論と、保守主義の社会哲学との関連を述べている。 主としてイギリスの20世紀哲学と保守主義との関連を述べて来たのである。 尤も、オースティンとハートは、確かにオックスフォードの人であるが、ウィトゲンシュタインとハイエクは、言うまでもなくウィーンの人である。 しかし、今世紀初頭のウィーン哲学は、必ずしもドイツ哲学の本流とは言い得ず、むしろイギリスにおいて活躍する人々の方が多かったと言っても過言ではない。 ウィーンの哲学は、ドイツにおけるイギリス哲学なのである。 いずれにせよ、本書のこれまでの諸章は、イギリス哲学に焦点を絞って来たのである。 ところが、これまでの論述において、20世紀イギリス哲学の行き着いた地平を辿って行く内に、それが、20世紀ドイツ哲学わけても解釈学的哲学の行き着いた地平と、極めて類似していることに幾度となく気付かされざるを得なかった。 村上泰亮の言葉を借りれば、「後期のウィトゲンシュタインは、ほとんど現象学への - 言わば裏側からの - 復帰を果たしているように映るのである」。 従って、20世紀イギリス哲学の帰結に、保守主義の社会哲学を読み込む本書としては、20世紀ドイツ哲学わけても解釈学的哲学と、それがもたらす社会哲学上の帰結に目を向けない訳にはいかない。 本書は、解釈学的社会学の方へと、呼ばれざるを得ないのである。 しかし、19・20世紀におけるドイツの社会哲学を取り上げるには、いささかの勇気が必要とされる。 それは、私自身が、これまで主としてイギリスの社会哲学を読み継いで来たという、研究経歴上の問題のためだけではない。 19・20世紀ドイツの社会哲学が輝かしいものであればある程、何故にドイツは、今世紀の二つの大戦において、あのように凄惨な敗北を喫さねばならなかったのか、という問いが否応なく覆い被さって来るからである。 もとより、ある言語による社会哲学に、その言語圏に属する国家社会の歴史的運命への、直接の責任が有り得よう筈もない。 しかし、ある社会における思想の在り様が、その社会の歴史的な運命に全く無関係であることもまた有り得ない。 ドイツの社会哲学は、ドイツの運命的な敗北に、何等かの関係を持っている筈なのである。 それでは、近代ドイツ思想と近代ドイツ社会の運命は、如何ように交錯するのであろうか。 この問いを問い切るためにこそ、些かの勇気が必要とされるのである。 何故ならば、この問いに対する答え方によっては、いわゆる戦後的な「常識」に、真っ正面から対立せざるを得なくなる場合も、充分に想像し得るからである。 このような勇気は、決定的な敗北ということをついぞ知らない、近代イギリスの社会哲学を取り上げるに当たっては、必ずしも必要とはされない。 しかし、たとえば近代日本の社会哲学を取り上げようとするならば、是が非でも必要とされるものである。 蓋し、近代日本社会もまた、過ぐる大戦において歴史的な敗北を喫したのであり、そのことと、近代日本思想との関係もまた、避けては通れない問いだからである。 いずれにせよ、近代ドイツの社会哲学あるいは近代日本の社会哲学を取り上げんとする試みは、少なくとも私には、些かの勇気を必要とする試みであるように思えてならないのである。 従って、以下の試みは、ささやかな覚悟を秘めてのことである。 20世紀末の時点に立って、ドイツの哲学を概観するならば、そこには、大きく三つの潮流の存在していることが見て取れる。 一つは、現象学あるいは解釈学に代表される潮流であり、二つは、フランクフルト学派あるいは批判理論に代表される潮流であり、三つは、分析哲学あるいは批判的合理主義に代表される潮流である。 これらの三潮流は、それぞれに社会哲学上の帰結を含意している。 すなわち、第一の潮流は、解釈学的社会学を、第二の潮流は、批判社会学を、第三の潮流は、機能主義社会学を含意しているのである。 これら三潮流を、その相互連関に留意しつつ、大胆に要約するならば、まず、第二の批判理論とは、たとえば人間の解放といった普遍妥当的とされる根拠に基づいて、社会の総体を批判しさらには変革し得るとする哲学であって、マルクスとフロイトの継承線上に位置することを、自他共に認める立場である。 次に、第三の批判的合理主義あるいは機能主義とは、人間の知識に普遍妥当的な根拠付けなど可能ではなく、知識とは、自らを妥当させる根拠(たとえば反証可能性基準)それ自体の選択をも含めた、自由な決断に外ならないとする哲学であって、三潮流の中で唯一、現代的な科学の方法論であり得ることを自負している立場である。 これらに対して、第一の解釈学とは、人間とその社会あるいは文化の解釈は、たとえば社会の伝統といった自らを妥当させる根拠をも、自らの対象とせざるを得ないのであるから、自らの普遍妥当性を根拠付け得る筈もなく、しかし、自らの妥当根拠を自由に選択し得る訳でもないとする哲学であって、19世紀以来のテクストあるいはコンテクスト解釈学の伝統に棹さす立場である。 言い換えれば、 批判理論とは、価値と認識についての普遍主義あるいは客観主義の視点に立つ、実践の哲学であり、 批判的合理主義とは、価値と認識についての相対主義あるいは主観主義の視点に立つ、科学の哲学であるのに対して、 解釈学とは、客観主義あるいは主観主義のいずれでもない言わば第三の視点に立つ、伝統の哲学なのである。 このような大胆な要約を示されれば即座に、幾つもの疑問が涌き上がって来て当然である。 たとえば、解釈学のいう伝統と、現象学の言う《生活世界》とは、果たして如何なる関係にあるのか、また、実践哲学の復権が言われる中で、批判理論は、果たして如何なる位置を占めるのか、さらに、批判的合理主義の言う仮説選択と、機能主義の言う《システム》選択とは、果たして異なった概念であるのか、等々の疑問である。 しかし、本論においては、これらの疑問にこれ以上立ち入ることはしない。 これらの疑問を詳細に検討するためには、遥かに充分な準備が必要とされるからである。 むしろ、本論においては、人間とその社会あるいは文化を解釈するという、解釈学的な問題の構造を解析することによって、何故に、批判理論と機能主義(批判的合理主義)が社会理論として不可能となり、解釈学的な社会理論のみが可能となるのかを検討してみたい。 さらに本論においては、そのような解釈学的社会学が、何故に保守主義であらねばならぬのかも検討してみたい。 これらの検討を通じて、伝統へ回帰することが、社会を解釈することの、逃れ得ぬ条件であり、かつ、避けられぬ帰結であることが、明らかになると思われる。 ◆2.自己関係性の構造人間や社会や文化を解釈するという行為は、一体、いかなる特徴を持った行為であるのか。 この問いを問う前に、まず、社会という事態を如何に把握すべきかについて、多少なりとも議論して措く必要がある。 社会とは、差し当たり、人間の行為の集合である。 しかし、このような行為空間に、何等かの構造、形式あるいは秩序が導入されて始めて、社会は、社会として発見され得る。 すなわち、社会とは、何等かの構造、形式あるいは秩序の存在する行為空間なのである。 ここに言う、行為空間に何等かの構造、形式あるいは秩序が存在するとは、ある行為空間に内属する行為が、何等かの根拠に基づいて、その妥当であるか否か、あるいは、その有効であるか否かを、ほとんどあらゆる場合に決定され得る、という事態に外ならない。 言い換えれば、構造、形式あるいは秩序の存在する行為空間とは、自らに内属する殆どあらゆる行為の、妥当であるか否か、あるいは、有効であるか否かを、常に決定し得る行為空間なのである。 ここでは、この意味において、構造、形式あるいは秩序の存在する行為空間を、秩序付けられた行為空間と呼び、そのように行為空間を秩序付ける、すなわち、行為の妥当性あるいは有効性を決定する根拠となるものを、行為のノルム(規範)、ルール(規則)あるいはコンテクスト(文脈)と呼ぶことにしたい。 すなわち、行為は、何等かの規範、規則あるいは文脈に依することによって始めて、自らの妥当し得るか否かを決定し得るのであり、また、行為空間は、何等かの規範、規則あるいは文脈が導入されて始めて、秩序付けられるのである。 従って、社会とは、何等かの文脈によって秩序付けられた、行為空間に外ならないことになる。 言い換えれば、社会とは、何等かの文脈に依存することによって始めて、自らの妥当しうるか否かを決定し得る、行為の集合に外ならないのである。 このような社会という事態を解釈する行為は、一体、如何なる特徴を持つのであろうか。 行為という事態を、一篇のテクストに譬えることが許されるならば、ある文脈に依存することによって始めて、自らの当否を決定し得る場合、すなわち社会を解釈する行為は、あるコンテクストに依拠することによって始めて、自らの意味を決定し得るテクストの集合を解釈する行為に外ならない。 言い換えれば、社会の解釈とは、あるコンテクストを共に織り成している、テクストの束を解する行為に外ならないのである。 さらに言えば、この解釈する行為それ自身もまた、一篇のテクストに外ならず、何等かのコンテクストに依拠することによって初めて、自らの意味を決定し得る。 すなわち、解釈する行為それ自身もまた、行為である以上、何等かの文脈に依存することによって初めて、自らの妥当し得るか否かを決定し得るのである。 従って、社会を解釈する行為は、自らの対象とする社会、すなわち秩序付けられた行為空間とは差し当たり区別される、何等かの秩序付けられた行為空間に内属することになる。 すなわち、社会を解釈する行為は、それ自身もまた行為であるがゆえに、言わばメタ社会とでも呼ぶべき社会に内属せざるを得ないのである。 この解釈行為の内属する(メタ)社会と、解釈行為の対象とする(対象)社会とが、同一ではないとするならば、社会を解釈するに当たって特徴的な問題は生じ得ない。 言い換えれば、解釈行為の依存する文脈と、対象社会を秩序付ける文脈とが、異なるものであるとするならば、次節以降に述べるような問題は生じ得ないのである。 しかし、社会を解釈するという課題は、対象社会とメタ社会との峻別を、ついに許さない。 対象社会を秩序付ける文脈と、メタ社会を秩序付ける文脈とは、究極的には一致せざるを得ないのである。 何故ならば、秩序付けられた解釈行為の空間としてのメタ社会もまた、社会である以上、当然に解釈行為の対象となり得るのであって、社会の全体を解釈せんとする行為は、自らの内属する社会をも、自らの対象とせざるを得ないからである。 すなわち、社会の全体を解釈せんとするならば、対象社会は、メタ社会それ自体をも包含せざるを得ないのである。 従って、メタ社会を秩序付ける文脈、すなわち解釈行為の依存する文脈は、対象社会を秩序付ける文脈の一部分とならざるを得ない。 言い換えれば、社会全体を解釈せんとする行為は、自らの妥当し得るか否かを決定する根拠それ自体をも、自らの対象とせざるを得ないのである。 このように、解釈行為の対象となっている社会に内属する行為の妥当根拠が、同時に、解釈行為それ自身の妥当根拠でもある事態を、ブプナーに従って、自己関係的な事態、あるいは、自己関係性と呼ぶことにしよう。 すなわち、社会全体を対象とする解釈行為は、自らの根拠を自らの対象とせざるを得ないという意味において、自己関係性の構造を余儀なくされるのである。 もっとも、解釈の行為が、必ずしも社会の全体を対象とする必然はない。 従って、社会の部分を対象としている限り、解釈の行為が、自己関係性の構造を引き受けなくとも済む場合もあり得よう。 しかし、解釈の行為が、自らの内属する社会、すなわち秩序付けられた解釈空間それ自体を対象とする場合には、依然として、自己関係性の構造を避け得ない。 そのような場合とは、解釈の行為とその妥当根拠とを反省的に解釈する場合、言い換えれば、解釈学的な行為の遂行される場合である。 すなわち、解釈学的行為は、その対象である解釈行為の妥当根拠と、それ自身の妥当根拠が厳密に一致するという意味において、まさに自己関係性の構造を遂行しているのである。 従って、自己関係性の構造が問題とされるのは、社会全体を対象とする解釈行為の場合と、解釈行為それ自体を対象とする解釈行為、すなわち解釈学的行為の場合とに限られることになる。 このような自己関係性の構造、すなわち自らの妥当根拠を自らの解釈対象とする構造こそ、解釈学的循環と呼ばれる構造に外ならない。 言い換えれば、自らのコンテクストを自らのテクストとする処に、解釈学的循環が生じるのである。 解釈学的循環は、解釈学の全歴史を通底する根本構造である。 解釈学の主要なメッセージは、押し並べて、この解釈学的循環から帰結されると言っても過言ではない。 本論の以下の諸節もまた、この解釈学的循環あるいは自己関係性の諸帰結を検討することに費やされる。 そこでは、自己関係性の帰結として、批判理論と機能主義あるいは批判的合理主義の不可能であることが、明らかにされると共に、解釈学的循環の帰結として、保守主義あるいは伝統再生の不可避であることが、示される筈である。 ◆3.基礎付けの不可能自己関係性を引き受ける解釈行為、すなわち、社会全体を対象とする解釈行為、あるいは、自己自身の妥当根拠を対象とする解釈行為は、自らの妥当し得るか否かを、如何にして決定し得るのであろうか。 言い換えれば、自らの妥当根拠を対象とする解釈行為は、自らの妥当性を、如何にして根拠付け得るのであろうか。 たとえば、自らの妥当根拠に対する解釈を遂行して、そこには「自らの妥当根拠に対する解釈は妥当でない」という準則が含まれている、と解釈する場合を考えてみよう。 この場合、自らの妥当根拠に対する解釈が妥当であるとするならば、その解釈の妥当でないことが帰結され、逆に、自らの妥当根拠に対する解釈が妥当でないとするならば、その解釈の妥当であることが帰結される。 従って、この場合、自らの妥当根拠に対する解釈の妥当であるか否かは、全く決定し得ないことになる。 すなわち、自らの妥当根拠を対象とする解釈行為は、自らの妥当性を、全く根拠付け得ないのである。 このような決定不能性あるいは根拠付けの不可能は、自らの当否を自らが決定する構造、言い換えれば、自らを根拠として自らを正当化する構造の存在する処では、何処にでも生じ得るパラドックスである。 従って、自己関係性の構造の存在が、自らの妥当根拠に対する解釈の決定不能あるいは根拠付けの不可能を帰結するのは、このような自己決定あるいは自己正当化のパラドックスの、一つの例であるとも言い得るのである。 いずれにせよ、社会の全体を対象とする解釈の行為、あるいは、自らの妥当根拠を対象とする解釈の行為は、自らの妥当性の決定不能あるいは根拠付けの不可能に陥らさるを得ない。 言い換えれば、社会の全体を対象とする解釈の行為、あるいは、自らの妥当根拠を対象とする解釈の行為は、そもそも、合理的な行為としては成立し得ないのである。 社会の全体あるいは自らの妥当根拠を対象とする解釈の行為が、自らの当否を決定し得る、如何なる根拠をも持ち得ないという事態は、批判理論の遂行せんとしている、社会の全体あるいは自らの内属する社会を対象とする批判の行為が、必ずしも可能ではあり得ないことを示唆している。 すなわち、社会の全体あるいは自らの内属する社会を対象とする批判は、自らの妥当根拠それ自体をも批判の対象とせざるを得ず、そのような批判は、自らの妥当し得るか否かを、ついに決定し得ないのである。 言い換えれば、社会の全体あるいは自らの内属する社会を対象とする批判には、自らを妥当させる究極的な根拠など、決して存在し得ないのである。 従って、批判理論は、ついに可能ではあり得ない。 すなわち、社会の全体あるいは自らの内属する社会に対する、疑い得ぬ確実な根拠に基づいた、普遍妥当的な批判など、全く不可能なのである。 このことは、同時に、社会の全体あるいは自らの内属する社会を対象とする、合理的な言及や制御や変革やの、不可能であることも含意している。 何故ならば、社会の全体あるいは自らの内属する社会を対象とする、言及や制御や変革やの行為は、批判の行為と同様に、自らの妥当根拠を自らの行為対象とせざるを得ず、自らの妥当性を、全く根拠付け得ないからである。 すなわち、社会の全体あるいは自らの内属する社会を対象とする、言及や制御や変革やの行為は、合理的な行為としては決して成立し得ないのである。 言い換えれば、社会の全体あるいは自らの内属する社会は、合理的な言及や制御や変革やといった行為の対象とは、ついになり得ないのである。 従って、社会の全体あるいは当該行為の内属する社会は、言及/制御/変革不能という意味において、まさに暗黙的となるのである。 社会の全体あるいは制御行為の内属する社会が、制御不能であるということは、取りも直さず、社会の全体を秩序付けている文脈、あるいは、制御行為の依存している文脈もまた、制御不能であるということに外ならない。 すなわち、社会全体を秩序付ける文脈、あるいは、制御行為の依存する文脈は、暗黙的なのである。 従って、社会全体を秩序付ける文脈は、意図的に設定される事態ではあり得ない。 そのような文脈は、行為の意図にはよらず、行為の結果として、自生的に生成される事態なのである。 また、制御の行為は、自らの意識的には制御し得ない文脈に依存して初めて、自らの行為を可能にし得ることになる。 この制御行為の依存する文脈もまた、制御行為の遂行の累積的な帰結として、自生的に生成される事態なのである。 すなわち、社会全体を秩序付ける文脈、あるいは、制御行為の依存する文脈は、暗黙的なのである。社会全体を秩序付ける文脈、あるいは、制御行為の依存する文脈は、暗黙的であるがゆえに、ただ遂行的となるのである。 言い換えれば、そのような文脈は、意識的に語り得ないがゆえに、ただ遂行的に示されるのみなのである。 ◆4.《選択肢》の不在社会の全体あるいは自らの内属する社会を解釈する行為は、自らの当否を決定し得る、如何なる根拠をも持ち得ない。 自らの内属する社会を解釈する行為には、究極的な妥当根拠など、決して存在し得ないのである。 それでは、自らの内属する社会を解釈する行為に、言わば暫定的な妥当根拠を付与する試みは可能であろうか。 なるほど、自らの内属する社会への解釈に、究極的な妥当根拠など存在し得ない。 しかし、そのような解釈に、暫定的な妥当根拠を付与することによって、そのような解釈の、差し当たり妥当し得るか否かを決定することは可能ではないか。 ただし、ここに言う妥当根拠の暫定的であるとは取りも直さず、自らの内属する社会への解釈の、妥当し得るか否かを決定する根拠それ自体には、その妥当であるか否かを決定し得る、いかなる根拠も存在し得ない、ということに外ならない。 すなわち、暫定的な妥当根拠とは、解釈行為自らの内属する社会の解釈に、その妥当根拠を与えつつ、それ自体は、いかなる妥当根拠をも持ち得ない事態なのである。 言い換えれば、暫定的な妥当根拠は、自らの妥当根拠それ自体への遡行を、言わば中断することによって、解釈行為自らの内属する社会の解釈に、その妥当根拠を付与するのである。 自らの内属する社会への解釈は、このように、自らの妥当根拠を暫定的に付与されることによって、差し当たり、自らの妥当し得るか否かを決定し得るかも知れない。 従って、そのような解釈は、差し当たり、自らの妥当性を根拠付け得る、いわゆる科学的な言明として遂行され得るかも知れない。 しかし、そのような科学的言明の妥当性を根拠付けている、その妥当根拠は、あくまでも暫定的なものであって、自らの妥当性を根拠付ける、いかなる妥当根拠も存在し得ない。 科学的言明とは、さらなる根拠への遡行を中断することによって初めて可能となる、暫定的に根拠付けられた解釈の行為なのである。 それでは、自らの内属する社会への解釈を暫定的に根拠付ける、妥当根拠それ自体は、どのようにして与えられるのであろうか。 もとより、そのような妥当根拠それ自体には、いかなる妥当根拠も存在し得ないのであるから、そのような妥当根拠を、何等かの根拠に基づいて選択することは不可能である。 従って、そのような妥当根拠は、もし選択することが可能であるとするならば、いかなる根拠にも囚われない、いわば自由な決断によって選択されざるを得ない。 すなわち、暫定的な妥当根拠は、その選択可能を前提とするならば、解釈主体の自由な決断によって与えられるのである。 この意味において、科学的な言明とは、究極的には自由な決断に依存している行為に外ならない。 普遍的な妥当根拠の果てる処、自由な決断あるのみ、という訳である。 しかし、暫定的な妥当根拠を選択する、解釈主体の自由な決断が可能であるためには、そもそも、暫定的な妥当根拠それ自体を選択することが可能であらねばならない。 すなわち、妥当根拠が選択可能であるためには、妥当根拠についての、ある一つの選択に代替し得る、それ以外の選択肢が存在しておらねばならないのである。 ところが、社会の全体あるいは自らの内属する社会を解釈する行為の、暫定的な妥当根拠には、いかなる選択肢も存在し得ないことが示され得る。 すなわち、妥当根拠が選択可能であるためには、妥当根拠についての、ある一つの選択に代替し得る、それ以外の選択肢が存在しておらねばならないのである。自己関係的な解釈行為は、たとえ暫定的なそれであったとしても、些かの選択可能性も持ち得ないのである。 何故ならば、自己関係的な解釈行為においては、自らの行為の妥当根拠と、自らの対象の妥当根拠とが一致せざるを得ない。 従って、社会の全体なり、あるいは、解釈行為自らの内属する社会なりを、解釈の対象とするならば、自らの対象としての社会全体を秩序付ける文脈(妥当根拠)、あるいは、自らの対象としての自らの内属する社会を秩序付ける文脈(妥当根拠)それ自体を、自らの行為の依存する文脈(妥当根拠)とせざるを得ないことになる。 すなわち、社会の全体あるいは自らの内属する社会を対象とする解釈の行為は、自らの行為の妥当根拠として、自らの対象の妥当根拠以外の、いかなる選択肢も持ち得ないのである。 言い換えれば、自らの内属する社会を解釈する行為の妥当根拠は、些かも選択可能ではあり得ないのである。 従って、自らの内属する社会に対する解釈の妥当根拠を、解釈。主体の自由な決断に委ねることは、全く不可能となる 何故ならば、そのような解釈の妥当根拠には、選択肢が全く不在であるために、解釈主体による自由な決断の余地は、些かも残されてはいないからである。 このことは、科学的言明の妥当根拠(たとえば反証可能性基準)を、自由な決断に委任する、批判的合理主義の、必ずしも可能ではあり得ないことを示している。 すなわち、科学的言明の妥当根拠を、如何なる根拠にも囚われない自由な決断に委ねることによって、そのような妥当根拠によって秩序付けられた、科学的言明のゲームを展開せんとする、批判的合理主義の試みは、社会の全体あるいは自らの内属する社会を対象とする言明の妥当根拠に、如何なる選択肢も存在し得ないという事態によって、挫折せざるを得ないのである。 言い換えれば、批判的合理主義の含意する、科学的言明の妥当根拠それ自体についての相対主義、いわゆるパラダイム相対主義は、社会の全体あるいは言明行為自らの内蔵する社会を対象とするパラダイムに、選択可能性の全く不在であるがゆえに、失敗せざるを得ないのである。 従って、批判的合理主義によるパラダイムの選択は、全く不可能となる。 このことは、機能主義による社会システムの選択が不可能であることと、ほとんど同型的に対応する事態であると思われる。 社会の全体あるいは自らの内属する社会を解釈する行為の妥当根拠が、解釈主体の自由な決断によっては選択され得ないという事態は、そのような解釈の行為が、自らの対象とする社会を秩序付けている文脈から、ついに自由ではあり得ないことを示している。 すなわち、そのような解釈の行為は、自らの対象とする文脈、従って、自らの依存する文脈から、ついに離脱し得ないのである。 言い換えれば、解釈行為という(メタ)テクストは、自らのテクストでありかつ自らも織り込まれているコンテクストから、決して離脱し得ないのである。 そのようなコンテクストは、解釈の行為(メタ・テクスト)に先立って遂行されている、言わば先行的な解釈(テクスト)の累積であるとも言えよう。 従って、解釈の行為は、先行的な解釈に拘束されて初めて可能であることになる。 すなわち、解釈の行為とは、言わば先行解釈の地平に投げ出されて在る行為に外ならないのである。 ◆5.再び伝統とは何か社会の伝統あるいは自らの内属する社会を解釈する行為は、自らの妥当し得るか否かを究極的には決定し得ず、また、自らの妥当性を根拠付ける文脈を暫定的にすら選択し得ない。 言い換えれば、社会の全体あるいは自らの内属する社会を解釈する行為は、自らの対象とする社会を秩序付ける文脈を、究極的には操作し得ず、しかも、そのような文脈から、暫定的にすら離脱し得ないのである。 すなわち、解釈の行為が、自らの対象とし、従って、自らの依存する文脈は、究極的には操作不能であり、暫定的にも離脱不能である、何ものかなのである。 このような解釈行為の文脈こそ、伝統と呼ばれるものに外ならない。 すなわち、伝統とは、操作不能という意味において拘束的であり、解釈行為の遂行において従われる外はない事態なのである。 言い換えれば、伝統とは、解釈行為の語り得ず、ただ示し得る事態であると共に、解釈行為の逃れ得ず、ただ従うべき事態なのである。 従って、解釈の行為とは、このような伝統に従いつつ、このような伝統を示す、すなわち、伝統に依存しつつ、伝統を生成する行為に外ならないことになる。 言い換えれば、社会の全体あるいは自らの内属する社会を秩序付ける文脈、すなわち、伝統を解釈する行為とは、伝統から離脱するのではなく、伝統に依拠しつつ、伝統を操作するのではなく、伝統を再生する行為に外ならないのである。 このように、伝統に依拠しつつ、伝統を再生する行為の遂行を、保守主義と呼ばずして、一体、何を保守疑義と呼び得るのか。 すなわち、社会の全体あるいは自らの内属する社会を解釈する行為の遂行は、保守主義以外の何ものでもないのである。 社会の全体あるいは自らの内属する社会を解釈する行為は、伝統を普遍的に批判し得る根拠を持ち得ないが故に、伝統を生成し、また、伝統を自由に選択し得る選択肢を持ち得ないがゆえに、伝統に依存する行為であらざるを得ない。 すなわち、唯一可能な社会理論として、批判理論や機能主義と決別する解釈学的社会学の遂行は、取りも直さず、保守主義の外ではあり得ない。 解釈学的社会学の保守主義たる所以である。 社会の全体あるいは自らの内属する社会を解釈する行為は、伝統に依存しつつ、伝統を生成する行為である、という命題は、解釈学的社会学の根本命題である。 本論は、この根本命題の含意を、簡単にスケッチしたに留まる。 論じ残された問題は数多い。 たとえば、ある歴史的な社会を解釈の対象に据えた場合、その歴史的な社会を秩序付けている文脈と、解釈の行為の内在する社会を秩序付けている文脈とは、必ずしも常には一致しない。 従って、そこには、解釈の対象とする(対象)社会の文脈と、解釈の内蔵する(メタ)社会の文脈とが一致する、いわゆる自己関係性の構造は、必ずしも見い出されない。 しかし、そもそも、解釈の行為は、対象社会の文脈とメタ社会の文脈との間に、何等かの一致を前提することによって、初めて可能になるとも考えられるし、あるいは、それらの間に、何等かの一致を帰結することによって、初めて実現し得るとも考えられる。 すなわち、解釈の行為は、自己関係性の構造を、その前提とも帰結ともしているのではないか、と考えられるのである。 この場合、解釈を遂行する過程において、対象社会の文脈とメタ社会の文脈とは、どのように離反し、あるいは、どのように一致していくのか、このことが問われねばならない。 この問いは、解釈の遂行課程において、自己関係性の構造が、どのように生成されて来るのかを問うことに外ならない。 ガーダマーの言う、地平融合の問題である。 しかし、本論は、この問いに答えない。 解釈学的社会学の理論的彫塑は、今後の課題である。 解釈学的社会学が、伝統に依存しつつ、伝統を生成する行為に外ならないとするあらば、日本における解釈学的社会学は、日本の伝統を生成する行為を閉却する訳にはいかない。 もっとも、日本の伝統というと、即座に、古代以来の天皇制や、中世以来のイエ社会やを思い浮かべ、中国文明やあるいは近代文明の影響を受けていない、言わばナショナリスティックな伝統を考える向きがしばしば見受けられるが、ここに言う伝統は、必ずしもそのようなものではあり得ない。 日本において解釈学的社会学を遂行する場合、私の差し当たり対象としたい伝統は、17世紀ないし19世紀以降の近世あるいは近代日本の伝統である。 すなわち、近代文明の一翼を担う地域文化としての日本の伝統を対象としたいのである。 この間の事情は、ドイツにおいて解釈学的社会学の遂行される場合と大した違いはない。 ドイツの解釈学もまた、17世紀ないし19世紀以降の近代ドイツの哲学的な伝統を、差し当たり継承しているのである。 いずれにせよ、日本における解釈学的社会学を遂行するに当たって、差し当たり対象としたいのは、近世あるいは近代日本における哲学的な伝統である。 そのような伝統を解釈することによって、伝統に依存しつつ、伝統を生成する行為の一端を担ってみたいのである。 このこともまた、今後の課題に外ならない。 |
| + | ... |
第一章 世紀末の新しい保守主義 (省略) 第二章 合理と個体 (省略) 第三章 暗黙の言及 (*6) Polanyi, Michael ("Personal Knowledge"1958 長尾史郎訳 『個人的知識』1985) ハイエクは、ポランニーから多くの影響を受けている。 たとえば、自生的秩序の概念は、ポランニーから譲り受けたものである。 確かに、ハイエクは、ポランニーの暗黙知の概念を、言葉としては用いていないが、内容的には同様の考え方に立っている。 (*7) 橋爪大三郎 (『言語ゲームと社会理論 -ヴィトゲンシュタイン・ハート・ルーマン-』 1985) ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論から、ハイエクが直接の示唆を受けているか否かは定かでない。 従って、ここに言う家族的類似は、両者の理論が結果として類似しているという主張以上のものではない。 なお、ハイエクは、ウィトゲンシュタインの伝記を手掛けたことがあるそうである。 (他は省略) 第四章 規範の文脈 (*5) 土屋俊 (『心の科学は可能か』 1986) 自己言及性という概念の採用に当たっては、土屋(1986)に大きな示唆を受けた。 (*8) 土屋俊 (『心の科学は可能か』 1986) 文脈依存性という概念の採用に当たっては、土屋(1986)に大きな示唆を受けた。 (*18) 土屋俊 (「何種類の言語行為があるか -言語ゲームとしての言語行為-」 講座『思考の関数1 ゲームの臨界 -アゴーンとシステム-』 1983) 発語内行為の分類に関しては、土屋(1983)に示唆を受けた。 (他は省略) 第五章 慣習と遂行 (*1) Popper, Karl R. ("Objective Knowledge"1972 森博訳 『客観的知識 -進化論的アプローチ-』1974) 《世界Ⅰ》 《世界Ⅱ》 《世界Ⅲ》 の概念については、Popper に示唆を受けた。 (*2) これは、行為の累積的な帰結として生成される秩序が、何故に、行為の発効し得るか否かを決定する根拠すなわち、行為の依存する文脈となり得るのか、という問題である。 もし、行為の依存する文脈が、行為によって意図的に設定されるとするならば、そこには、自己言及あるいは自己回帰のパラドックスが生ずることになり、行為の発効し得るか否かは決定不能に陥らざるを得ない。 従って、行為の発効し得るか否かが決定可能である、すなわち、行為の依存する文脈が存在し得るとするならば、それは、たとえ行為の累積的な帰結として生成される秩序であったとしても、行為の意図的な設定にはよらないことが明らかになる。 言い換えれば、行為の依存する文脈は、もしそれが存在し得るとするならば、行為の累積的な帰結からは必ずしも独立していないにも拘わらず、行為の意図的な帰結からは全く独立しているのである。 (*3) 行為の発効し得るか否かを決定する根拠、言い換えれば、行為を根拠付けあるいは正当化する文脈に対する言及の総てが、自己言及あるいは自己回帰の行為となる訳では必ずしもない。 ある特定の行為秩序を正当化する文脈、すなわち、ある特定の社会ゲームを構成するルールに対する言及は、必ずしも自己に回帰する言及とはならず、ある特定の行為秩序あるいは社会ゲームを制御さらには設定する行為は常に可能である。 しかし、この場合、ある特定の文脈あるいはルールに言及する行為それ自身の依存する文脈あるいはルールは、差し当たり、言及の対象になっていない。 もちろん、ある特定の文脈に言及する行為を正当化する文脈それ自体に対する言及も、常に可能である。 しかも、そのような言及は無限に遡及し得る。 何故ならば、文脈あるいはルールの全体に言及する行為それ自身の依存する文脈あるいはルールに対する、新たな言及が、常に可能なのであるから、もとの言及は、文脈あるいはルールの全体を対象とする言及とは決してなり得ないのである。 このことは、文脈あるいはルールの全体に対する言及が、もし存在し得るとするならば、それは、自らを正当化する文脈あるいはルールそれ自体をも対象とする言及、すなわち、自己言及あるいは自己回帰の行為とならざるを得ず、そのような言及の発効し得るか否かを決定することは、すなわち、そのような言及の行為そのものが、原理的に不可能となるのである。 従って、ある特定の文脈によって正当化される行為秩序、あるいは、ある特定のルールによって構成される社会ゲームの制御さらには設定ならばいざ知らず、行為秩序あるいは社会ゲームの全体を対象とする制御さらには設定の行為は、原理的に不可能とならざるを得ない。 すなわち、行為秩序あるいは社会ゲームの全体に対する制御さらには設定は、自己回帰的な行為であらざるを得ないがゆえに、不可能となるのである。 (*4) 自生的秩序やルール、あるいは言語ゲームといった、《遂行的なるもの》は、行為の累積的な遂行としてのみ示されるという意味において、行為累積的である。 行為は、自らの文脈としての《遂行的なるもの》に、自らの発効し得るか否かを依存しているという意味において、文脈依存的である。 しかし、《遂行的なるもの》の全体を対象とする行為は、自らの依存する文脈をも対象とせざるを得ないという意味において、自己回帰的であり、自らの発効し得るか否かを決定し得ない。 すなわち、《遂行的なるもの》全体を対象とする行為は、自己回帰的であるがゆえに不可能なのである。 従って、行為の累積である《遂行的なるもの》に、行為が自らの発効し得るか否かを依存したとしても、《遂行的なるもの》の全体は行為の対象とはなり得ないのであるから、必ずしも矛盾は生じない。 言い換えれば、《遂行的なるもの》は、行為の累積的な帰結であるにも拘わらず、行為の意図的な対象とはなり得ないがゆえに、行為の規範的な文脈となり得るのである。 (*14) 累積的、規範的、暗黙的な事態としての《遂行的なるもの》と、社会との同一性は、本書に述べた社会哲学の最も基本的な命題である。 すなわち、社会は、《遂行的なるもの》と同様に、行為の累積的な遂行それ自体であるという意味において、累積的であり、また、行為の発効し得るか否かの依存する文脈であるという意味において、規範的であり、さらに、その全体を対象とする行為の自己に回帰するがゆえに不可能であるという意味において、暗黙的である。 保守主義は、累積的な伝統と、規範的な権威と、暗黙的な偏見との擁護し得ること、あるいは、擁護すべきことを見出すことによって、この意味における社会を、近代において初めて発見したのである。 保守主義のこのような捉え方は、保守主義を、言わば社会学として捉えることに外ならない。 言い換えれば、本書は、保守主義の伝統の中に、社会学の最良の部分を見出そうとする試みなのである。 なお、保守主義の社会学的な側面以外の諸相については、次節において簡単に検討したい。 (他は省略) 第六章 解釈学的社会学としての保守主義 (省略) |
タグ: