| ◇おしゃべり◇ |
| BBS |

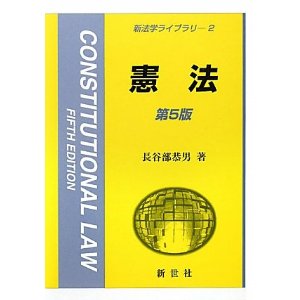 |
『憲法 第5版』 (長谷部恭男:著 (2011年)) |
| 長谷部恭男
は、故・芦部信喜(東大憲法学の最大の権威)門下の現代左翼を代表する憲法学者(東大法学部教授(憲法学)・元東大法科大学院長)である。 しかし師・芦部の憲法論が基本的には観念論的・形而上学的な(=存在証明の不可能なものを勝手にでっち上げている懸念の高い)大陸法学を引きずったままの修正自然法論・制憲権論に依っているのに対して、長谷部教授は、分析哲学(=哲学の役割は特定の観念体系の構築ではなくて、諸概念の分析・明晰化であるとする哲学潮流)を踏まえた英米系の法理論(ハートの社会的ルール説etc.)が世界的なスタンダードになって久しい状況に適応すべく、こうした師の修正自然法論・制憲権論を明確に否定する立場を鮮明にする一方で、なおこうした英米圏の法理論を憲法9条の改憲阻止を眼目とした護憲論に結びつける論説を近年盛んに発表しており、芦部に代わって左翼憲法論の新たなリーダーとなりつつある。(※参考ページ:政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価)。 長谷部教授の憲法論は、このように憲法の概念論(=憲法とは何であるか、という理解)としては芦部説より遥かにマシではあるが、そのもつ国家観・歴史観が結局のところ、ひと昔前の丸山眞男「日本ファシズム論」(戦前の日本は暗黒のファシズム国家であったとする戦後左翼が盛んに流布させた論説)に依拠したままであるために、憲法の理念論(=憲法はどうあるべきか、という理解。ことに日本の憲法典はどうあるべきか、という理解)に関して、戦後左翼的な歪みから脱却できていない。 |
| + | ... |
<目次>
◆1.1 憲法と国家◇1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法憲法(〔英〕 constitution, 〔仏〕 constitution, 〔独〕 Verfassung)という言葉はさまざまな意味で用いられる。 一般に行われる意味の分類としては、まず、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法という区分が重要である。 憲法の2つの意味
現在の我が国においては、「日本国憲法」という名称の法典がそれであるが、イギリスのように、形式的意味の憲法を持たない国もある。 また、ドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz fur die Bundesrepblik Deutschland)のように形式的意味の憲法であるにもかかわらず、歴史的な事情により、それが「憲法(Verfassung)」という名で呼ばれていない場合もある。 実質的意味の憲法の範囲を厳密に確定することは不可能であるし、そうする実益も少ない。 実質的意味の憲法の範囲は、形式的意味の憲法の内容とも、また憲法学の研究・教育の対象とも論理必然のつながりがないからである。 むしろ、重要なのは、すべての国家に必ず実質的意味の憲法があるのはなぜかという問題である。 それを解明するためには、国家の性質をまず考える必要がある。 ◇1.1.2 実質的意味の憲法と国家国家とは 国家については、それが主権、領土、国民の3つの要素から構成されると説明されるのが通常である(三要素説)。 国家といわれるものが、これら3つの要素を備えているという意味であれば、この言い方はあながち間違いではない。 領土のない国家や国民の全くいない国家は想定しにくい(もっとも主権については 1.2.3 の説明を見よ)。 しかし、主権、領土、国民という3つのものが寄り集まることによって国家が形成されるという意味であれば、それは誤解を招く表現である。 主権や領土も国民も、国家があって初めて存在し得るものだからである。 国家とは一体何だろうか。 株式会社や私立大学などと同様、国家は抽象的な存在であり、目に見えないし、手で触ることもできない。 目に見える形で存在するのは、たとえば国の象徴とされる旗、国の役所として使われている建造物、国の領土として存在する山や川などに過ぎない。 富士山や利根川は、自然の山や川であり、それが「日本の領土」であるのは、我々がそういう眼鏡をかけて、富士山や利根川を見るからである。 これらの背後に想定されている観念的な存在が国家である。 国家はなぜ行動できるか このように国家には実体がなく、従って、それ自身は目も口も、また手足も持たないので、「行動する」こともないはずである。 ところが、人々は、あたかも国家が人間と同じように意思を持ち、それに従って行動したり、他の国家と交渉を持つかのように考える。 とりわけ、国家は、会社や大学と違って、国民の自由や財産を強制的に奪い、ときには生命まで奪うことがある。 このように、人々が人間のアナロジーで国家の構造や行為を理解することが出来るのは、特定の個人の行為を、国家の行為として考えるという約束事があるからである。 実質的意味の憲法とは、個人の具体的行為を国家の行為として解釈するための最終的な拠りどころに他ならない。 言い換えれば、実質的意味の憲法は、誰が、如何なる手続で、如何なる内容の権限を国家の名において行使し得るかを定めるルールである。 徴税職員による税の徴収が強盗と異なるのは、前者が法律によって徴収の権限を与えられているからであり、法律がそのような権限を与え得るのは、国会議員と呼ばれる人々が憲法の定める手続に則って法律を制定したからである。 その結果、実際に行動しているのは徴収職員たる具体的人間であるにも拘わらず、我々は、国が税を徴収していると考えることになる。 議員や徴収職員、警察官や兵士のように、国家の名において行動する人間は、国家の「機関(organ)」と呼ばれる。 個人が口や手や足などの器官(organ)を通じて行動するように、国家という抽象的人格は、機関を通じて行動する。 私の手の行なったことが私の行為とされるように、機関と呼ばれる人々の行為は、国家の行為と見なされる。 国家の存在と実質的意味の憲法 このように、国家という約束事を成立させるための最終的な拠りどころが実質的意味の憲法であるならば、およそ、すべての国家にそれが伴っていることは当然である。 国家が存在するということと、実質的意味の憲法が存在するということは、同一のことを異なる言い方で述べているに過ぎない。 チェスが存在するということと、チェスのルールが存在するということが同じであることと事情は同様である。
◇1.1.3 国家の正当性に関する諸理論国家というものは、突き詰めれば我々の頭の中にしかない約束事であるから、その存在を認めないという考え方を採ることも出来る。 実際、アナーキストと呼ばれる人々は、国家の正当性を否定し、国家などない方が人々は幸福に暮らすことが出来ると主張する。 このように、考えようによっては、無くても済ませることが出来るのに、なぜ、人々は国家という約束事を受け入れているのであろうか。 ときにはこの約束に従って、個人の自由や財産、さらには生命までが強制的に奪われることを考えると、この疑問は切実となる。 この国家の正当性という問題には、古来、さまざまな回答が与えられている。 以下、その幾つかを見てみよう。 社会契約論 まず、社会契約論といわれる一群の議論によれば、人々は以前は国家のない状態、つまり自然状態で暮らしていたが、そこで起こる不都合を解決するために社会契約を結んで国家を設立したとされる。 そのため、国家の正当性も自然状態における不都合が何であったか、そして、社会契約がそれを如何に解決したかに依存することになる。 ホッブズ(Hobbes, T.)が『リヴァイアサン』において主張したように、自然状態における万人の万人に対する戦争状態を終わらせるために、人々はその自由を放棄して主権者への服従を誓ったのだと考えれば、国民の自由を否定する国家が正当化されることになる。 もし、個人の手元に自由を残せば、その限りにおいて、戦争状態が残されることになるからである。 戦争を終結させ、人々の生命と財産を守るためには、人々がその自由をすべて主権者に譲り渡すことが必要となる(ホッブズ [1992] 第2部)。 これに対し、ロック(Locke, J.)が『統治二論』において述べたように、国家は人々の利己的な行動によっては達成され得ない外交や防衛・警察などの公共サービスを行い、人々の生命や財産を保護するために設立されたのだと考えるならば、国家の行動範囲はこの公共サービスの提供に必要な限度を越えてはならないはずであり、とくに人々の生来の権利を侵さないよう、厳格に拘束されるべきこととなる(ロック [2007] 第2篇第9章)。 ロックの考え方は、現代の経済学の考え方とも通ずるところがある。 経済学の標準的な議論によれば、個人の自由な行動を通じて社会の福祉の最大化を実現する市場メカニズムが良好に機能している限り、国家は人々の行動に干渉すべきではない。 国家の介入が許されるのは、市場によっては効率的なあるいは公正な結果がもたらされない場合に限られる。 もとより、何がそのような場合にあたるかについては、時代により場所により、考え方の違いがある。 おおまかにいえば、近代初頭のヨーロッパにおいては、市場の機能が相対的に高く評価され、国家の任務は外交・防衛と国内の治安維持に限られるとの夜警国家思想が強かった。 しかし、現代の福祉国家においては、市場機構の機能不全がいろいろな点で指摘され、所得配分の是正や景気変動・経済成長の調整、道路・港湾・住宅などの社会資本の整備など国家に非常に広汎な任務が期待されるに至っている。 いずれにしても、個人の権利や利益を保障し実現するための手段として、国家に一定の正当な機能や任務を認める立場からすれば、国家の正当な活動範囲もそれによって限界づけられる。 国家がこの限界を超えて個人の自律的な領域に入り込むこと、とりわけ人生の目的や意義に干渉することは、個人の尊厳を侵すものとして禁じられる。 そして、現実の国家が与えられた機能や任務を適切に果たしていないことは批判の対象とされ、究極的には、法律への服従義務からの解放や、革命による新しい国家の設立が正当化されることになる。 共同体主義 これに対して、個人は特定の社会に所属し、その中で自己の位置に応じた役割を遂行することによってのみ人生の意義を掴むことができるという共同体主義に従うならば、社会全体の利益と競合する個人の利益はあり得ず、国家の栄光と繁栄は、各個人の人生の目標と一致することになる。 ヘーゲル(Hegel, G. W. F.)は、人間は自分があるところのすべてを国家に負っているのであって、「人間の持つすべての価値と精神の現実性は、国家を通していしか与えられない」と述べる(ヘーゲル [1994] 序論B(C))。 このような考え方は、国家は個人の利益を実現するための道具に過ぎないという啓蒙主義の中心的思想と対立する。 ヘーゲルが家族や職業団体の重要性に着目したように、共同体主義は、社会生活の絆となり人生に意義を与えるものとして国家と個人の間に位置する中間団体を重視する。 そして、個人主義の提唱する個人の自律が、実は何の指針をも与えない否定的で無内容な自由に過ぎず、虚無的な秩序の破壊をもたらす危険を指摘する(ヘーゲル [1978] §5 参照)。 ◇1.1.4 法の3つの役割本書は、国家の必要性と正当性は、国家や民族あるいは社会等の集団そのもの持つ価値からではなく、個人の権利や利益から導かれるとの考え方から出発している。 ここでは、国家の主要な任務として、3つのものを取り上げて説明する。 第一は調整問題の解決であり、第二は公共財の提供であり、第三が人権の保障である(長谷部 [1991] 第3章参照)。 第一と第二の任務は、なぜ国家の存立が正当視されるかを説明し、第三の任務は、いったん成立した国家がもたらす危険へ対処する工夫を国家組織自体の中に組み込むべきことを説明する。 (1) 調整問題の解決調整問題とは 世の中には、どれでもよいが、とにかくどれかに決まってくれなければ困る事柄、つまり調整問題(coordination problem)が沢山ある。 車が道の右側を通るべきか左側を通るべきか、について、事々しく議論をしても仕方がない。 むしろ、どちらかに決まっていること、そしてすべての人がその決定に従うことが肝要である。 複数の選択肢が想定できるとき、とにかくその中のどれかに決まっていることですべての人が利益を得られる問題は世の中に無数にある。 礼儀作法や言葉遣い、文法規則のように、慣習が決めている問題もあるが、法が適切に決定し得る事柄もある。 市場取引のルール 遺言をするために証人が要るか否か、小切手を振り出すには何を記入すべきかなどの財産権や契約法上のルールも、調整問題を解決する法の例である。 市場取引を成り立たせるルールが何等かの形で決められていれば、そのルールを前提としたうえで、人々は互いに他者の行動を予測しながら、自己の利益の最大化を目指す計算を行うことが可能となる。 市場における自由な行動を通じて社会全体としての利益も増大するはずである。 (2) 公共財の提供ただ乗り問題 法が解決すべき問題は、いったん解決されると万人が等しく利益を得る調整問題だけではない。 警察による治安サービスを例にとると、自分は腕に覚えもあるし盗まれるほどの財産もないから、警察を養うための税金など払いたくないという人からも税金を徴収しなければ、多くの人は同様の理由をつけて税の支払いを免れてただ乗りをしようとするため、財政的に警察組織は維持し得なくなり、その結果、生ずる治安の悪化は、すべての人に不利益をもたらすであろう。 このように警察、消防、環境保全などの公共財といわれるサービスは、経費を負担しない人もその恩恵に与かることができるため、人々が自分の目先の利害のみを眼中に置いて行動する市場を通じては、適切に供給されない。 そこで政府が法制度を通じて公共財を提供し、その費用は税金として、社会全体から公平にかつ強制的に徴収することになる。 公共財の供給と民主主義 どのような公共財をどの程度、提供すべきかは、国民が社会全体の長期的な利害を勘案しながら、投票を通じて多数決で決めるべき事柄である。 多数決で敗れた少数派も、政府が公共財を提供しない場合に比べれば、不満の残る決定でも従った方が有利であるし、少数派と多数派をあわせた社会全体の利益は、多数決に従うことで最大化する。 (3) 人権の保障以上の2つは、万人が同様に利益を得るか、多数派と少数派とで利害が対立するかの違いはあれ、社会全体にとっての利益が問題となる状況である。 これに対して、第三の人権の保障は個人の自律にかかわっている。 個人の生まれながらの権利 - 人権 人々が日々の生活の中で下す決定の中には、他の誰でもなく、その人自身が自由に決めるべき事柄がある。 朝食の献立やテレビ番組は何を見るかという趣味や好みの問題から始まって、自分の進路の如何や尊厳死を選ぶか否かという世界観や人生の目標の問題にいたるまで、社会の慣習も議会の決定も左右し得ない事柄は多い。 人の生まれながらの権利、つまり人権という観念は、個人が決めるべき事柄に、社会や政府を含めた他者は介入し得ないはずだという考え方に支えられている。 人は根源的に平等であり、自分の生き方を決めるのは自分自身でしかない。 その決断を通じて、人はその人生に自ら意味を与えていく。 社会全体の利益が、このような意味での人権の制約を正当化することはあり得ない。 逆にいえば、人権には、社会全体の利益を理由とする政府の行為の正当性を覆す「切り札」としての働きがある。 人生観や世界観について、根底的に異なる考え方を抱く人が共に暮らす現代社会において、たとえ社会の多数派の支持があったとしても、政府が特定の価値観に基づいて個々人の生き方に介入するならば、それが政府の公正な活動として受け入れられることはなく、かえって深刻な社会的対立を生み出すであろう。 多数派と異なる価値観を抱く人を平等な個人として承認していないことを意味するからである。 「切り札」としての人権をすべてのメンバーに平等に保障することは、価値観の相克する社会で、それでもなお人々が社会生活の便益とコストを公平に分かち合うことを可能とするための基本的な枠組みとなる。 国家と人権保障 このような人権を法によって保障する必要が生まれるのは、国家が存在するからこそである。 調整問題状況や公共財の供給の必要から、人々が国家という約束事を正当視し、その法に従おうとするとき、逆に、国家がその正当な権限を超えて人々の生来の人権を侵害する危険が生まれる。 国家は、その領域内における正当な実力の行使を独占しており、国民の生命・自由・財産を奪い取る力を持っているため、その権限を限定する必要性も大きい。 権力の分立、政治部門から独立した裁判所による違憲審査制度や人権保障という工夫が要請される最大の理由はそこにある。 ◆1.2 立憲的意味の憲法◇1.2.1 近代立憲主義市民革命と近代立憲主義 実質的意味の憲法の内容は、国家によってさまざまである。 一人の独裁者の命令がそのまま国家の意思と見なされ、それによって強制的に国民の自由や財産が奪われるような内容であることもあろう。 これに対して、17世紀から18世紀にかけて、欧米諸国で起こった市民革命をきっかけとして、憲法は、権力者の恣意を許すものであってはならず、個人の権利と自由を保障するために、そしてその限りにおいて国家の行為を認めるものであるべきだとの考え方が確立した。 この近代立憲主義と呼ばれる思想は、国家の任務を個人の権利・自由の保障にあると考えるが、その任務を果たすために強大な権力を保持する国家自体からも権利と自由を守らねばならないとの立場をとり、このような目的に即して、国家機関の行動を厳格に制約しようとする。 そして、このような考え方に立脚した憲法を、立憲的意味の憲法、あるいは近代的意味の憲法と呼ぶ。 「すべての権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない国家は憲法を有しない」(フランス人権宣言16条)といわれるときは、このような意味で憲法という言葉が使われている。 近代的意味の憲法においては、多くの場合、国家の任務と限界を示す権利が権利宣言という形で成文化され、他方、権力の乱用を防ぐために、統治機構についても権力分立や法による支配など、さまざまな組織上の工夫が施されている。
なお、以下で説明するように、国家が保護すべきものとされる「自然権」と実定憲法において保障されるべき「憲法上の権利」ないし「基本権」とは、必ずしも一致しない。 ◇1.2.2 近代憲法から現代憲法へ近代憲法の特徴 近代立憲主義が確立した当初の憲法においては、権利宣言においても、思想・信条の自由、表現の自由、人身の自由、財産権の保障などの個人の権利を国家権力に対して防衛するという色彩が濃く、団体行動の権利や社会権は、ほとんど顧みられていない。 また、統治機構の面でも、国民の代表によって制定された法律によって行政権および司法権を厳格に拘束しようとする考え方が強く、立法権そのものを拘束しようとする考え方はあまり見られなかった。 さらに、当時は、参政権も納税額や性別によって限定されており、「教養と財産(Bildung und Besitz)」を有する市民層という国民の限られた部分の意見が議会に強く反映する構造になっていたことも見逃してはならない。 現代憲法への転換 強要と財産を持つ人々による政治という考え方から、できるだけ多くの人々が国政に参加すべきだとの考え方への転換が行われたのは、ヨーロッパにおいても19世紀後半から20世紀初めにかけてのことに過ぎない(その背景には、主要各国の軍事戦略の転換がある。この点については、長谷部 [2006] 第4章参照)。 そして、選挙権の拡大とともに、国家が大衆の要求に応ずる必要が生じたこと、また他方で、社会主義思想が、近代憲法の保障する人権が単に形式的な自由と平等を保障するにとどまり、真に人間らしい生活を保障する役割を果たしていないとの主張を広めるに従って、国家の任務と限界に関する考え方も大きな変化を遂げた。 ドイツのワイマール憲法やフランス第四共和政憲法など、第一次大戦以降にヨーロッパ諸国で制定された諸憲法の権利宣言においては、従来の個人レベルの自由権と並んで、集会の自由・結社の自由のような集団的自由権、労働者の団結権・団体交渉権・争議権のような労働基本権が保障される他、最低生活の保障や勤労権、教育権など、実現のために国家の積極的な介入を要するような権利も謳われている。 日本国憲法も、これらの点で例外ではない。 また、権利宣言として成文化された権利のカタログに示されない領域でも、国家には、景気変動や経済成長の調整、社会資本の整備など、積極的な役割が期待されている。 次に、憲法による制約の対象についても考え方の変化が見られる。 現代社会においては、国家権力とそれ以外の社会的権力、つまり大企業や政党、労働組合、私立大学などの違いは絶対的なものではなく相対化しており、従ってこれらの社会的権力の行為も憲法による直接あるいは間接の制約の対象にすべきだとの見解が主張されている。 統治機構への影響 以上のような近代憲法から現代憲法へ、言い換えれば、夜警国家から福祉国家への国家観の変容は、統治機構の面でも重大な変化をもたらしている。 まず、福祉給付行政に見られるような行政裁量の拡大は、議会立法による行政権の厳格な拘束という法の支配(1.2.5 参照)の理念を後退させる状況を生み出した。 また、政府の活動領域の拡大は、政府が産業界や労働界をはじめとする社会内のさまざまな利益集団と協議する必要を生み出し、国会を通じて国民の利益が一元的に代表されるとの近代憲法の建前に反して、多様で個別的な利害が政府と直接に交渉する特権を得る状況をもたらしている。 他方、大衆の政治参加に伴って成長した政党組織は、議会内での議員の規律を強め、その結果、政党の領袖からなる内閣による議会の支配を現出した。 選挙権者の数が限定されていた近代社会においては、地方の名望家が独自の資金と組織によって当選し、議会内で緩やかな議員組織を形成していたが、現代の普通選挙制度の下では、政党の政策・組織・資金に頼らない限り、議員の地位を獲得することはきわめて困難となり、そのため党組織への議員の従属が見られる。 さらに、戦間期から第二次大戦中のファシズムの経験から、立法府による侵害から国民の権利を守る制度が必要だとの考え方が強まり、戦後、多くの国で違憲立法審査制度が導入されることとなった。 ◇1.2.3 国民主権主権とは 主権という言葉の主な用法としては、
統治権という意味の主権の用例としては、ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ極限セラルベシ」がある。 統治権の最高独立性を示す主権の用例としては、憲法前文3項における「自国の主権を維持し」がある。 これに対し、日本国憲法前文で「主権が国民に存する」といわれ、1条で「主権の存する日本国民」といわれる場合には、③の意味の主権が国民に帰属することが述べられている。 国民主権の内容 国民主権の原則は、
前者は、国民主権の権力的契機、後者は、国民主権の正当性の契機といわれることがある。 君主主権の下においては、君主自身が統治権のかなりの部分を行使し得たために、権力的契機と正当性の契機とは重なり合っていたが、国民主権の下においては、市民が常時政治に直接に参与することは不可能であるため、両者は乖離し、正当性の側面が強調されることになる。 国民主権の原理が、国民の実際の政治参加をどの程度まで要求するかについては、代表制の観念とも関連して議論の対立が見られる(12.1.1 参照)。 主権概念の見直し 国家の主権および国家における主権は、唯一不可分で最高独立であり、無制約であるという考え方が伝統的には支配的であった。 しかし、実際には、連邦国家のように中央政府と各州政府に統治権が分割されることもあるし、違憲審査制によって国民を代表する議会の立法権が裁判所によって制約されることもある。 また、国際的な慣行や条約によって国家の行動が制約されることも珍しくない。 主権が無制約であるとの考え方は、権力分立や違憲審査など、さまざまな制度によって国家権力を制約しようとする近代立憲主義の考え方と正面から対立する。 「国民主権」の原理が国民の政治参加を広範に要請するという前提をとったとしても、そうして政治過程に参加する国民は、さまざまな制度の枠組みを乗り越えて無制約に国政を決定し得るわけではない。 主権が唯一不可分で無制約であるとの考え方にさほど理由がないとすると、国家という単位で法のあり方を考えることも必然的ではないことがわかる。 1.1.4 で述べた法の役割を、国際的な法や組織が効果的に果たすのであれば、国家を単位として社会生活を規律することに必ずしもこだわる必要はない。 地球環境の保全や国際平和の維持という公共財は、個々の国家を超えるルールや組織を要求するであろうし、地域ごとの実情に応じた統治権の行使は地方政府への大幅な権限の委譲を正当化するかも知れない。 「国民主権」の下で、市民の直接の政治参加をどのような制度的枠組みの下で、どこまで認めるのが妥当かも、1.1.4 で述べた法の役割をどのような制度が適切に果たすかという視点から検討する必要がある。 主権という概念に基づく議論の限界に留意し、この概念にあまり多くのものを読み込み過ぎないようにしなければならない(長谷部 [1999] 第5章)。
◇1.2.4 権力分立原理の変容権力分立の原理は、モンテスキュー(de Montesquieu, C. L.)によって確立されたと考えられている。 『法の精神』(1748)で示された彼の理論は、当時のイギリスの政治体制をモデルとして組み立てられており、その内容は、権力集中の排除を目的とする消極的原理と権力の抑制均衡を狙う積極的原理の2つに区分することができる(モンテスキュー [1987] 第11篇第6章)。 権力集中の排除 まず、消極的原理は、国家の統治権を、立法・司法・執行の三権に区別し、そのうち2つ以上が、1つの機関によって独占されないよう、政治体制を構成する必要があるとする。 このような独占は、専制政治、つまり人々の自由の抑圧をもたらすからというのがその理由である。 確かに、立法機関と法を具体的な場面に適用する機関とが融合すれば、個別の事情やその時々の考慮によって法は伸縮自在に適用されることとなり、あらかじめ定められた一般的な法に従って予見可能な形で国家権力が行動するという「法の支配」は失われることになる(1.2.5 参照)。 司法権と執行権とが融合した場合にも、立法権の定めた法による拘束は名目的になり、同様の専制がもたらされるおそれが強い。 権力の抑制均衡 もっとも、国家権力の集中を排除する消極的な原理だけでは、憲法の構成原理として不十分であり、モンテスキューは、積極的な原理として、権力の抑制均衡の仕組みを提唱する。 これは、司法や執行を支配する最高の権能である立法権の構成に関する原理である。 モンテスキューによれば、当時のイギリスの立法府は、市民階級の代表からなる庶民院、貴族からなる貴族院、さらに立法裁可権を有する国王の三者から構成され、三者すべての合意がない限り、新たな法律が制定されない仕組みになっていた。 執行権を有する国王が立法裁可権を持つことにより、議会が執行権を簒奪するような法律を制定することを防ぐことができる。 また、三者のすべての同意がない限り法律が制定されない以上、制定された法律は、すべての社会階層の利益にかなう、自由を守る法律であるはずである。 モンテスキューの発想にならって行政権の首長に立法拒否権を認めた憲法として、フランスの1791年憲法やアメリカ合衆国憲法がある。 現代の権力分立 もっとも、モンテスキューが権力分立の原理を提唱したのは、国民主権の原理が確立せず、君主や貴族階級がなお大きな政治的発言権を有していた制限王政時代のイギリスをモデルにしてのことであった。 このような時代を背景とする権力分立論が果たして現代国家でも有効であり得るかが問題とされねばならない。
このような現代の権力分立が提起するおそらく最大の問題は、国民主権原理との関係である。 議会が、主権者たる国民の直接の代表であることを考えれば、なぜ行政権や裁判所がそれに従属することなく、かえって、ときには議会の行動を抑制し得るのかが問われることとなる。 このうち、行政権に関する限りでは、日本は議院内閣制度を採用していることから、機構上、行政権を担当する内閣が議会の多数派と行政権とは実は融合していることを示しており、その限りで権力分立原理は変容を被っていることになる。 ただ、議院内閣制の下では、内閣が辞職の自由を持つことと、場合によっては自己の政策の是非を有権者に問うために議会を解散し得る点で、行政府が議会の意思に無原則に従う議会統治制よりは、内閣の独自性が保たれているといえよう(13.1.1 (2))。 しかし、内閣総辞職の後、あるいは解散-総選挙の後に組織される新内閣は、議会多数派の意思を反映していなければならない。 フランス第五共和政やアメリカ合衆国では、行政権の長である大統領が、議会と同様に、有権者を直接に代表するという形で、権力分立と国民主権との整合性が図られている。 分立原理の変容 もっとも、行政権が立法権と対抗し得る存在と考えられるに至った実質的な理由は、モンテスキューの時代と異なり、現代の行政権が単なる法律の執行にはとどまらず、立法活動自体の指導をも含む統治活動を担当しているからである(13.1.2 (1))。 国家に最小限の役割のみが期待されていた時代においては、各身分の既存の権利が新たな法律によって侵害されない仕組みを作り出すことが肝要であった。 これに対して、国家の役割が増大した今日においては、行政権の担当する統治活動を民主的にコントロールすることが重要な課題となる。 議院内閣制や大統領の公選制も、このような視点からその意義を理解する必要がある。 他方、裁判所については、伝統的には、司法は法律を個別の事件にあてはめて、それを解決するだけであり、裁判官の個人的な良心や倫理観がそこに介入する余地はないと考えられてきた。 従って、司法が正しく運営されるためには、政治部門の介入を排除し、法律の忠実な適用を保障しなければならないこととなる。 そこから、裁判官の職権の独立や身分保障の必要が説明される。 もっとも、実際には、法の解釈適用において、裁判官の個人的な考えが全く働かないということはあり得ない。 とくに、抽象的な憲法の条文の解釈に基づいて、国民を代表する議会の制定法の効力を審査する違憲審査制度を如何にして正当化できるかが、議論の焦点となっている。 議会を含む民主的な政治過程そのものの正常な機能を維持するため、あるいは個人の自律を多数決による政策的決定から守るために違憲審査が要請されるという議論など、さまざまな考え方が提示されている(14.4.8. 参照)。
◇1.2.5 法の支配法の支配は、国家機関の行動を一般的・抽象的で事前に公示される明確な法によって拘束することにより、国民の自由を保障しようとする理念である。 法の支配の内容 「人の支配」ではなく、「法の支配」を実現するためには、何よりもそれが従うことの可能な法でなければならず、法に基づいて社会生活を営むことが可能でなければならない。 そのためには、①法が一般的抽象的であり、②公示され、③明確であり、④安定しており、⑤相互に矛盾しておらず、⑥遡及立法(事後立法)が禁止され、⑦国家機関が法に基づいて行動するよう、独立の裁判所によるコントロールが確立していること、が要請される(長谷部 [2000] 第10章)。 このような法の支配の要請は、法令の公布に関する規定(憲法7条1号)や憲法41条の「立法」の概念、司法の独立(憲法76条以下)の他、憲法31条以下の諸規定に具体化されている(8.3.2. (3) 【法の支配との関係】 参照)。 「善き法」の支配 法の支配は、「善き法」の支配と同視されることがある。 形式的法治国と実質的法治国の概念を対置し、法の支配を後者と同視する考え方もその一例である。 また、個人の尊厳や基本的人権の保障、国民主権など、近代立憲主義の諸要請がすべて法の支配に含まれるとする者もいる。 しかし、このように法の支配を濃厚な意味で理解してしまえば、この概念を独立に検討する意義は失われる。 確かに、法の支配の内容とされる法の一般性・抽象性・明確性・安定性、および遡及立法の禁止は、法が法として機能するための、つまり法が人の行動の指針として機能するための必要条件である。 立法が個別的にしかも事後的に為され、法の文言も不明確であり、しかも朝令暮改のありさまでは、人々は国家機関の行動について如何なる予測を立てることもできず、そのため法に従って行動することは不可能となるであろう。 しかし、人種差別立法や出版物の検閲制度を設定する法も、やはり法として機能するためには、これらの特徴を備えている必要がある。 これらの特徴はいずれもそれ自体としては、悪法の支配とも十分に両立し得る。 また、前述のような法の支配の内容は、法が民主的に定められるか否かとは関係がない。 法が法として機能するために、今掲げたような幾つかの条件が必要であることが、法と道徳との必然的なつながりを意味するといわれることもあるが、これも誤りである。 切れ味の良いことがナイフの道徳性を示していないのと同様、法が法として機能するための条件を備えていることは、法の道徳性を示していない。 今述べたとおり、きわめて不道徳な目的を持つ法も、法として機能するためには、このような条件を備えていなければならない。 法の支配の限界 さらに、法の支配は、法が備えるべき条件の一つに過ぎず、他の要請の前に譲歩しなければならない場合もあることに留意しなければならない。 法の支配の要請がどこまで充足されるべきかは程度問題であり、個別の企業を国有化するための立法や女性のみを保護対象とする労働立法も、一般抽象性の点で悖(もと)るところがあるとしても、政府の役割の拡大した福祉国家の下においては肯認され得るであろう。 法の支配を支える根拠となる個人の自律や社会の幸福の最大化という目的自体が、国家の役割の拡大をもたらしているからである。
◇1.2.6 硬性憲法改正手続による区分 憲法が通常の法律よりも厳格な手続によらなければ改正出来ない場合、それを硬性憲法と呼び、通常の法律と同様の手続で改正し得る場合、軟性憲法と呼ぶ。 硬性憲法と軟性憲法の区別は、ブライス(Bryce, J.)によって為されたもので、彼は、成典か否かの区別を前提とせずに、憲法一般にこの分類をあてはめた(J. Bryce [1901] pp.128-33)。 一国における実質的意味の憲法がすべて成典化されることは実際上あり得ず、従って、それがすべて硬性化されることもあり得ない。 硬性憲法の国か軟性憲法の国かの区別は、その国に硬性の憲法典があるか否かの区別として捉えられるべきである。 現在のイギリス、建国当初のイスラエルなどが、軟性憲法の国家の例として知られる。 硬性憲法の特長 近代立憲主義は、一般に憲法の成典化とその硬性化とを推し進めた。 国家機関への拘束と人民の権利の内容を成典化し、明確にすればその遵守を期待することが出来るし、そうして生まれた成典憲法を、通常の法律より厳格な手続でしか変更できない憲法とすれば、そのときどきの議会多数派の手から少数者の権利や社会生活の基礎となる価値を保障することが出来、また改正手続に国民投票を取り入れることで、国民の意思を憲法に反映すると同時に、憲法の正統性を強めることも可能となる。 さらに、連邦国家においては、連邦を構成する各州の承認が改正のために必要となる。 もっとも、憲法改正手続が厳格であることは、必ずしも実際の改正が困難であることを意味しない。 改正が為されるか否かは、政治情勢や憲法擁護に対する国民の考え方にも大きく依存する。 他方、改正が困難であると、実際の状況に合わせて不文の慣習が補充的にあるいは憲法典に反する形で成立することがある。 しかし、憲法典の解釈が柔軟に為されるならば、憲法典が同一のままであっても、さまざまな状況の変化に対応することが可能となる(1.3.4、1.3.5 参照)。 日本国憲法は、硬性の憲法典であり、改正のためには、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民の承認とが必要とされる(1.4.1 参照)。
◇1.2.7 憲法の尊厳的部分と機能的部分憲法の2つの部分 近代立憲主義が国民の権利・自由を保障するうえで、議会・内閣・裁判所などの国家機関の仕組みや権限に着目するのは、これらの機関こそが国家権力の実際の担い手であると考えるからである。 この前提は、現代社会において権力が行使される状況を正確に反映しているであろうか。 バジョット(Bagehot, W.)は、『イギリス憲政論』(1867)の中でイギリスの国家体制を分析する際、憲法の尊厳的部分と機能的部分とを区別した。 前者は、国民の崇敬と信従を喚起し、維持する部分であり、後者が実際の統治に携わる。 バジョットによれば、当時のイギリスの国家制度のうち王室や貴族院は前者であり、庶民院や内閣は後者にあたる(バジョット [1970] 第1章)。 現代憲法の機能的部分 この区別に即して現代の日本の政治制度を分析するとどうなるだろう。 天皇制は明らかに尊厳的部分に属しているが、さらに、唯一の立法機関とされる国会や行政権を統括するはずの内閣も、次第に尊厳的部分へと追いやられているように見える。 実際に統治活動の中心にあるのは、大部分の法案を準備し予算案を編成する中央官僚機構と、財界・産業界・各種圧力団体の要請と支援を受け、ときには外国政府の圧力を受けて官僚の活動に影響力を行使する政権政党である。 そして、統治活動の態様も、法律およびそれに基づく国民の権利自由の制約ではなく、補助金の交付や行政指導、人員の派遣など、法的コントロールに馴染みにくい形をとることが増えている。 このような憲法の機能的部分の活動を厳格な法のコントロールの下に置くことは、とりわけ行政活動の肥大した現代国家では難しい。 それは、彼ら自身が立法・行政活動の主体でもあり、そうである以上、法的措置をとる以前に、他の方法で所期の効果を達成することができるからである。 いずれにしろ最後は法的措置を取られると分かっている以上、相手方も長期的観点からなるべくコストがかからず、摩擦の少ない形で機能的部分の要求に対処しようとするであろう。 機能的部分に対する制約 もちろん、機能的部分に属する人々も全く無制約で活動するわけではない。 数年ごとに行われる国政選挙のため、有権者の意思を無視することは許されない。 従って、世論に影響を与えるマスメディアの批判も大きな効果を持つ。 また、機能的部分の権力の主要な源泉が、国会や内閣など憲法の尊厳的部分の活動をコントロールし得る点にある以上、国会や内閣の活動を規律する憲法典、各種の法令および慣習は遵守せざるを得ない。 もっとも、これらのルールは、そのすべてが裁判所によって強行されるわけではないため、彼ら自身によって承認されている限りにおいて、彼らの行動を縛るという性格は残る。 裁判所の違憲審査権が行使される場合でさえ、最終的な有権解釈権者たる最高裁判所によって解釈された限りにおける憲法が適用されるに過ぎない。 権力の拘束を使命とする憲法は、究極的には、権力者自身によって受け入れられている限りにおいて、権力を拘束することができる(この点については 1.3.3、1.4.2、1.4.3 を見よ)。 もちろんそうは言っても、憲法と現実の距離には許容限度があろう。 憲法を単なる神話として軽視することは、機能的部分の権力の基礎を掘り崩すことになる。 機能的部分の機能性もその神話によって支えられているからである。 ◆1.3 憲法の法源と解釈◇1.3.1 成文法源と不文法源法源という言葉も様々な意味で用いられるが、広義では、法の存在形式を指す。 実質的意味の憲法が国法体系においていかなる形をとって現れるかにより、各種の法源が存在することになる。 このうち、憲法典、条約、法律など成文化されたものを成文法源、慣習、判例などのように成文化されていないものを不文法源と呼ぶ。
後述するように(1.3.4)、判例については、それが狭義の法源にあたるか否か、そして慣習については、それが最狭義の法源にあたるか否かが問題とされている。 ◇1.3.2 日本国憲法主な成文法源としては、憲法典である日本国憲法、さらには国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法、皇室典範などの法律の他、衆議院規則、参議院規則、最高裁判所規則などがある。 このうち最も重要なものは日本国憲法であり、実質的意味の憲法のうち極めて重要な部分が、この法典によって定められている。 日本国憲法は近代立憲主義の系譜に属しながら現代的な特質をも備えた硬性の憲法典であり、前文と全11章からなる本文とによって構成されている。 前文については、これを単なる政治的宣言と見なし、その法源性を否定する見解み見られるが、少なくとも立法や解釈の指針としての役割は果たし得るとする見解の方が有力である。 法源性を否定する根拠としてしばしば掲げられるのは、前文の規定の抽象性であるが、そのことだけを取ってみれば、本文の規定についても同様に当て嵌まる事柄である。 また、前文の改正には96条の定める手続を踏むことが必要であり、その限りで憲法典の一部たる性格を失わない。 ◇1.3.3 最高法規憲法の最高法規性 憲法98条1項は、日本国憲法を「国の最高法規」とし、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」は「その効力を有しない」と定める。 ここにいう最高法規とは、形式的効力において最高の法という意味である。 憲法の条文自体あ、このように定めているというだけでは、憲法を最高法規とする根拠として不十分である。 「私は正直者です」という者が、必ずしも正直者とは限らないことと、事情は同様である。 通常は、96条の定める改正手続の硬性と81条が明定する違憲審査制とが、憲法の最高法規性を制度面で裏付けているとされる。 また、97条の述べる基本的人権の性格は、前文並びに1条、9条で明らかにされた国民主権主義および平和尊重主義と相俟って、憲法が最高法規たる実質的理由を基礎づけているとされる。 法の運用者による受容 もっとも、日本国憲法が硬性の改正手続や違憲審査制の設置などの制度的特徴を備えていること、そして、日本国憲法がその内容において、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義などの正当な原則を掲げていることは、日本国憲法の日本における最高法規性を直接に基礎づけるわけではない。 この種の正当性を標榜する法文は世界に数多く存在するが、当然のことながら、それらのすべてが日本の最高法規と見なされてはいない。 日本国憲法が日本の最高法規である直接の理由は、日本社会において法の運用に携わる人々-官僚、裁判官、議員等-が、「日本国憲法を最高法規として扱うべし」というルールを受け入れ、それに則って行動しているからである。 つまり、日本国憲法が国の最高法規なのは、「日本国憲法を最高法規として扱うべし」という実質的意味の憲法が事実上存在するからであり、そのような実質的意味の憲法が存在するのは、それを法の運用者が事実上受け入れ、それに則って行動するからである。 もちろん病理的な政治体制を除くと、法の運用者によって受け入れられているルールは、社会の大多数のメンバーによっても受け入れられているであろう(ハート・法の概念第6章参照)。 法の運用者になぜそのようなルールを受け入れるのかと問えば、日本国憲法が基本的人権を保障するから、あるいはそれが硬性の憲法典だからと答えるかも知れないが、単に、そんなことは当たり前だと応ずるかも知れない。 平常時にこのような問い掛けをする人間は稀であろう(1.4.2 参照)。 経過規定 憲法98条1項に関しては、それが従前の法令の効力について定める経過規定としての意味を有するかという問題が議論される。 支配的学説や判例(最大判昭和23.6.23刑集2巻7号722頁)は、この問題を積極に解し、98条1項は、日本国憲法施行の際に存する明治憲法下の法令のうち、憲法の条規に反しないものについては、引き続き効力を有する旨をも意味しているとする。 明治憲法下の法令のうち、法律事項を規定するものには法律としての、それ以外の事項を規定するものには命令としての効力を暫定的に認めた1947年法律72号、政令14号も、この趣旨を受けたものとされる。 しかしながら、98条1項が経過規定としての意義を持たず、そのため日本国憲法が経過規定を全く欠いていたとしても、法秩序が革命的な変革を受けた場合にそうであるように、民事・刑事の事件を日々解決すべき裁判所などの法適用機関は、成立時において有効に制定された法令である以上、制定の根拠となる規範(この場合は、明治憲法)が消滅した後も当該法令の内容が新たな憲法に違反するなどの特別な理由のない限り有効に存在し続ける続けるものとして適用するはずである。 さもなければ、安定した法秩序に基づく市民生活の継続は不可能となる(芦部・憲法学Ⅰ100頁)。 憲法の大規模な改正を理由に下位の法令をすべて無効とすれば、従来の法を前提として生活してきた人々の期待を覆し、「法の支配」の要請に著しく反することになる。 民法および不動産登記法が新憲法の成立によって失効したか否かが争われた事件で、最高裁が「法律は一旦適法に制定された以上その後の法律により改廃せられない限り効力を失うものではない」と述べているのも同様の趣旨と考えられる(最判昭和30.4.5民集9巻4号456頁)。 つまるところ、98条1項が経過規定であるか否かという問題は、さほど重要なものではない。 占領法規の効力 占領時代に制定された法令の独立後の効力についても、同様に考えることが出来るはずである。 最高裁の判例は、連合国最高司令官の要求の実施を政府に義務づけた昭和20(1945)年緊急勅令542号およびそれに基づく政令(いわゆるポツダム命令)について、日本国憲法施行にかかわりなく憲法外において法的効力を有していたとの立場をとった(最大判昭和28.4.8刑集7巻4号および最大判昭和28.7.22刑集7巻7号1562頁)。 平和条約発効後の同勅令に基づく命令の効力については、当初、
通説は憲法98条1項が経過規定としての意義を持つとの前提から第②説の立場をとる(清宮・憲法Ⅰ26頁、宮沢コメ806頁)。
◇1.3.4 不文法源不文の法源としては、慣習と判例とが問題とされる。 慣習や判例が法源であるか否かが問われる際には、暗黙のうちに、一般的抽象的な形で妥当すべき規範を確定している制定法こそが本来の法源でると前提されたうえで、このような性格を持たない慣習や判例を果たして法源として認めることが出来るかという形で問いが立てられることが多い。 判例について厳格な先例拘束性が当て嵌まる場合にのみ、それを法源と呼ぶことが出来るという主張は、できるだけ判例を制定法に近づけて解釈しようとする試みの一つである。 逆に、具体的な事例から構成される慣習や判例に現れた社会の伝統的な考え方こそが、その共同体における人々の行動のあり方を示す法の本来の姿であり、制定法こそが例外的な現象であるとの理解もありえよう。 以下では、一般的抽象的な規範を確定的に示す制定法が、典型的な法源であるとの前提の下に、慣習と判例とがどこまで、法源としての性格を備えているかという問題を扱う。 以下、分説する。 (1) 憲法慣習慣習の合理的基礎 慣習が、少なくとも憲法典よりも形式的効力の劣る法源として、実質的意味の憲法の一部たり得ることは、多くの論者が認めるところである。 そのような慣習の成立要件については議論の対立が見られる。 一つの見解は、イギリスにおける憲法習律についての議論にならい、慣行が規範意識をもって遵守されていることに加えて、その慣行に合理的理由のあることを要求する(伊藤・憲法80-82頁)。 たとえば、衆議院の解散を実質的に決定する権限の所在、および解散の許される要件については憲法典に明確な規定がないが、慣例上は、1948年12月の第一回解散以来、内閣が実質的な決定を行い、しかもほとんどの場合、憲法69条所定の衆議院の議決なしに解散が行われてきた。 解散に先立って内閣不信任の議決が行われたのは、1952年8月、1953年3月、1980年5月および1993年6月の4回の解散にとどまる。 そして、議院内閣制の下における議会と内閣との均衡を保ち、かつ重大な政治問題について時機を失することなく有権者の審判を仰ぐためには、内閣に自由な解散権を与えることにも合理性があると考えられることから、このような慣行は習律としての地位を得たとの有力な見解がある(解散権の所在と行使の要件については 13.3.3を、習律については 13.3.3 (3) 【憲法習律】を見よ)。 もっとも、慣習の主要な機能を、社会で反復して発生するさまざまな調整問題状況を解決することに求めるならば、当該慣習に、他の選択肢と比較して特別の合理性を要求することにはさほど意義が認められないことになる。 他の選択肢と比べて、その慣習がはるかに合理的なのであれば、そもそも、その問題は調整問題ではなかったということになろう。 解散権の行使の要件の問題についても、内閣に広い裁量を与えることが、裁量を狭めることに比べて、明らかに合理的であるか否かは疑わしい。 広い裁量は、党利党略に基づく解散を引き起こす危険を増し、政権党に有利な形で解散権が行使される可能性を広げることになる。 もちろん、慣習の機能が調整問題状況の解決にある以上は、たとえ慣習として成立した選択肢が他の選択肢に比べてとくに合理的であるとはいえなくとも、なお、その慣習に従うことには合理性があることになる。 憲法典に反する慣習 他方、憲法慣習が憲法典を改廃する効力を持ち得るかについては、厳しい意見の対立がみられる。 慣習が憲法典を改廃し得るとする主張は、憲法改正手続によらずに憲法の意味内容が慣習によって変化し得ると認めることになり、法的意味における憲法の変遷を認めることとなる(1.4.3)。 憲法制定者が制定当時に想定した状況のその後の変化に対応する必要性や、国政のあり方に対する主権者たる国民の決定権を強調する人々は、国民の合意を得た憲法慣習による憲法典の改廃を認めようとするが、硬性憲法の意義を重視する人々は、主権者の意思とされるものが多くの場合、立法府や行政府など国家機関の意思に過ぎないことを指摘し、憲法慣習に憲法典と並ぶ効力を認めることは危険であるとする。 少なくとも、合意(consensus)を理由に、憲法の変更を主張することは出来ないであろう。 同意(consent)と異なり、単なる意見の一致である合意が法的効力を基礎づけることはあり得ない。 世論調査が国民投票の代わりになり得ない一つの理由はここにある。 3つの論点 慣習が憲法典を改廃し得るかという問題については、3つの点に留意する必要がある。
(2) 判例判例とは裁判の先例をいう。 判決や決定などの裁判が、具体的事件を解決する限りにおいて法としての意味を持つことは当然のことである。 問題となるのは、本来、具体的事件を解決するために下された裁判が、後の裁判を拘束する一般的な規範としての意義を持ち得るか否かである。 このような意味での判例となるのは、通常、先例とされる裁判の判決理由中の判断のうち、主文を導くための直接の論拠となっている部分(ratio decidendi)に限られ、それ以外の傍論部分(obiter dictum)に判例としての意義が認められることはないといわれるが、実際には傍論部分の判断が後の裁判で論拠として援用されることも少なくない。 判例の拘束力 先例拘束主義(principle of stare decisis)の妥当する英米法圏においては、判例は「法的拘束力」を持つが、日本を含めてそれ以外の諸国では、「事実上の拘束力」を有するに過ぎないといわれることがある。 もっとも、イギリスにおいても、厳格な先例拘束主義が確立したのは、せいぜい19世紀の後半からのことである。 判例法の特質はむしろ個別の事件ごとに背景となる正当化根拠に応じて柔軟な解決を目指す点にあり、そもそも先例の権威ある定式化を許さない。 予測可能性と法的安定性を図るたまに厳格な先例拘束主義を導入することは、古典的な判例法の考えからすれば逸脱であり、先例の拘束力のみに着目して判例法を論ずるのはむしろ制定法国の見方ではないかとの疑問もある。 他方、事実上の拘束力と法律上の拘束力との間にどれほどの実質的な違いがあrのかという問題もある。 法律問題の最終的な有権解釈権を持つ裁判所が、判例に事実上拘束されるということは、取りも直さず判例が法的な拘束力を持つことを意味するのではないかとの疑問を提起することも可能である。 憲法典や法律が法源であり得るのも、裁判所がそれらを事実上適用するからであり、裁判所が憲法典や法律を適用しなくなれば、それらはもはや法源ではあり得ない。 実際、もし裁判所が、何が ratio decidendi であるか、あるいは、当該事件は先例と区別(distinguish)され得るかなどという問題に頭を悩ますこともなく、事実上先例を援用して具体的事件を解決しているのであれば、事実上の拘束力は法的拘束力よりもむしろ強力であるといえる(樋口・憲法430-33頁参照)。 少なくとも、最高裁判所の判例が下級裁判所に対して持つ拘束力に関する限り、事実上の拘束力説と法的拘束力説との間に意味のある違いはない(最高裁判所の判例が最高裁判所自身を拘束するかという問題については、14.4.7 を見よ)。 法源としての判例 国民主権の理念を徹底させる立場からは、国会や内閣と異なり、国民に対して政治責任を負うこともなく、従って必ずしも国民の意見を反映していない裁判所の裁判が、法源として扱われることには疑義を呈し得る。 これに対しては、判例を法源とすることによって国民に裁判の結果についての予測可能性を保障し得ること、そして法律によって判例を覆す権限を持つ国会が判例を放置すること自体、国会の黙示の承認を意味すると反論することができよう。 判例が狭義の法源にあたることは承認できるとしても、最狭義の憲法法源、つまり合憲・違憲の判断基準になり得るか否かは別問題である。 この問題は、慣習を最狭義の法源と考えるべきかという問題の一事例である。 判例が最狭義の憲法法源であるとすると、判例は同じレベルの後法として憲法典を改廃し得ることになる。 この問題については、憲法慣習について述べたこと、そして憲法の変遷について後述すること(1.4.3 (2))がそのまま妥当する。 ◇1.3.5 憲法の解釈憲法典や法律などの法源の中には、なんらの意識的な解釈を要することなく、一読して直ちに意味を了解し得るものもある。 あらゆる条文、あらゆる文言が解釈を必要とするとすれば、解釈の結果たる言明もさらに解釈を要するはずであり、この解釈の連鎖は終わることはなく、条文の意味は永遠に不明となろう。 しかし、法源の中には、不明確な概念を用いていたり、相互に衝突するかに見える複数の条文が存在することから、さまざまな解釈を許すものもあり、そのような場合、裁判所をはじめとする法適用機関は、まず、適用されるべき法源の意味を解釈によって確定する必要に迫られる。 裁判所も各種の法源によって一義的に拘束されているわけではなく、議会が一定の憲法典の解釈に基づいて法律を制定するように、裁判所による裁判をある種の立法作用として見ることも可能である(ケルゼン・一般理論242-43頁)。 解釈の条件 さまざまな意見の対立が見られる法律問題について如何なる解釈を選択すべきかは、重要な問題である。 一般に、正当な解釈の満たすべき条件としては、以下のようなものが挙げられる。
もちろん、このような条件を満たす解釈があらゆる法律問題について必ず一つだけ定まるというわけではない。 裁判所の有権解釈が定まった後においてもなお、正当な解釈が何かについての論争が続くことの方が普通である。 ◆1.4 憲法の変動と保障ここでは、憲法の変動の類型と保障の方法のうち、憲法改正について論ずる。 憲法の保障の方法のうち、違憲審査制については、14.4 での説明を、また、抵抗権の問題については、5.1.3 (2) の説明を見よ。 なお、本節の議論は、日本国憲法を典型とする近代立憲主義の系譜に属する硬性の憲法典を持つ国家を念頭に置いている。 ◇1.4.1 憲法改正の手続憲法改正とは、憲法典に定められた特別の手続を踏んで憲法を修正することであり、その点で、憲法典に定められた手続を踏まずに憲法の意味内容を変更する憲法変遷とは異なる。 憲法典も、特定の目的を実現するために作り出された一種の社会的技術であり、道具である。 道具が、当初の目論見どおりに働かなかったり、あるいは目的自体が変わった場合には、道具としての憲法典を修正する必要が生ずる。 作り直しの必要があるか否かは、実際に使ってみたうえでなければよく分からない。 多くの憲法典は、自ら修正の手続を定めており、日本国憲法も例外ではない。 日本国憲法の改正手続は、発案、発議、承認という3つの段階を経ることとなっている。 発案 発案とは、国会による発議の前提として、国会のいずれかの議院において、改正の議案が提出されることをいう。 その院の議員が、この発案を為し得ることは疑いがない。 内閣が、この発案を為し得るか否かについて議論が為されているが、憲法上、大臣の過半数は国会議員でなければならないため、たとえ内閣に発案権がないといても、大臣は議員としての資格で、発案を為し得る。 発議 国会による発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要とされている(憲法96条1項)。 改正手続に関しては、衆議院の参議院に対する優越は認められない。 総議員の意味については、
欠員が反対票に数えられるのは不合理だとするのが②説の論拠であるが(清宮・憲法Ⅰ400頁、宮沢・コメ790頁)、欠員がある分だけ改正が容易になるのも同様に不合理であるし、出席議員の3分の2の賛成で反対派を除名することにより改正を容易にする道を防ぐためには(憲法58条)、①説の方が妥当である(伊藤・憲法 654頁)。 承認 国会の発議の段階で各議院に必要な数の賛成を得られない議案については、その時点で手続は中止する。 もし必要な賛成が得られたならば、次に国民投票にかけられ、国民の承認を求めることになる。 国民の承認については、必要なのが、①有権者の過半数か、②無効票を含めた総投票の過半数か、③有効投票の過半数か、という対立がある。 有効投票の過半数と考えるべきであろう。 2007年5月に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」は、国民投票の手続について定めるとともに、国会による発議に関する手続を整備するための国会法の改正を行うものである。 改正案の原案の発議は、衆議院では議員100人以上、参議院では議員50人以上の賛成をもって「内容において関連する事項ごとに区分して行われる」(同法151条、国会法68条の2、68条の3)。 国民投票は、国会が改正を発議した日から起算して60日以後、180日以内において、国会の議決した期日に行われ(同法2条1項)、国民投票において、改正案に賛成する投票数が有効投票総数の2分の1を超えたときは、憲法96条1項にいう国民の承認があったものとされる(同法126条1項)。 ◇1.4.2 改正の限界憲法改正に限界があるか否かについては、一般に、
そして、これら3つの問題に対する答えは、改正権の上位に憲法制定権が別に存在すると考えるか否かによって変わると考えられている。 日本国憲法の下では、国民主権の原理に「反する一切の憲法・・・・・・を排除する」と述べる前文の文言、戦争、武力による威嚇または武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては「永久にこれを放棄する」と述べる憲法9条1項、この憲法が国民に保障する基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とする憲法11条が、実体的改正禁止規定の例として挙げられることがある。 改正手続規定は、憲法96条がそれにあたる。 憲法制定権の存否と限界の有無 もし、改正権の上位に、改正権を制約する憲法制定権はないと考えるならば、改正権には限界はないという答えが出て来ると考えられている。 上の3つの論点に即していえば、たとえ実体的禁止規定が存在したとしても、それ自体を改正してしまえばよいし、そのような禁止規定がない場合に改正に限界が存在しないことは当然である。 また、所定の改正手続を踏みさえすれば、改正手続規定自体を改正することにも障害はない。 これに対して、改正権は、上位にある憲法制定権により授権された権限であると考えるならば、改正権は憲法制定権自体の根拠となっている「根本規範」を変更することはできず、そのような改正がたとえ行われたとしても、それは法的には「革命」であって「改正」ではない。 もし、実体的な改正禁止規定が、憲法制定権自体を構成する根本規定の内容を確認するものであれば、そのような改正禁止規定を変更することはできない。 さらに、改正手続規定についても、改正権がこれを変更することは、自らが憲法制定権に成り代わることを意味するので、原則として許されない。 限界の有無は何によって決まるか 以上のような考え方については、以下のような論点に留意する必要がある。 第一に、憲法の最高法規性に関する状況(1.3.3)と同様、憲法改正の限界の有無に関しても、直接には、憲法改正に関与し得る人々-国会議員、官僚、裁判官、広くは有権者一般-が、実際に何等かの限界を受け入れているか否かが問題である。 何等かの限界がこれらの人々に事実上受け入れられていれば、その事実上のルールに則した形で限界は存在する。 ここでも、日本国憲法という憲法典が改正の限界について何事かを語っているか、あるいは、普遍的妥当性を有する政治道徳の原則が憲法の背景に存在するかという問題への答えは、改正の限界の有無を直接には導かない。 また、憲法制定権が改正権のさらに上位に存在するか否かという問題も、限界の存否とは直接には結びつかない。 改正権が最高機関であれば、改正に限界はないという議論は、憲法典のみが憲法の領域における実定法であるという誤った前提に立脚したものであり、改正権が最高機関であること自体が、法の運用者によって受け入れられている限りで成り立つという事情を見逃している。 さらに、改正権が最高機関であるという前提からは、改正権を構成している規範を自ら改変することはできないという結論、つまり一定の論理的な改正の限界があるという結論をも導き得る。 一般に、法が存立するためには、それを定める立法機関を構成する授権規範が別に存在している必要がある。 法は、その存立の根拠を自らに与えること、つまり自己授権を行うことはできない(清宮・憲法Ⅰ17頁、長谷部 [1991] 27-28頁)。 立法機関を構成する授権規範は、①立法権者、②立法の手続、③立法の内容、を定める三種類の規範から成り立つ。 現在の日本における形式的意味における法律の場合でいえば、
つまり、法律の制定権を基礎づける授権規範は、憲法典がこれを定めている。 法律の制定機関である国会は、自己の権限を構成し、その根拠となっているこれらの授権規範を変更することは許されない。 他方、憲法改正権も一種の立法権である。 それを構成する授権規範は、
従って、改正手続規定を変更することも、実体的改正禁止規定を変更することも許されないという結論が、そこから導かれる。 これに対しては、国会の立法権の授権規範は、憲法のみではなく、国会法など国会自身の制定する法律によっても定められており、これらの法律については国会自身が改正することが出来るのだから、憲法改正権もやはり憲法典によって定められている限りで自分自身を構成する授権規範を改正することは可能であるとの反論があり得る。 しかし、憲法典の定める国会の授権範囲は、それなくしては立法権者たる国会が存在し得ない原初的な規範であり、国会法などの法律による規定はそれを補足するものに過ぎない。 同様に、憲法典によって定められた改正権の授権規範も改正権をはじめて構成する原初的な規範であって、改正権自身による改正を許さない。 憲法改正権の上位に、憲法制定権が存在するという前提に立って、はじめて、憲法制定権を構成する根本規範(それは憲法制定権を構成する授権規範である)に反しない限りで、実体的改正禁止規定を改正し、あるいは改正禁止規定を改正する余地が生まれる。 憲法制定権の存在は、改正の限界をむしろ縮小し、改正し得る範囲を拡大する(根本規範によって構成されない、制約のない始源的な憲法制定権力なる概念が筋の通ったものではあり得ない点については、1.2.3【憲法制定権力】参照)。 「改正の限界」の意味 第二に、「改正の限界」という概念の意味である。 改正権に限界があると主張する論者も、そのような限界を超える改正が事実として起こり得ないと考えるわけではなく、そのような「改正」が行われたとしても、それは法的な観点から見れば「改正」とは評価し得ず、変更後の憲法と変更前の憲法との間には、法的連続性はない、つまりそれは「改正」ではなく「革命」であるとするにとどまる。 従って、新しい憲法は、前の憲法とは異なる根本規範に立脚した憲法だということになる。 何等かの改正の限界が、実際上広く受け入れられていたとしても、それに反する「改正」が行われる可能性はある。 このような革命的変動の後、若干の政治的動揺を経て、元の憲法が復活した場合には、もともとの改正の限界が再び受容され、中間期の憲法の変動は、「違法な改正」として説明され、処理されることになるであろう。 他方、革命的変動がその後長期に亘って定着し、変動後の憲法体制が当該社会の法運用者によって、そして最終的には社会の大部分のメンバーによって広く受け入れられたとすると、このとき、革命は完成したわけであり、以前の改正の限界に関するルールも「旧法」として、つまり現在では効力を有しない法として説明され、処理されることになるであろう。
◇1.4.3 憲法の変遷2つの「憲法変遷」 憲法の変遷という言葉も、様々な意味で用いられる。 非常に広い意味では、実質的意味の憲法の内容が変化することを一般的に指す。 この意味での憲法の変遷は、いかなる社会でも、常に見られることだろう。 ただ、憲法の変遷が重要な意義を持つのは、硬性の憲法典を持つ国家で、憲法所定の手続を経ずに、憲法の意味内容が変化することが認められるか否かという問題についてである。 この場合でも、憲法典の内容に反する法律や裁判が、実質的意味の憲法として通用することはあり得る。 これは社会学的意味における憲法変遷と呼ばれる現象である。 このような意味での憲法変遷があり得るからこそ、それに対処するために、各国で違憲審査の制度が設けられている。 他方、憲法所定の手続を経ずに、憲法典自体の意味内容が変化することを、法的意味における憲法変遷と呼び、このような意味での憲法変遷があり得るかについて、対立がある。 この問題は、先に述べたように(1.3.4 (1))、憲法慣習が憲法典を改廃する効力を持つか否かという問題と重なり合う。 (1) 社会学的意味における変遷実際には、社会学的意味における憲法変遷がいかにして可能であるかを説明することもそれほど容易ではない。 上位の法に反する下位の法は無効であり、存立し得ないと単純に考えるならば、社会学的意味における憲法変遷もあり得ないはずである。 幾つかの説明の仕方がある。
これに対して、違憲の法律はそもそも無効であるという立場を貫くならば、誰もが、自らの判断で違憲無効の法律を無視して行動し得ることとなり、無政府状態を招くことになろう。 人々が実定法を尊重するのは、(2)で述べるように、そうすることで重要な調整問題が解決され、各自の利益そして社会全体の利益にかなうからである。 (2) 法的意味における変遷法的意味の変遷はなぜおこるか 法的意味における憲法の変遷、つまり憲法典の改廃が、改正手続を経ることなく生じ得るかという問題については、憲法典の最高法規性それ自体も、憲法典を最高法規として扱う不文のルールが法の運用者によって受け入れられている限りではじめて成立しているという認識から出発する必要がある(1.3.3)。 憲法典以外の慣行や法令が、憲法典に代わるルールとして法運用者によって受け入れられ、それに則って法運用者が行動する場合には、憲法典が改廃されたか否かに関わりなく、最高法規たる憲法の意味内容は変動したことになる。 変遷は正当化できるか もっとも、このような実定法の認識の問題として憲法の変遷があり得るかという問題とは別に、このような憲法の変遷が正当化されるか(変遷した後の憲法に従うべきか)という問題を立てることは可能である。 あるルール(の集合)が憲法典という法形式を備えているという事実が、そのルールの拘束力を意味するという事情は、法律・命令・裁判などその他の法形式の場合と基本的には異ならない。 あるルールが特定の法形式を備えている、つまり実定法であるがゆえに、それに従うべしという実践上の法実証主義は、人々が実定法に従うことで社会生活上の多様な調整問題を解決できるという功利主義的配慮によって正当化される。 憲法は、1.1.2 で述べたように主として国家機関を組織しその権限内容と手続を定める法であるから、取引法上のルールなどとは違って調整問題の解決という役割はないとの疑問があるかも知れない。 しかし、国家が果たすべき役割を、実際にはどの機関(人々)が、どのような組織と権限を通じて果たすのかという問題は、それ自体、調整問題であり、従って、社会の大部分の人々は、各自、社会の大部分の人々が受け入れるルールを、自分も進んで受け入れようとするはずである。 大部分の人々が「国会」だと思う機関の制定した法に従うのが誰にとっても利益となるし、大部分の人が「裁判所」だと思う機関の下した裁判でなければ、それに従うことにさして意味はない。 そのような誰が国家機関かに関するルールを憲法典という特別の法形式によって定め、容易には変動しない旨を定めておけば、この調整問題の解決を期待する人々にとって便利であろう。 その限りで、憲法典を最高法規とし、かつ硬性として容易な変更を許さないとすることには正当性があることになる。 しかし、この問題が所詮、調整問題である限り、憲法典と異なる組織・権限・手続に基づいて国家機関が構成され活動を継続したとすると、多くの人々にとっては、その実効的なルールに従うことが自己の利益にも、また社会全体の利益にもかなうこととなろう。 つまり、憲法変遷を認める「べき」かという問題は、調整問題の解決という役割によって支えられる実践上の法実証主義が、「憲法典」という具体の実定法に関して有する射程の問題である。 目的が調整問題の解決である限り、憲法典の外に生じた実効的な慣習が憲法典より適切に調整問題を解決している以上は、憲法の変遷を認めるべきである。 つまり憲法典という実定法を尊重すべきだというルールをさらに支える正当化根拠により適合している。 しかしながら、憲法の果たすべき役割は調整問題の解決には限られていない。 変遷したか否かが問題となる条文の役割が、その時々の政治的・社会的多数派によっては変更されるべきでない公共財の実現にかかわるものであるとき、あるいは、社会全体の利益に抗して守られるべき人権にかかわるとき、憲法の変遷を正当化し、そのような実効的な慣行に従うべきだと主張することは出来ない。 |
| + | ... |
<目次>
◆2.1 大日本帝国憲法◇2.1.1 大日本帝国憲法の制定大日本帝国憲法制定の背景 大日本帝国憲法(明治憲法)の制定は、国内政治のレベルでは、藩閥政府と自由民権運動との抗争と妥協の産物として、憲法思想のレベルでは、西欧を起源としながら普遍的な妥当性を主張する近代立憲主義と日本固有の国家体制を確立し維持しようとする考え方との対立の中で理解することができる。 明治国家建設の過程で、政権抗争に破れ下野した副島種臣、板垣退助らは1874年に「民選議院設立建白書」を左院に提出し、加藤弘之らの設立尚早論者との論争が新聞、雑誌等で広く行われるようになった。 政府は翌1875年には「漸次立憲政体樹立の詔」を出し、1876年9月には、・・・(中略)・・・国憲起草の勅命が、元老院に対して下された。 元老院は、1880年末に「日本国憲按」と題する最終案を作成して、天皇に奏上した。 この案は当時のヨーロッパ諸国の憲法、とくにベルギーおよびプロイセンの憲法に依拠したものであったが、海外「各国之憲法ヲ取集焼直シ候迄ニ而我国体人情等ニハ聊モ致注意候モノトハ不被察」(伊藤博文の岩倉具視あて書簡)、あるいは「我カ国体ト相符ハサル所アル」(岩倉具視の論評)ものと考えられ、採択されるに至らなかった。 伊藤博文の起草作業 出直しとなった憲法起草作業は伊藤博文を中心として進められた。 伊藤は、憲法調査の勅命により1882年にはヨーロッパに赴いて、ベルリン、ウィーンでグナイスト(Gneist, R. v.)、シュタイン(Stein, L. v.)、モッセ(Mosse, A.)らの講義を聴き、帰国後、井上毅、伊藤巳代治、金子堅太郎の3人の協力を得て憲法の起草に着手し、1888年に成案を得た。 伊藤らの草案は、彼自身を議長とする枢密院への諮詢を経て確定し、翌1889年2月11日に「大日本帝国憲法」として公布された。 施行されたのは、上諭第4項の定めるとおり、第1回帝国議会開会の時にあたる1890年11月29日である。
◇2.1.2 大日本国憲法の基本原理と運用大日本帝国憲法には、天皇主権、皇室の自律、天皇大権による国政運営など、天皇の統治権を広範に認める側面と、欧米諸国の憲法にならって、権利の保障、権力の分立、限定された民主政治など、自由主義あるいは民主主義に即した制度を取り入れた部分とがある。 天皇主権 1条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とされ、第4条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ」とされるとおり、統治権は天皇が行使するものとされ、立法、司法、行政の各権能は、究極的には天皇に帰属し、議会、裁判所、政府各機関は、大権を翼賛するに過ぎないとの建前がとられた。 立法権については、天皇は緊急勅令いよび独立命令を発する権限を持ち(8条、9条)、また議会の議決した法律案も天皇の裁可によって初めて法律として成立すると考えられ、議会の立法権は限定されていた(もっとも、議会の議決した法案で、裁可されなかったものはない)。 その他にも、天皇は行政各部の官制の制定および官吏の任免(10条)、陸海軍の統帥(11条)、非常時における戒厳の宣告(14条)など、広範な権限を有した。 また、統帥権については、慣習法上、国務大臣の輔弼によらず、陸軍参謀総長、海軍軍令部長が大権を輔弼するものとされ、従って、議会も政府の責任追及を通じてこれをコントロールすることはできないものとされた(美濃部・撮要322-30頁)。 皇室の自律 さらに、皇室に関する事項は皇室典範、皇室令などにより皇室自らが定めるものであって、そもそも憲法の定めるべきことではなく、従って一般国民や議会の関与する余地はないとされた(2条、17条、74条)。 臣民の権利と義務 大日本帝国憲法はその第2章で、国民の権利と義務について定めを置いたが、そこで保障されたのは「臣民」として天皇から認められた限りでの権利と義務であり、個人の生来の平等な権利が保障されたわけでえはない。 保障された権利は、主として、居住及移転の自由(22条)、言論著作印行集会及結社の自由」(29条)などの消極的自由権であり、いずれも「法律ノ範囲内ニ於テ」という法律の留保の下にあった。 衆議院議員の選挙制度も「選挙法ノ定ムル所」に委ねられている(35条)。 学説においても、「我が憲法に於ける臣民の権利の保障は原則として唯行政権及司法権に対する制限たるに止まり立法権に対する制限に非ず。・・・・・・憲法は其の各条に於て臣民が法律の範囲内に於て何々の自由を享有し、又は法律に定めたる場合を除く外其の自由を侵されざることを定めたるに止まり、国民が法律に依りても侵されざる権利を有することを定めず」(美濃部・撮要181頁)と理解されていた(もっとも、美濃部によれば、「法定の裁判官の裁判を受くる権利」(24条)と「公安を害せず臣民の義務に反せざる限に於て信教の自由を有すること」(28条)とはこの例外で、立法権自身が憲法に制約されている(前掲))。 もっとも、権利の制約が法律に委ねられている限りでは、フランス第三共和政やイギリスが伝統的にそうであったように、議会が人権の擁護者としての役割を果たす余地もあり得たが、1938年の国家総動員法の制定によって国民の自由と財産の制約が勅令に白紙委任されると、このような民主的歯止めも失われることとなった。 また、臣民の権利は、非常時における天皇大権の行使に対抗できない旨が明記されている(31条)。 国政の運営 政治運営の面では、国務大臣はそれぞれ天皇に責任を負うものとされ、議会の信任を在職の要件とするものではないとの超然内閣主義が当初とられた。 しかし、大正末から昭和初期にかけては、衆議院の多数派政党が政権を担当するという議院内閣制が「憲政の常道」とされた。 衆議院は、貴族院と同等の権限を持ち、議会の支持がない限り、政府が必要とする法律、予算を得ることは困難であったから、政府が衆議院に対して責任を負う政治運営には、制度上の困難があったといえる。 この間、1925年には男子普通選挙法が成立し、1928年の衆議院選挙において初めて実施されている。 しかし、統帥権が政府の輔弼の対象とならないとされたことや、陸軍大臣および海軍大臣に現役の将官を充てる制度が長期に亘って存在したことなどから、軍が内閣の構成に至るまで政治的に大きな発言権を確保した。 とくに1932年の五・一五事件以降、軍部の政治介入に対する有効な歯止めが失われるとともに、政治制度の民主的な運用も廃れることとなり、1940年に諸政党が解散して大政翼賛会が組織されたことで、政党内閣の基礎自体が失われた。 ◆2.2 日本国憲法の制定◇2.2.1 憲法制定の過程ポツダム宣言受諾と憲法改正 1945年8月14日に日本政府が受諾したポツダム宣言は、その10項後段で、「日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙(しょうがい)を除去すべし。原論、宗教および思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし」とし、さらに12項では、「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ、平和的傾向を有しかつ責任ある政府が樹立せらるる」ことを連合国占領軍の撤収の条件としていた。 このポツダム宣言の内容を実現するために、大日本帝国憲法の改正が必要か否かについては、少なくとも、敗戦直後に成立した東久邇宮内閣では、否定的見解が強かった。 「国体護持」を謳って、辛うじて終戦に踏み切った直後であるだけに、憲法の改正を言い出しにくい情勢であったことにもよると思われる。 これに対して、連合国最高司令官のマッカーサーは、1945年10月4日、東久邇宮内閣の国務大臣であった近衛文麿に対し、さらに、10月9日に成立した幣原内閣の首相、幣原喜重郎に対して、ポツダム宣言実施のためには憲法改正が必要であることを示唆した。 幣原内閣は、マッカーサーの示唆を受けて、1945年10月25日、松本蒸治国務大臣を長とする憲法問題調査委員会(通称、松本委員会)を発足させた。 松本委員会は、憲法改正について消極的であり、委員会発足に際しての松本委員長の談話でも、同委員会は「必ずしも憲法改正を目的とするものではなく、調査の目的は、改正の要否および改正の必要があるとすればその諸点を明らかにすることにある」とされていた。 委員会が最終的にまとめた「松本案」といわれる改正草案も、天皇主権を維持し、国会に対して責任を負わない枢密院を残し、国民に対する権利の保障についても広範な法律の留保を設けるなど、保守的なものであった。 総司令部による草案の起草 総司令部は、憲法改正は必要としながらも、改正は日本政府のイニシァティヴで進められるべきものとの立場をとっていたが、1946年2月3日になって、マッカーサーは、総司令部が独自に改正草案を作成し、これを日本側に提示すべきだとの立場をとるに至る。 この方針転換の背景には、以下のような2つの考慮が働いていたと考えられる。
マッカーサーは、2月3日、総司令部民政局(Government Section)のメンバーに憲法草案の起草を命じ、その際、草案に必ず盛り込むべき原則として、①天皇制の存続、②戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認、③封建制度の廃止と貴族制の改革、の3点を示した。 いわゆるマッカーサー・ノートである(高柳他 [1972] 99-107頁)。 総司令部は、2月13日、吉田茂外相官邸での会談において、総司令部案を日本政府側に手渡した。 日本国憲法の誕生 日本政府は、結局この総司令部案を基礎として改正を行うことを受け入れ、松本国務大臣の下で、総司令部案に相当の修正を加えた「3月2日案」を作成する。 さらに、総司令部との折衝の結果、3月6日に「憲法改正草案要綱」を閣議決定した。 ついで、4月10日に衆議院議員の総選挙が行われ、最後の帝国議会の衆議院議員が選出される。 政府の憲法草案は、枢密院での審議を経た後、6月25日に衆議院本会議に上程され、衆議院で約2ヶ月、貴族院で約1か月半に亘る審議を経た後、10月7日に確定され、枢密院での審議、天皇の裁可を経て、同年11月3日に公布された。 施行は、憲法100条の定めるとおり、公布後6か月を経た1947年5月3日である。
◇2.2.2 日本国憲法制定の法理① - 八月革命説日本国憲法は、形式的には明治憲法の改正として、明治憲法73条の定める改正手続に則って成立した。 しかし、その内容をみると、明治憲法とは全く面目を一新しており、新しい憲法の制定と考える方が相応しい。 とくに、明治憲法で統治権の総攬者とされた天皇が、単なる象徴とされ、新たに国民が主権者として位置付けられている点は、憲法改正の限界を超えるものと見ることができる。 このような国民主権原理の確立と日本国憲法の制定とが如何にして正当化し得るかについては、宮沢俊義教授のいわゆる八月革命説が一般に受け入れられてきた。 その概要は以下のとおりである(宮沢 [1967])。 法的意味における革命 国政の最終的な決定権という意味での主権は、明治憲法下では本来、天皇にあった。 ところが、敗戦時に日本政府が受諾したポツダム宣言の12項は「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ・・・・・・政府が樹立せらるる」ことを要求している。 これは国民主権の確立を要求するものであり、ポツダム宣言の受諾により、日本の主権は天皇から国民へ移ったことになる。 このような主権の転換は、法的意味における革命と考えることが出来る。 現行憲法は、国民主権原理を採用しているが、これはポツダム宣言の受諾に伴う主権の転換の帰結を宣言しているに過ぎず、創設的な意味を持つものではない。 主権原理の転換と改正の限界 現行憲法は明治憲法の改正手続に則って制定されたが、本来、明治憲法の改正手続を通じて憲法の根本原理である天皇主権の国民主権への転換を行うことは、憲法改正の限界を超えており、法的に不可能のはずである。 これが可能であるとすれば、それはポツダム宣言の受諾によってすでに主権原理が転換し、国民主権原理と抵触する限りにおいて、明治憲法の意味内容に根底的な変更が加えられていたからである。 さらに、ポツダム宣言の受諾によって主権原理が転換し、明治憲法の意味内容が根底的に変化している以上、改正手続のうち、貴族院、枢密院の審議裁決、および天皇の裁可は、法的には不必要であった。 ◇2.2.3 日本国憲法制定の法理② - ノモス主権論八月革命説に対しては、ポツダム宣言の受諾は、日本に国民主権の確立を義務付ける債権的効果を持つにとどまり、ただちに国民主権への移行をもたらす物権的効果は有しないのではないかとの批判や、日本が占領下に置かれ、国家としての主権を喪失しているにも拘わらず国政の最高の決定権の国民への移行を論ずる意味はあるのか等の批判がある。 中でも、明治憲法と日本国憲法との根本的な連続性を主張し、宮沢教授との論争に発展した尾高朝雄教授のノモス主権論が注目に値する。 その概要は、以下のとおりである(尾高 [1954])。 主権はノモスにある 国政のあり方を最終的に決定する者が天皇であれ、国民であれ、その決定は、法の根本原理たるノモス(nomos)に従っていなければならない。 ノモスとは、所与の具体的条件の下で、できるだけ多くの人々の福祉をできるだけ公平に実現していかなければならないという規範である。 国政が、常にこのノモスに従っていなければならない以上、主権はノモスにあるというべきである。 明治憲法では天皇にあった主権が、新憲法の下では国民にあるといわれることがあるが、いずれの憲法の下でも主権はノモスにあり、従って新憲法制定による変革は、日本の国家組織を根本的に変えるものとは言えず、日本の「国体」は変化していない。
◇2.2.4 両説の検討 - 憲法の科学「主権」をどう捉えるか 八月革命説とノモス主権論との対立の中心には、「主権」という概念の捉え方がある。 宮沢教授のように、国政のあり方を最終的に決める力として主権を捉えるならば、この力を有するのは具体的な人間でなければならず、天皇か、国民か、それとも他の誰かかという形で答えられねばならない。 たとえ、国政がノモスに従っていなければならないとしても、ノモスの内容を判定する者は誰かという問いに答えない限り、主権の問題は解決しないことになる。 もちろん、尾高教授のように、国政に関する決定が常に従わなければならない規範を主権の在りかとする主権の捉え方もあり得、その限りでは、両説の対立は概念の組み立て方の問題となり、簡単には決着がつかないことになる。 しかし、尾高教授のように、国政の最終的決定権者が変わっても国家組織の根本的変動はないとの立場をとると、フランス革命もロシア革命も、革命とはいえないことになり、常識と大きく異なる言葉の用法だといえよう。 「憲法の科学」と八月革命 八月革命説とノモス主権論との対立は、いずれが「憲法の科学」として妥当であるかについての対立であるとされることがあるが、そこで言われている「科学」の意義については慎重な検討が必要である。 八月革命説を取ろうと、ノモス主権論を取ろうと、我々は実際に起こった歴史的事実を残らず知ることが出来る。 「八月革命」は、これらの具体的事実と並ぶもう一つの事実ではなく、これらの事実に関する一つの描写の仕方、一つの解釈である。 八月革命説も、ノモス主権論も、具体的な事実の摘示によって「反証」されることはなく、従って反証可能な仮説としての「科学」ではあり得ない。 もっとも、これは八月革命説がいかなる意味でも「憲法の科学」ではあり得ないことを意味しない。 法の「科学」は、事実によって反証可能な仮説の構築と、そのテストに限られるわけではない。 法的関係を認識し、記述する学問は、単に、外的に観察し得るデータを記述するだけではなく、その法的関係にコミットする参加者の視点から見て、それらの観察し得るデータが如何なる「意味」を持っているかを理解し、認識する必要がある。 たとえば、交通ルールの研究者は、赤いランプが点灯した際、何パーセントの車が停止するかを記録するだけではなく、運転者がそれを「停止せよ!」という意味を持つ「信号」として理解し、それを自己および他者の行動の評価基準として受け入れていることをも記述する必要がある。 八月革命説が「憲法の科学」であるとすれば、それが、戦後の憲法体制を戦前の国家体制と正統性根拠の点で切断された体制として受け入れ、コミットする人々から見て、明治憲法から現行憲法への移行が、如何に首尾一貫して説明され得るかを明らかにしているからである。 従って、八月革命説は、その本来の姿においては、つまりそれにコミットする人々から見れば、一つの実践的立場の表明である。 それが「科学」であり得るとすれば、宮沢教授がそのような立場にコミットせず、そのような立場を「記述」することに終始している限りにおいてである。 同様のことが、対立する実践的立場についてであるが、ノモス主権論に関してもいえる。
|
| + | ... |
<目次>
◆3.1 憲法9条の起源◇3.1.1 マッカーサー・ノート9条の原型 憲法9条の原型は、占領軍総司令官であったダグラス・マッカーサーが、1946年2月、総司令部独自の新憲法の起草を決意した際に、草案に盛り込むべき基本原則として民政局のスタッフに示したいわゆるマッカーサー・ノートの第二原則である。 それは、「国権の発動たる戦争は廃止する。日本は紛争解決の手段としての戦争、さらに自己の安全を保持する手段としての戦争をも放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない」とする。 この第二原則は、起草作業を主として担当した総司令部民政局のスタッフには余りにも理想主義的であると考えられたため、彼らの用意した第一案では、この原則は憲法の本文ではなく前文に置かれ、また自衛のための武力の行使あるいは武力による威嚇の可能性を残す文案に改められた。 しかし、このような「法律家」的考慮は、戦争放棄の協調を求めるマッカーサーの完全な了解を得ることができず、自衛のための武力行使の可能性は維持されたが、彼の強い主張で、戦争放棄および戦力不保持の原則は、最終的な総司令部案では本文に移され、それを受けた日本政府の憲法草案、そして確定した日本国憲法でも本文に置かれている。 ◇3.1.2 芦田修正帝国議会での修正 衆議院での審議において、9条2項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が加えられた。 これは、この修正を提案した衆議院憲法改正特別委員会の委員長であった芦田均氏の名をとって、一般に「芦田修正」といわれる。 芦田氏は、この提案の当時はその趣旨を明確にしなかったが、後になって、修正後の9条は自衛のための戦争や軍備を許容しているとの見解を明らかにした(憲法調査会事務局 [1961] 503-04頁)。 極東委員会は、この修正が行われた後、現在の憲法66条2項のいわゆる文民条項を憲法に組み入れることを強く主張し、その意向を受けて、貴族院で修正が為された。 この極東委員会の要求も、芦田修正により自衛のための軍備が可能になったとの解釈を前提にしていたものと理解できる。 もっとも政府は審議中、一貫して、原案と修正後の条項は趣旨において差異はないとの説明を加えていた(憲法調査会事務局 [1961] 504頁)。 ◆3.2 憲法9条の解釈起草者の意思と解釈 ある法律の成立の経緯、あるいは起草や審議にあたった人々の考えは、その法律の解釈を決定するわけではない。 法としての効力を有するのは、あくまで条文に定式化された限りでの立法者の意思である。 それ以外の起草者や立法者の考えは、たとえそれを知ることが出来たとしても、それによって現在の我々が拘束されるべき理由は乏しく、憲法思想史や比較法上の素材と同様、解釈の参考資料となるに過ぎない。 我々はむしろ如何なる解釈が9条を憲法全体の構造と理念に整合的に位置づける最善の解釈といえるかを議論すべきであり、起草者の意思に従うべきだと主張する論者は、なぜ起草者の考えが最善の解釈といえるかを立証すべきである。 憲法9条の解釈の根底にある様々な考え方については、3.3以降で述べることとし、ここでは、9条に関するいろいろな解釈を分類学的に記述する。 ◇3.2.1 憲法9条は法か?政治的宣言か 9条の解釈にあたっては、まず、9条が果たして法としての身分を持つか否かが問題とされる。 ある立場によれば、9条は単なる政治的宣言(マニフェスト)に過ぎず、法規範としての身分は持たない(高柳 [1953])。 このため、9条は国会の審議においても、裁判所での裁判においても、他の法律や命令などがそれに違反するか否かが問われる基準とはならない。 総司令部の起草者達が、この見解をとっていたことは、前に述べた(3.1.1)。 これに対して、学界の通説は、9条は法としての身分を持つとし、それに反する国家行為は、単に政治的に不当であるにとどまらず、違憲無効と評価されるとする。 もっとも、中には、問題の高度の政治性ゆえに裁判所における判断基準(裁判規範)としての使用は控えるべきであるとの見解もあり(伊藤・憲法169頁)、この立場と、政治的宣言に過ぎないという立場との距離は小さい。 ◇3.2.2 「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放棄1項が放棄するもの 次に、9条1項にいう「国際紛争を解決する手段として」「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を放棄するという文言が如何なる意味を持つかが議論されている。
◇3.2.3 「戦力」保持の禁止(1) 戦力の意義戦力とは 第三に、9条2項前段で保持が禁止されている「戦力」とは何かが問題となる。 陸海空軍、あるいはそれに相当するような、外敵の攻撃に対して実力をもって抵抗し、国土を防衛することを目的として設けられる人的および物的手段の組織体が通常、戦力といわれるものであるが(宮沢・コメ168頁、芦部・憲法60頁)、あらゆる戦力の保持が禁止されているか否かについて争いがある。
政府の解釈 政府は、「近代戦争を有効適切に遂行し得る装備、編成を備えるもの」として「戦力」を定義したうえで、2項前段では自衛の目的のものを含め、あらゆる「戦力」の保持が禁止されているとする一方、ここにいう「戦力」に至らない程度の、自衛のための最小限度の実力の保持は、あらゆる国家が享有する自衛権によって正当化されるとしてきた(政府の憲法解釈 25-32頁、国会の憲法論議Ⅰ 601-05頁)。 そして、政府の見解では、自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力にとどまっているため、9条で保持を禁じられた戦力にはあたらないとされている。 しかし、何が、この「必要最小限度の実力」にあたるかは、その時々の国際情勢や軍事技術の水準等によって変化するとされる。 核兵器でさえ、防衛的な性格を持つものであれば憲法上、保持を禁止されているわけではない(政府の憲法解釈 33頁)。 現在、核兵器を保有しないのは、政府及び国会の政策的決定によるもので、それは非核三原則、原子力基本法および核兵器不拡散条約に現れているとされる。 この政府の解釈からすれば、自衛のため以外の目的で実力が行使されることは、憲法に反することとなる。
(2) 日米安全保障条約米軍駐留は違憲か 日米安全保障条約によって国内に駐留するアメリカ合衆国軍についても、この駐留が9条2項に違反する戦力の保持といえないかが問題とされる。 この点については、
判例では、いわゆる砂川事件第一審判決が①説の立場をとって、合衆国軍隊の駐留は憲法上、許すべからざるものとしたが、国の飛躍上告を受けた最高裁は②説をとり、外国の軍隊は9条2項にいう戦力にあたらないとしている。 もっとも、最高裁は、安保条約が違憲か否かという判断については、この条約の高度の政治性を理由に、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」であるとし、結論としてその判断は司法審査の範囲外にあるとした。 集団的自衛権 なお、政府の解釈によれば、憲法9条は個別的自衛権の行使のみを許すもので、日本と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合、それを日本への攻撃とみなして共同して防衛にあたる集団的自衛権については、日本を防衛するための必要最小限度の実力行使の範囲を超えるものとして、憲法により禁じられている(国会の憲法論議Ⅰ 698-704頁)。 従って北大西洋条約機構(NATO)に見られるような地域的安全保障体制に参加することや、湾岸戦争に見られたような多国籍軍に参加することは憲法に違反することになる。 いわゆる周辺事態(「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」)に対応して日本政府が実施する措置等を定め、日米安保条約の効果的な運用への寄与を図ることを目的とする周辺事態法も、日本政府がアメリカ合衆国軍に対して行う支援や捜索救助活動等を直接戦闘行為が行われることのない「後方地域」に限り、また、支援の一環としての「物品の提供」は弾薬等の「武器の提供」を含まないものとしている。
◇3.2.4 「交戦権」の否認交戦権とは さらに、2項後段で否認されている「交戦権」が何を意味するかが争われている。 戦争をする権利そのものを意味するとの説もあるが、国際法上、交戦国に認められている諸権利、すなわち、占領地の行政権、船舶の臨検・拿捕権、あるいは敵の兵力を兵器で殺傷する権利などをいうとする説がより多数の支持を得ている。 たとえ戦争をする権利そのものが存在するとしても、その権利は結局は交戦国に認められる諸権利に還元されるはずであり、両説を区別する意義は明らかでない。 なお、自衛のための武力ないし実力の行使を認める立場からすれば、自衛のためには交戦国に認められる諸権利としての交戦権も認められるといわざるを得ないはずである。 敵兵を殺傷する権利なしに、実力によって自衛することは不可能であろう。 ◆3.3 公共財の提供と国民主権日本国憲法9条の法的性格をいかに考えるか、9条と自衛隊、安保条約との関係をどう考えるかは、単なる条文の字義の解釈にとどまらず、より根本的な問題についての立場の違いによるところが大きい。 公共財としての防衛サービス 防衛は、近代立憲主義の建前をとるか否かにかかわらず、ほとんどの国家がその任務の一つとしてきたものである。 なぜだろうか。 モノに限らず、サービスについても、通常は、市場において自由な取引がされ、サービスを求める人は、市場で代金と引換えにそれを手に入れる。 しかし、外敵の侵入から自己の生命・財産を守るための防衛サービスは、典型的な公共財であり、市場で手に入れることが難しい。 公共財を適切に供給するための一つの解決策は、市場ではなく、国家が防衛サービスを提供することとし、その費用は「税金」として住民全員から公平に、しかし強制的に徴収する方法である。 歴史的に見るとこの解決策が一般的に採用されてきた。 さまざまな公共財の供給は政府が実現すべき「公共の福祉」の典型例である。 防衛サービスの民主的決定 この場合、問題は、どの程度の防衛サービスを国が提供し、それに対応してどの程度の費用を国民が負担すべきかである。 市場であれば、各消費者が自分の好きなだけのサービスを自分の支払いたいだけ購入することができるが、公共財の場合はそれが不可能である。 そこで代わりに、国政の最終的な決定権者である国民が、防衛サービスの量と費用負担について、投票で決定することになり、それが困難であれば、国民の代表である議会がそれを決定する。 このような判断は、時々刻々と変化する国際情勢や技術の進展を考慮しながら、その都度、行っていく必要があろう。 砂川事件上告審判決(前掲最大判昭和34.12.16)や長沼事件控訴審判決(後掲札幌高判昭和51.8.5)が、防衛問題は、第一次的には国会や内閣、そして最終的には主権者たる国民が決定すべき問題だとしているのも、上述の議論と同じ趣旨のものと理解できる。 また、この考え方を推し進めれば、およそ憲法によって防衛のあり方を極度に限定すべきではなく、いわんや自国の軍備の保有を禁ずることは非現実的だということになる。 憲法によって軍備を限定すること、とくに日本のような極めて硬性の憲法によってそうすることは、制定時における国際情勢や技術に基づく判断によって、将来における防衛サービス提供に関する主権者の決定を拘束することになる。 9条を単なる政治的マニフェストとして扱おうとする人々は、このような懸念を前提にしていると考えられる。 従って、9条の定める理想は理想として尊重するが、現実には、その時々の情勢判断によって、保持する軍備の水準、同盟を組む相手国等を、それらが全体として日本を危険にするか安全にするか、安全にするとしても如何なるコストにおいてか等を勘案しながら決定していくしかない。 自衛権 なお、あらゆる国家には、国外からの急迫不正な侵害に対して自国を防衛するために必要な限度で武力を行使する、固有の「自衛権」なるものがあるといわれることもある。 前述した日本政府の見解(3.2.3)も、このような前提に立っている。 戦争放棄の宣言は、放棄する主体の存在と維持を前提とするものであるから、戦争放棄の宣言自体が、自衛権の存在を前提としているという議論は、一見したところもっともらしい。 しかしながら、個人の場合には、確かにその生命・身体・財産に対する急迫不正の侵害に対し実力を持って防衛する権利があるといい得るであろうが、国家は、1.1.2 で述べたとおり、それ自体としては約束事に基づく抽象的な存在に過ぎず、それに固有の自衛権があるという議論はさほど説得力のあるものではない。
◆3.4 民主主義の限界と憲法公共財の供給のあり方について、主権者たる国民あるいはその代表が決定すべきだという以上の議論は、幾つかの前提のうえに成り立っている。 民主的決定の条件
これらの条件は、通常、満足されているであろうか。 もちろん完璧な形で満足されることを要求することは非現実的である。 多少、不完全であっても、さほど大きなコストを支払わずに民主主義が運営されているならば、その結果は主権者あるいはその代表の決定として尊重し、人権が侵害されている場合に限り、裁判所を通じて救済を与えれば足りる。 決定枠の限定 しかし、こと防衛に関する限り、民主政の欠陥はあまりにも深刻であり、失敗のコストが過大であるため、何等かの形で決定の幅自体を最初から限定しようとする立場も成り立つ。
以上のような危険を避けるために、その時々の多数派によっては動かし得ない政策決定の枠を憲法によって設定して措くことは、合理的な対処の一つである。 各国の合理性と国際社会の非合理性 たとえ、以上の問題が解決され民主政治が理想的に機能したとしても、なお問題は残る。 国内政治のレベルで、個人のイニシァティヴでは防衛という公共財を適切に供給し得ないという問題が、国際社会においては、ちょうど逆転した形で現れるからである。 国際社会全体としては、軍備を削減し、戦争の危険を少なくすることが、すべての人の利益にかなうはずであるが、各国政府は、他国が軍備を拡張し自国が弱い立場に置かれることを恐れて、軍拡競争に走る傾向がある。 個々の国にとっての「合理的」な行動が、国際社会全体として非合理的な軍拡競争をもたらす危険に対処する一つの方法は、各国が憲法によって軍備拡張の余地をあらかじめ限定することであろう。 9条の意義 以上のような議論を前提とすれば、国の保有し得る軍備を限定すること、あるいはさらに推し進めて、「戦力」と言い得る組織の保持を禁止する主張が現れることも不思議ではない。 そして、主権者たる国民の決定権を縛ることに憲法9条の意義があると考える以上、主権者意思に基づく憲法の「変遷」や、高度の政治性ゆえの「主権者の決定権」を持ち出すことは、こと9条に関する限りそもそも不適切だということになる。 国民を代表する国会やそれに政治責任を負う内閣が、そのことを理由に憲法9条の拘束を免れることも当然できない(長谷部 [2004])。 もちろんこのように軍備を限定する立場をとる場合には、さらに、いかにして理想とは程遠い現在の世界においてなおかつ平和を確保し得るかについて積極的な政策提言を行う必要があろう。 多国間で軍備を相互に削減し、武器輸出を抑制し、経済的協力関係や文化的交流を強化して、できる限り軍備によらずに国際平和を維持する枠組みを作り出す構想はその一つである。 ◆3.5 平和的生存権平和的生存権 他方、軍備によって国を防衛しようとすること自体が、国民の「人権」を侵害するため許されないとの主張も見られる。 「平和的生存権」がそれである。 この議論によれば、9条の要請する非武装平和主義は、憲法前文にいう「平和のうちに生存する権利」を制度面で保障するものである。 従って、国が軍備を保持することは9条に反するため憲法違反であるだけでなく、さらに、それが許されない根底的な理由は、人権たる平和的生存権を侵害する点にある。 問題はそこでいわれている「人権」という言葉の意味である。 もしこの言葉を「切り札」としての人権という強い意味に受け取るとすると、社会全体の利益を理由としてこのような人権を侵害することが許されない以上、3.3、3.4で述べたような政策的な計算をするまでもなく、軍備の保持は違憲であるし、人権を守るべき裁判所は、防衛問題についても積極的に違憲判断をすべきことになる(5.2.3 参照)。 長沼事件の第一審判決は、平和的生存権が、森林法における保安林制度の保護法益であり、住民の訴えの利益を基礎づけるとしたが(前掲札幌地判昭和48.9.7)、同事件の控訴審判決は、この権利が「裁判規範として、なんら現実的、個別的内容をもつものとして具体化されているものではない」とした(前掲行集27巻1193頁)。 平和的生存権論の難点 平和的生存権にはさまざまな反論が予想される。 自然状態で暮らしていた人々が公共財の適切な享受を求めて国家を建設する際、典型的な公共財といえる防衛サービスの供給を全面的に禁止するとは俄かに想定しにくい。 平和のうちに生存する権利は、逆に適切な軍備の保持への要請を正当化するとも考えられる。 確かに、核兵器の脅威に曝された現代では、軍備を保有すること自体が戦争と人類絶滅の危険を増大させるという議論は説得的である。 大量破壊兵器の貯蔵・配備の均衡によって長期的に平和を維持するという考え方は余程、冒険心に富んだ危険愛好者しか真面目に受け取りにくい。 また旧ソ連を含む東欧諸国が民主化し、東西の融和のすすむ今日が軍縮の大きなチャンスを提供していることも見逃すべきではない。 しかし、一国のみが通常兵器を含めて軍備を全面的に放棄してしまえば、他国は軍縮へのイニシァティヴを失ううえに、侵略によって得られる期待利益を増大させることになり、非武装によって生じた力の空白は、逆に周辺地域を含めて不安定化し、武力紛争の危険をもたらす危険がある。 冷戦が終結した後も、民族対立、宗教対立による地域紛争の危険は残っている。 いかなる個人、民族も、他国を含めた周辺地域の平和を危うくしてまで軍備を全面放棄する権利は有していないのではなかろうか。 逆の言い方をすると、通常兵器の一方的即時全廃を可能にするほど周辺諸国の国内政治および国際政治について楽観的であり得るのであれば、戦争の放棄や軍備の廃棄はさして重要な課題とはいえなくなるはずである。 現実には平和の維持も国民の生命・財産の保全も困難であるにも拘わらず、それでもなお軍備を全廃すべきであるとの主張の背後にあるのが、それが人としての「善い生き方」だからという前提があるのだとすれば、多元的な価値観が相克するこの社会において、そうした特定の「善い生き方」をすべての国民に強いることは、日本国憲法の拠って立つ立憲主義と両立し難い(長谷部 [2004])。 世界全体の究極的な平和という理想を達成するためには、理想を目指す情熱とともに冷徹な状況判断と計算の能力が必要となる。 3.3 および 3.4 で描かれたような政策判断を「人権」の観念によって遮断することが適切であるとは考えにくい。 憲法上の権利として「平和的生存権」を観念する余地があるとしても、それはあらゆる人に生まれながらにして認められる権利ではなく、平和の維持という社会全体の利益を実現するために憲法によってとくに認められた権利であり、従ってこの平和の維持をはじめとする重要な社会的利益によって制約され得る権利として捉えられるべきであろう。 |
| + | ... |
|
タグ: