芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第18章 憲法の保障 p.363以下
<目次>
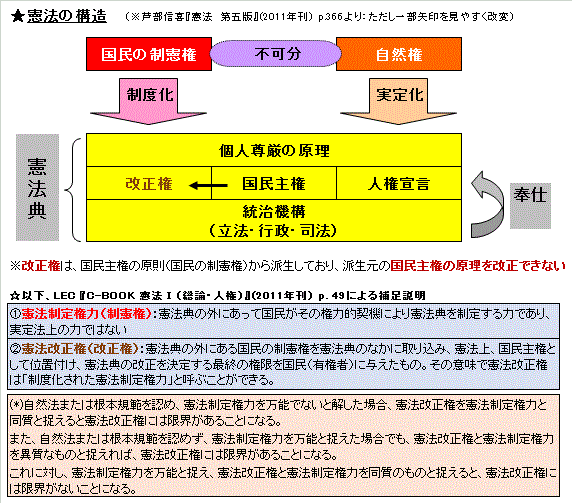
一 憲法保障の諸類型
憲法は、国の最高法規であるが、この憲法の最高法規性は、ときとして、法律等の下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされ、歪められるという事態が生じる。
そこで、このような憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し、または、事後に是正するための装置を、あらかじめ憲法秩序の中に設けておく必要がある。
その装置を、通常、憲法保障制度と言う。
憲法保障制度を大別すると、
| ① |
憲法自身に定められている保障制度と、 |
| ② |
憲法には定められていないけれども超憲法的な根拠によって認められると考えられる制度 |
がある。
①の例を日本国憲法で示すと、憲法の最高法規性の宣言(98条)、公務員に対する憲法尊重擁護の義務づけ(99条)、権力分立制の採用(41条・65条・76条)、硬性憲法の技術(96条)などのほか、事後的救済としての違憲審査制(81条)がある。
②の例としては、抵抗権と国家緊急権が挙げられる。
その他に、法律レベルでも、刑法の内乱罪(77条)、破壊活動防止法等の規定により、憲法秩序の維持が図られている。
以下、まず②を概説し、①については、世界的に最も重要な憲法保障制度となった違憲審査制の意義と機能を検討し、憲法改正の問題を扱うことにしたい。
◆1 抵抗権
国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を行った場合に、国民が自らの権利・自由を守り人間の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段が不可能となったとき、実定法上の義務を拒否する抵抗行為を、一般に抵抗権と言う。
抵抗権の考えは古くからあり、人権思想の発達に大きな役割を演じたが、それが実際に重要な意味をもったのは近代市民革命の時代であった。
自然権の思想と結び合って、「圧制への抵抗」の権利が強調され、若干の人権宣言の中にも謳われた(1789年・1793年のフランス人権宣言参照)。
その後、近代立憲主義の進展とともに、憲法保障制度が整備され、抵抗権は人権宣言から姿を消してしまう。
それは、抵抗権が本来、個人の権利・自由として実定化されることに馴染まない性格をもっているからである。
確かに、第二次世界大戦時におけるファシズムの苦い経験を経て、戦後、抵抗権思想が復活し、それを再び人権宣言の中に規定する憲法も現れるようになったが、それは本来の抵抗権をすべてカバーするものではない。
抵抗権の本質は、それが非合法的であるところにあり、制度化に馴染まないと解される。
一定の内容の実定化が可能であるにとどまる。
日本国憲法が国民の抵抗権を認めているかどうかは、抵抗権の意味・性格をどのように理解するか、とくに抵抗権は自然法上の権利か実定法上の権利か、という難しい問題と関わるので、簡単に結論を出すことは出来ない。
基本的人権を国民は「不断の努力によつて」保持しなくてはならないこと(12条)から、ただちに実定法上の権利としての抵抗権を導き出すことは、きわめて困難であるが、憲法は自然権を実定化したと解されるので、人権保障規定の根底にあって人権の発展を支えてきた圧政に対する抵抗の権利の理念を読みとることは、十分に可能である。
◆2 国家緊急権
戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限を、国家緊急権と言う。
この国家緊急権は、一方では、国家存亡の際に憲法の保持を図るものであるから、憲法保障の一形態と言えるが、他方では、立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険性をもっている。
従って、実定法上の規定がないても、国家緊急権は国家の自然権として是認される、とする説は、緊急権の発動を事実上国家権力の恣意に委ねることを容認するもので、過去における緊急権の濫用の経験に徴しても、これをとることはできない。
超憲法的に行使される非常措置は、法の問題ではなく、事実ないし政治の問題である。
この点で、自然権思想を推進力として発展してきた人権、その根底にあってそれを支えてきた抵抗権と、性質を異にする。
そこで、19世紀から20世紀にかけての西欧諸国では、非常事態に対する措置をとる例外的権力を実定化し、その行使の要件等をあらかじめ決めておく憲法も現れるようになった。
それには、
| ① |
緊急権発動の条件・手続・効果などについて詳細に定めておく方式と、 |
| ② |
その大綱を定めるにとどめ、特定の国家機関(例、大統領)に包括的な権限を授権する方式 |
の二つがある。
しかし、危険を最小限度に抑えるような法制化はきわめて困難であり、二つの方式のいずれも、多くの問題点と危険性を孕(はら)んでいる。
とくに②は、濫用の危険が大きい(例、ワイマール憲法48条の定める大統領の非常措置権)。
我が国では、明治憲法は緊急権に関する若干の規定を設けていたが(8条の緊急命令の権、14条の戒厳宣告の権、31条の非常大権など)、日本国憲法には、国家緊急権の規定はない。
ニ 違憲審査制
(省略)
三 憲法改正の手続と限界
◆1 硬性憲法の意義
憲法には、高度の安定性が求められるが、反面において、政治・経済・社会の動きに適応する可変性も不可欠である。
この安定性と可変性という相互に矛盾する要請に応えるために考案されたのが、硬性憲法(rigid constitution)の技術、すなわち、憲法の改正手続を定めつつ、その改正の要件を厳格にするという方法である。
これは、最高法規たる憲法を保障する制度として、重要な意義を有する。
ただ、国家によって事情は異なるが、あまり改正を難しくすると、可変性がなくなり、憲法が違憲的に運用される恐れが大きくなるし、反対に、あまり改正を容易にすると、憲法を保障する機能が失われてしまう。
日本国憲法は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とし、国民による承認は国民投票において、「その過半数の賛成を必要とする」と定める(96条)。
「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」と、国民投票における「過半数の賛成」という要件は、他国に比べて、硬性の度合が強い。
◆2 憲法改正の手続
憲法の改正は、国会の発議、国民の承認、天皇の公布という三つの手続を経て行われる。
(一) 国会の発議
ここに「発議」とは、通常の議案について国会法などで言われる発議(それは原案を提出することを意味する)とは異なり、国民に提案される憲法改正案を国会が決定することを言う。
(1) 発案
憲法改正を発議するには、改正案が提示されなければならない。
この原案を提出する権能(発案権)が各議員に属することは言うまでもないが(通常の議案の場合は、国会法56条1項により、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の賛成を要するが、憲法改正案についてはとくに要件を加重することも考えられる〔2007年の国会法改正で68条の2が追加され、「衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する」ことになった〕、内閣にも存するか否かについては、争いがある。
肯定説は、「国会の発議」は発案権者が議員に限られることを当然には意味しないこと、内閣の発案権を認めても国会審議の自主性は損なわれず、またそれは、議院内閣制における国会と内閣との「協働」関係からみて不思議なことではないこと、などを理由とする。
これに対して否定説は、憲法改正は国民の憲法制定権力(制憲権とも言う)の作用であるから、国民の最終的決定の対象となる原案の内容を確定する行為(憲法で言う「発議」)を国会が行うのは、制憲権思想からいって当然の理であり、この理を貫けば、「発議」の手続の一部をなすとも考えられる「発案」すなわち原案提出権は、議員のみに属すると解するのが憲法の精神に合致すること、内閣に発案権を認めても国会の自主的審議権が害されることはないとはいえ、改正案の提出権を法律案の提出権と同じに考えるのは、憲法と法律との形式的・実質的な相違を曖昧にする解釈であること、などを理由とする。
いずれの解釈が妥当か、俄かに断じ難い。
そのため、「憲法の本旨は、内閣の発案を認めるかどうかは、国会の意思による法律に委ねるという程度のものと解する」説にも、一理ある。
ただし、仮に否定説が妥当だとしても(私見はそれに傾くが)、内閣は実際には議員たる資格をもつ国務大臣その他の議員を通じて原案を提出することができるので、内閣の発案権の有無を論議する実益は乏しい。
(2) 審議
憲法・国会法に特別の規定がないので、審議の手続は法律案の場合に準じて行うことができると解される〔(現在は、国会法が改正され、第六章の2「日本国憲法改正の発議」、第11章の2「憲法審査会」、86条の2「憲法改正原案に関する両院協議会」が追加されている)〕。
ただ、定数足については、慎重な審議を要する案件であることに鑑み、総議員の三分の二以上の出席が必要ないし望ましいとする説が有力である。
しかし、三分の一以上とするか三分の二以上とするかは、法律の定めるところに委ねられていると解されるので、特別の規定がない以上は三分の一以上で足りる。
審議にあたり、国会が原案を自由に修正できることは、言うまでもない。
(3) 議決
各議院において、それぞれ総議員の三分の二以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。
両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。
議決のほかに、発議および国民に対する提案という特別の行為は必要とされない。
(ニ) 国民の承認
憲法改正は、国民の承認によって成立する。
この承認は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」によって行われる。
承認の要件とされる「過半数」の意味については、争いがあるが、有効投票の過半数と解するのが妥当であろう。
法律により投票総数の過半数と定めることも可能と解される。
このような国民投票による憲法改正決定の方式は、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる。
もっとも現在まだ憲法改正国民投票法は制定されていない(*)(†)。
| (*) 国民投票法の問題点 |
第一は、投票方法である。
同時に多くの改正案が発議される場合は、相互に不可分の関係にあるものを一括して記載することが必要であろう。
第二は、承認の効力発生時期である。
投票の効力を争う訴訟の出訴期間経過後、その間に訴訟があれば判決確定後、投票の結果が確定すると考えるのが妥当であろう。 |
(†) 国民投票法(正式名は「日本国憲法の改正手続に関する法律」)が2007年に制定され、3年後の2010年5月18日に施行された。
それによると、国会による改正の発議がなされると、その後60日から180日の間に国民投票が行われる(同2条1項)。
その間に国民への広報事務を担当する機関として国会に国民投票広報協議会が設置される(国会法102条の11、国民投票法11条以下)。
改正案に対する賛成・反対の「国民投票運動」は、選挙運動と比較すると相当規制が緩和されており、文書図書の規制、運動費用の規制、戸別訪問やインターネット上の運動の禁止もないが、公務員による運動や放送広告による運動は規制される。
改正原案の発議は「内容において関連する事項ごとに区分して行う」(国会法68条の3)ことになっており、区分された案につき個別的に国民投票を行うことになる。
そして、投票総数の二分の一を超えたとき国民の承認があったとされる(国民投票法126条1項)が、その場合の投票総数とは「憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数」(同98条2項)とされている。
承認の通知を受けると総理大臣は直ちに公布の手続きをとる(同126条2項)。
公布を行うのは天皇である(憲法7条1号)。
国民投票に関し異議のある投票人は30日以内に東京高裁に訴訟を提起できるが(国民投票法127条)、訴訟の提起があっても国民投票の効力は停止しない(同130条)。
なお、投票権者は「年齢満18年以上の者」(同3条)とされているが、そのために必要な法制上の措置がとられないかぎり(現時点でまだとられていない)、20歳以上の者とされている(同附則3条)。 |
(三) 天皇の公布
公布は「国民の名」で行われる。
これは、改正権者である国民の意思による改正であることを明らかにする趣旨である。
また、「この憲法と一体を成すものとして」とは、改正条項が「日本国憲法と同じ基本原理のうえにたち、同じ形式的効力をもつもの」であることを示す、と解する説が妥当であろう。
アメリカ合衆国憲法と同じ増補の方式を要求する趣旨だという特別の意味は、そこには含まれていない。
全部改正も、憲法改正権の限界を逸脱するものでないかぎり、必ずしも排除されているわけではないと解される。
◆3 憲法改正の限界
このような憲法改正手続に従えば、いかなる内容の改正を行うことも許されるかと言えば、けっしてそうではない。
この問題は、憲法、人権、国民主権等の本質をどのように考えるか、という憲法の基礎理論と密接に関連する。
我が国では、国民の主権は絶対的である(制憲権は全能であり、改正権はその制憲権と同じである)と考える理論、ないし憲法規範には上下の価値の序列を認めることは出来ないと考える理論に基づいて、憲法改正手続によりさえすれば、いかなる内容の改正も法的に許されると説く無限界説もある。
しかし、法的な限界が存するとする説が通説であり、かつ、それが妥当と解される。
この限界説の論拠として説かれている理由で重要なものは、次の二つである。
(一) 権力の段階構造
民主主義に基づく憲法は、国民の憲法制定権力(制憲権)によって制定される法である。
この制憲権は、憲法の外にあって憲法を作る力であるから、実定法上の権力ではない。
そこで、近代憲法では、法治主義や合理主義の思想の影響も受けて、制憲権を憲法典の中に取り込み、それを国民主権の原則として宣言するのが、だいたいの例となっている。
また、その思想は、憲法改正を決定する最終の権限を国民(有権者)に与える憲法改正手続規定にも、具体化されている(日本国憲法96条の定める国民投票制はその典型的な例である)。
憲法改正権が「制度化された憲法制定権力」とも呼ばれるのは、そのためである。
このように、改正権の生みの親は制憲権であるから、改正権が自己の存立の基盤とも言うべき制憲権の所在(国民主権)を変更することは、いわば自殺行為であって理論的には許されない、と言わなければならない。
(ニ) 人権の根本規範性
近代憲法は、本来、「人間は生まれながらにして自由であり、平等である」という自然権の思想を、国民に「憲法を作る力」(制憲権)が存するという考え方に基づいて、成文化した法である(第一章四2参照)。
この人権(自由の原理)と(一)にふれた国民主権(民主の原理)とが、ともに「個人の尊厳」の原理に支えられ不可分に結び合って共存の関係にあるのが、近代憲法の本質であり理念である(第三章一2参照)。
従って、憲法改正権は、このような憲法の中の「根本規範」とも言うべき人権宣言の基本原則を改変することは、許されない(前頁の図を参照)。
もっとも、基本原則が維持されるかぎり、個々の人権規定に補正を施すなど改正を加えることは、当然に認められる。
(三) 前文の趣旨
日本国憲法は、前文で、人権と国民主権を「人類普遍の原理」だとし、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と宣言している。
これは、ただ政治的希望を表明したものではなく、以上のような、憲法改正に法的な限界があるという理論を確認し、改正権に対して注意を促す意味をもっている。
ドイツ連邦共和国憲法が、国民主権と人権の基本原則に影響を及ぼす改正は許されないと定め(79条)、フランス第五共和制憲法が、共和政体を改正することはできないと定めている(89条)のも、同じ趣旨である。
(四) 平和主義・憲法改正手続
改正権に限界があるとすると、国内の民主主義(人権と国民主権)と不可分に結び合って近代公法の進化を支配してきた原則と言われる国際平和の原理も、改正権の範囲外にあると考えなくてはならない。
もっとも、それは、戦力不保持を定める9条2項の改正まで理論上不可能である、ということを意味するわけではない(現在の国際情勢で軍隊の保有はただちに平和主義の否定につながらないから)、と解するのが通説である。
なお、憲法96条の定める憲法改正国民投票制は、国民の制憲権の思想を端的に具体化したものであり、これを廃止することは国民主権の原理を揺るがす意味をもつので、改正は許されないと一般に考えられている。
◆4 憲法の変遷
憲法の保障にとってきわめて重要な問題は、憲法規範は改正されないのに、その本来の意味が国家権力による運用によって変化することである。
もっとも、憲法も変転する社会の動態の下で「生ける法」であるから、憲法規範の本来の意味に変化が起こり、その趣旨・目的を拡充させるような憲法現実が存在すること、これは当然の現象で、とくに問題とする必要はない。
問題は、規範に真正面から反するような現実が生起し、それが、一定の段階に達したとき、規範を改正したのと同じような法的効果を生ずると解することができるかどうか、《そういう意味の》「憲法の変遷」が認められるか、ということである。
これについては、
| ① |
一定の要件(継続・反復および国民の同意等)が充たされた場合には、違憲の憲法現実が法的性格を帯び、憲法規範を改廃する効力をもつと解する説と、 |
| ② |
違憲の憲法現実は、あくまでも事実にしかすぎず、法的性格をもち得ないと解する説 |
とが、厳しく対立している。
基本的には②説の立場をとりながら、《政治的な》ルール(これをイギリス法に倣って憲法の習律〔convention〕と言ってもよい)として国家機関(議会・内閣)を拘束する一種の弱い法的性格をもつことを認める考え方もある、
およそ、法が法としての効力をもつには、国民を拘束し、国民に遵守を要求する「拘束性」の要素と、現実に守られていなければならないとする「実効性」の要素が必要である。
憲法変遷を肯定する説のうち問題であるのは、実効性が失われた憲法規範はもはや法とは言えない、という立場をとるものである。
しかし、いかなる段階で実効性が消滅したと解することができるのか、その時点を適切に捉えることは容易ではない。
また、実効性が大きく気傷つけられ、現実に遵守されていなくとも、法として拘束性の要素は消滅しないと解することは可能であり、将来、国民の意識の変化によって、仮死の状態にあった憲法規定が息を吹きかえすことはあり得る。
①説の理論を安易に肯定することはできない。
最終更新:2013年04月30日 17:13